
パートをするようになると気になるのが、年収が課税対象になるのかどうかですよね。
初めてのパートなどとなると、年末に確定申告が必要になるのかどうかなども気になります。
とりあえず、面接のときには「扶養控除内で」と言っていても、実際のところどうなのか。
残業など重なり、思ったよりも収入があった場合など。
この記事では、確定申告が必要な場合と、必要ではない場合、またその方法などについて、詳しく見ていきましょう。
パートだったら確定申告が必要か必要ないのか?

まず、確定申告はその年の所得を税務署に申告して、結果納税をするために行う作業です。
個人事業主だとかフリーランスで所得を得ている人は、もれなく確定申告をする必要があります。
パート従業員の方の場合は、源泉徴収で年末調整をされているかどうかが前提で、2つのパターンに分かれます。
税金は、未納の場合は所轄の部署から納税の案内がきますが、払い過ぎている場合は、だれも教えてくれません。
自分で、状況を把握し対応する必要があります。
これって、親切ではないなぁと昔から思います。
結局は、自分が賢くないと損をしてしまうのですね。
パートの確定申告は扶養内で働いていれば必要ない?
パートをされている方の中には、夫や親の扶養に入っている方も多いですよね。
「扶養内で働くことのできる年収の上限」を確認しましょう。
でも、それぞれのケースで確定申告が必要かどうか、確定申告が必要だった場合。
どういうことに、気を付ければいいのでしょうか?
いわゆる103万円の壁です。
年収が103万円以下の方に確定申告の義務はありません。
ただ、下記の条件に両方当てはまる方は、確定申告をすることで「税金の還付」を受けられる可能性が高いです。
- 年末調整を受けていない
- パート代から源泉徴収をされている
年収100万超の人は住民税にも注意が必要!
注意しなければならないのは住民税です。
所得税をメインにお話してきましたが、所得税だけでなく住民税も給料から引かれていますよね。
住民税が免除されるのは年収100万(市町村により前後あり)です。
年収が103万だと所得税がかからなくても、住民税がかかることはあります。
なので、パート収入が100万円超103万円以下の場合は、確定申告で控除を利用することで住民税も非課税となる可能性があります。
利用できる控除がある場合は、確定申告を検討してみてもいいでしょう。
配偶者や親が年末調整や確定申告で「配偶者控除」「扶養控除」といった控除を利用できなくなり、税金の負担が重くなるパターンです。
ただし、配偶者の年収が201万円以下であれば「配偶者特別控除」という控除を利用することができます。
働く前まで家族の扶養に入っていた人は、、扶養から外れて自身で
- 国民年金
- 国民健康保険
また、社会保険料も支払う必要があります。
社会保険料をご自分で支払っている方は、年末調整あるいは確定申告で「社会保険料控除」を利用しましょう。
国民年金は毎月16,540円、国民健康保険は年収130万円の場合で年間にすると10万円前後引かれます。
これは結構大きな負担となりますよね。
なので、年収130万円のラインには十分注意が必要です。
年収130万円を超えるようになったら「社会保険料控除」を利用する
年収が130万円を超えて、給料から社会保険証を引かれているのであれば。
確定申告をすることで「社会保険料の控除」を受けることができます。
社会保険料の控除を受けるには、社会保険料として支払った額を記載して、国民年金の控除証明書を添付することが必要になります。
年収103万におさえたつもりが計算ミス!救済措置はある?
この場合、あなたの配偶者や親は本来は対象外となる「配偶者控除」や「扶養控除」を年末調整で利用してしまっている状況です。
年末調整が行える期限は翌年1月31日です。
なので、それまでに会社に申告をすれば、配偶者や親の勤務先で年末調整の内容を修正をしてもらえることが可能です。
どちらにしても、分かった時点でなるべく早く相談することをおすすめします。
源泉徴収されていない場合はどうしたらいい?
源泉徴収されていない場合は、1年間の給与所得が103万円を超えた場合に所得税が課税されます。
なので、確定申告が必要となります。
源泉徴収票をもらっていない…パートさんが確定申告をするなら
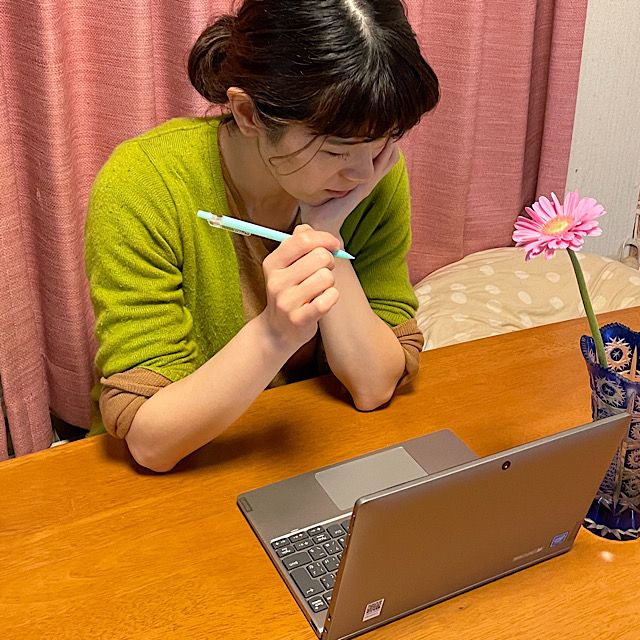
源泉徴収票をもらえていない場合は、税務署に相談をしましょう。
自分が納税を行っている市が所轄する税務署に行き「源泉徴収不交付の届出書」というのを提出します。
この時に、もし給料明細を保管しているのであれば持参することをおすすめします。
実際に「源泉徴収票の不交付の届出書」を出した方は。
税務署の職員の方から「念のため、社長の自宅・携帯など可能な限りの連絡先を教えてください」と言われ、しっかりと対応をしてくれるようです。
かなり大げさな手続きだなぁと思うかもしれませんが、所得税法という法律で源泉徴収票の発行をすることは会社に義務づけされているのです。
所得税法226条には、次のような規定があります。
その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、
その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない(一部省略)」
源泉徴収票を発行しない会社にはそれなりの理由や共通点がある
そもそも、源泉徴収票の発行をしていないような会社は「業績が悪かったり」「まだ社歴が浅かったり」といった傾向があります。
このような会社の中に、年に一回おこなう決算処理、確定申告を行うだけで大仕事。
いっぱい、いっぱいとなり、従業員への源泉徴収票の発行作業まで手が回らないということも。
だからといって、発行しなくてもよい、ということにはなりません。
経営者側からみても源泉徴収票を不交付する状況を放置しておくことは税務調査が入った場合、源泉徴収票を発行していないということは税務署も把握しています。
なので、発行していないということは、何か後ろめたいことがあるのでは?
人件費の架空計上をしているのでは?と疑われる理由にもなります。
親族経営の会社であっても、同じです。
- 所定の源泉所得税を差し引く義務
- 源泉徴収票を発行する義務
源泉徴収票を発行することでの支払先のメリット
給料の支払いを行っている側(勤務先)からみると。
源泉徴収票を発行することで「会社は、源泉徴収義務を果たしている。」といえます。
また、源泉徴収票を発行することで、税務署にも報告済みとなります。
なので、あとは労働者の自己責任で確定申告をするなり納税の処理を行ってください。
という、アピールになります。
発行依頼をかけているのに、なかなか手元に届かない方は「所得税法の規定に違反していませんか?」と声をかけてみましょう。
パートで確定申告しないとどうなる?罰則などはあるの?
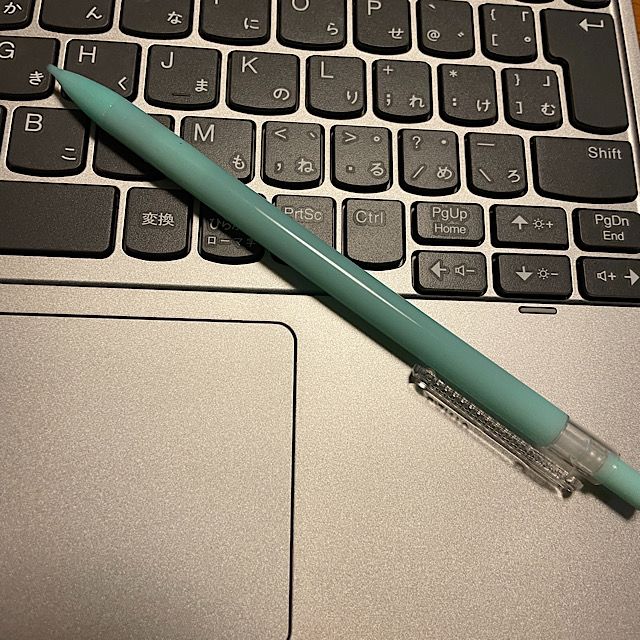
確定申告をしない場合によっては、後から税金を追徴されたり、罰則を科せられることもあります。
「扶養内で働いているだけだから確定申告は関係ない」と思っていると損をしてしまうこともあります。
確定申告が必要かどうか、自分自身のケースに当てはめて考えてみましょう。
確定申告義務があるのに確定申告をしなかったら
確定申告をしなければならない方が確定申告をしなかった場合、支払わなければならない所得税や住民税が正しく計算されません。
3月15日までに確定申告書を提出しなかった場合に、納付すべき所得税にプラスで課税されてしまいます。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 無申告加算税
- 50万円まで : 15%
- 50万円を超える部分 : 20%
確定申告の必要があると気が付いた場合には、すぐに税務署に連絡をして納税の意思を伝えましょう。
確定申告しなきゃだめ?パートを掛け持ちしている場合を解説
仕事を掛け持ちしてお給料をもらっている場合も確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
2カ所以上から給料取得が一定の収入としてある場合の確定申告対象者「20万円ルール」
年末調整を受ける会社のほかに、年間で給与取得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
2つ以上のお仕事を掛け持ちしていて、収入が一定額を超えている方が対象となります。
この20万円のルールは、副業が
「アルバイトやパートなのか」
「アルバイトやパート以外なのか」
によって内容がやや変わってきます。
副業の種類による20万円ルールの違い
ここからは、副業の種類による20万円ルールの違いを見ていきましょう。
アルバイトだとかパートの収入が「1年間で20万円以下」だったら、確定申告をする必要はありません。
この場合も、副業の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
アルバイトやパートの収入とそれ以外の所得の金額を合計して、20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
この結果から、パートの掛け持ちで片方の収入が年間20万円をこえない場合は確定申告の必要ななくなりますね。
20万円を超えている場合は、速やかに確定申告の手続きに入りましょう。
パートさんが確定申告するやり方!分かりやすく紹介します
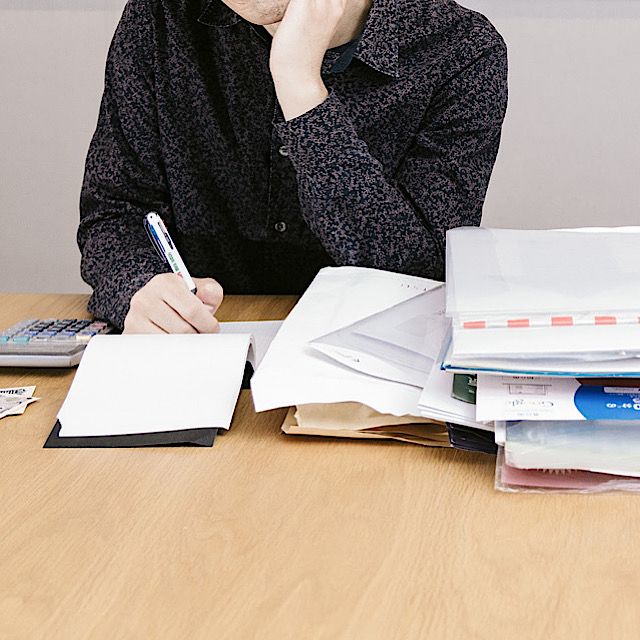
確定申告をした方がお得になることもあります。
このパターンに該当する人は、本来確定申告をする義務がありません。
しかし、確定申告をしないと払い過ぎた税金を還付されることはありません。
確定申告でどれくらいお得になる?
簡単な例を挙げて説明させていただきます。
確定申告をすることで、お給料から差し引かれた「3万円にかかる所得税額」が戻ってくる可能性があります。
戻ってくる税金がいくらになるかは、「控除」がどれくらいになるかに関わります。
なので、一概に金額は案内できません。
確定申告が必要かどうか、自分のケースでしっかり確認しましょう
確定申告の方法を簡単にご紹介!
確定申告と聞くと、「難しい」「ややこしい」「めんどうくさい」といいイメージは全くない人も多いかと思います。
わたしもそうです。
初めて私が確定申告をしたのは、出産をして産休に入った年でした。
医療費控除が受けられるということで、時間もあったので勇気を出して申請挑戦してみました。
また、ネットなどでもダウンロードが可能です。
申告書をもらいに行ったときに、受付の方にどういった理由で確定申告をしたいのかを聞かれます。
そこで、医療費控除や社会保険料の控除、など説明するとそれに必要な書類を用意してくれます。
なので、実際に申告をしたあとの書類不備を軽減することができます。
もらった書類はたくさんありますが、中に記載方法もあり細かくどこにどの金額を記入するかなど指示されています。
記載説明通りに書いていくと、簡単に作成することができました。
ネットでも簡単申告!
ネットやアプリを利用して申告することもできます。
聞かれたことに入力を進めていくと完了させることができます。
確定申告の時期には、税務署も混みあうので人混みを避ける意味でもネットを使うのはいいかもしれませんね。
確定申告が必要な人のまとめ

税金、確定申告など聞くとハードルが高く、理解しようとしても難しくて途中であきらめてしまうとこもありますよね。
パート収入の申告だけでなく、ふるさと納税や、住宅ローンの控除、医療費控除など知らないと損してしまう情報もたくさんあります。
せっかく働いてもらえたお金を大切にしてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
