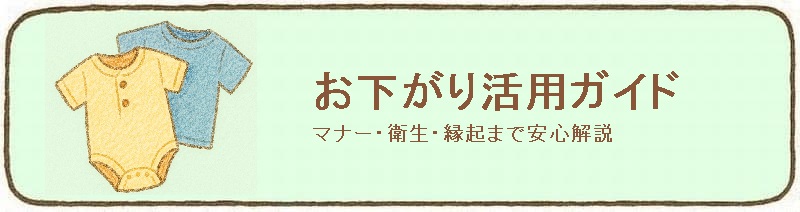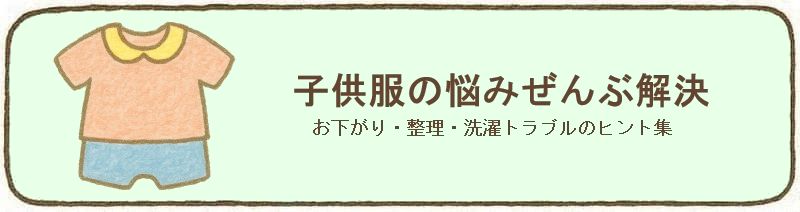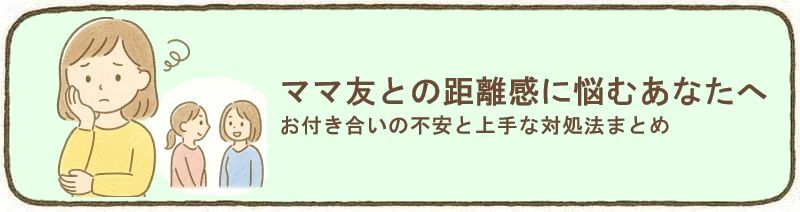子どもって、本当にあっという間に大きくなっていきますよね。
少し前までダブダブだったロンパースが、気づけばパツパツになっていて「え、もうこのサイズ?」と驚くこともしばしば。
成長は嬉しい反面、そのたびに買い替えなきゃいけない洋服代に、ため息をついたことがある人も多いのではないでしょうか。
特に乳幼児期は成長スピードが早く、着られる期間が短いうえに、保育園用・外出用・季節ごとの準備まで必要で、服にかかる費用も馬鹿になりません。
そんなとき、ふと思い出すのが「お下がり」という選択肢。
上の子のおさがりを使ったり、親戚や友人から譲ってもらえたりすることもありますよね。
ただ、それに対して「ありがたい!」と感じる人もいれば、「できれば新品を着せたい」と考える人もいるのが正直なところです。
どちらの考えにも、それぞれの事情や価値観があって当然。
だからこそ大切なのは、「どっちが正しいか」ではなく、「自分たちにとってどんな選択が心地よいのか」を見つけることだと思うのです。
この記事では、そのヒントを丁寧に探っていきます。
お下がりを「ありがたい」と思える瞬間
服が必要なタイミングって、なぜか重なる
子育てをしていると、「どうして今このタイミングで…」と思うような出来事が本当に多くあります。
急に寒くなった日や、保育園で泥んこ遊びをして服が足りなくなった日、新しい季節が始まって「あ、去年の服、もうサイズが合わない…」と気づいたとき。
そんな場面に限って、洗濯物が乾かない日が続いていたりして、焦る気持ちがどんどん積み重なっていきます。
そんな中で、タイミングよく「よかったらこれ使う?」と誰かから差し出された子ども服があったら、それはもう天の助けに思えることすらあるんです。
しかも、サイズがピッタリだったり、うちの子の好きなキャラクターがプリントされていたりしたら、ちょっと鳥肌が立つくらいに感動します。
お下がりって、単に「物をもらう」だけではないんですよね。
大変な時期に「ひとりじゃないよ」って背中をトントンしてもらえたような、そんな安心感も一緒に受け取っているような気がするのです。
「お金が浮く」以上に嬉しいこと
もちろん、経済的な面で助かるというのは、お下がりの大きなメリットのひとつです。
新品の子ども服は1枚1000円を軽く超えることも珍しくありませんし、それが何枚も必要となれば、家計にとっては大きな負担になります。
実際、国の調査※でも、子育て世帯の衣類関連の出費は決して少なくないことが報告されています。
でも、お下がりを使って感じる嬉しさって、単に「お金が浮いた」という数字以上のところにある気がします。
それは、誰かが「あなたの子どもにこれを着てもらいたい」と思って大切に残してくれていたということ。
服の中に、その人の想いや優しさが込められていると感じることがあるんです。
私が以前もらったお下がりの中に、小さな手紙が添えられていたことがありました。
「この服、うちの子のお気に入りでした。気に入ってもらえたら嬉しいです」と。
その瞬間、服が“単なる物”から“誰かの思い出”に変わって見えて、涙が出そうになりました。
こうした体験をすると、「お下がりって悪くないな」と素直に思えるようになります。
ただの節約ツールではなく、人と人のつながりを感じられる、あたたかい循環の一部なんだと気づかされるのです。
※衣類の出費に関する参考:家計調査報告(総務省統計局)
お下がりに抵抗があるのは、心が繊細な証拠
「いらない派」は決して冷たいわけじゃない
「お下がり?ありがたいって思えない…」そう感じる自分に、どこか罪悪感を覚えたことはありませんか?
でもね、それって全然悪いことじゃないんです。
むしろ、あなたの心がまっすぐで繊細だからこそ。
たとえば「誰が使ったかわからない服をわが子に着せるのはちょっと…」と思ったり、「汚れやシミが気になってしまう」と感じるのは、ごく自然な感情です。
清潔なものを着せたい、衛生的な環境で過ごしてほしいという気持ちは、親なら誰しもが抱く大切な思いですよね。
実際、私も第一子のときはまさにそうでした。
はじめての育児で、なにをどう選べば正解なのかもわからないなか、「せめて服だけはちゃんとしたものを着せよう」と、見た目も素材もこだわって選んでいたことをよく覚えています。
今思えば、その気持ちの奥には「ちゃんと育ててるって思われたい」という、ちょっとした不安やプライドもあったのかもしれません。
でも、それも含めてすべて“愛情の形”なんです。
誰かにとっての「ありがたい」は、別の誰かにとっての「ちょっと違う」になることもあります。
だからこそ、無理して「もらわなきゃ」「活用しなきゃ」と思わなくてもいいんですよ。
衛生面の不安は「感じて当たり前」
YMYL的にも大切なのが、健康や衛生面に関する安心感。
お下がりに対して「なんとなく不衛生に感じてしまう」という不安の声も多く聞かれますが、それは理屈ではなく感覚の話。
だからこそ否定せず、きちんと向き合っていくことが大切です。
でも実は、家庭でできる対策もたくさんあります。
例えば、衣類専用の除菌スプレーや、敏感肌にも使える無添加洗剤を使って丁寧に洗えば、衛生面の不安はかなり和らぎます。
熱めのお湯でつけ置き洗いをしたり、天日干しをするだけでも、見えない汚れや菌を減らす効果が期待できるとされています。
さらに、最近では感染症対策への意識の高まりもあって、消毒や除菌の知識やアイテムも豊富になってきました。
「誰かが使ったから不安」ではなく、「使う前にしっかりケアすれば大丈夫」という選択肢も、これからの時代には十分現実的です。
何よりも、「安心できる方法を自分で選ぶ」ということが、家族にとっていちばん心地よい選択になります。
情報を知って納得して決めることで、「誰かに合わせる子育て」から「自分たちに合った子育て」へと、少しずつ切り替えていけるはずです。
お下がりが役に立った瞬間と、心が変わったきっかけ
子どもが小さいうちは、「とにかくなんでも新品で揃えたい」と思っていた私。
とくに第一子のときは、おもちゃもベビーカーも肌着も、全部ピカピカじゃなきゃ気が済まなかった。
“我が子にふさわしいもの”という目線でしか物が選べなくて、たとえ親切に「これ使う?」と差し出されたお下がりでも、笑顔で断っていた時期がありました。
でも、それがガラリと変わったのは、子どもが2人になったある日。
上の子が熱を出して保育園をお休み、下の子は離乳食を始めたばかりで毎日ぐっちゃぐちゃ。
買い物にも出られず、洗濯物は追いつかず、気持ちも体力もギリギリだったとき、ふと押し入れの奥から出てきたのが、以前もらってそのままにしていたお下がりの箱でした。
「たしか友だちがくれたやつだな…」と半信半疑で開けてみたら、
中には、まだタグ付きのままのロンパースや、肌触りの良い綿素材の服がたくさん入っていて、しかも今のサイズにぴったり。
思わず「神…!」と声が出そうになったのを覚えています。
そこからです。
私の中で、“お下がり=他人が使った物”という固定観念がほどけていったのは。
「もったいない」より「ありがたい」が勝った瞬間
正直、お下がりをもらったときに感じていた“もったいないからとっておくけど、多分使わないだろうな”という気持ち。
あのときの私は、「汚れていたら嫌だな」「自分の好みじゃないな」と、使う前から勝手に決めつけていたのだと思います。
でもいざ使ってみたら、それまでのこだわりが一気に吹き飛んで、むしろ「なんで今まで使わなかったんだろう」と思えるほど快適でした。
洗って柔らかくなった生地が赤ちゃんの肌にちょうどよくて、着せるたびに「これ、ほんとに良い服だなあ」としみじみ感じるように。
そしてなにより、「あのときの私を思って残してくれていたんだ」と気づいた瞬間、モノの向こう側にあった誰かの優しさにじんとしました。
その服には、その人の子どもが過ごした時間も、たくさんの思い出も一緒に詰まっていたんですよね。
考え方が変わるのは、悪いことじゃない
最初は頑なに「いらない派」だったとしても、何かの拍子に「いる派」へと気持ちが変わることは、全然おかしくないし、むしろ自然なことだと思います。
それは決してブレたとか、こだわりがなくなったわけじゃなくて、「経験によって価値観が柔らかくなった」という成長の証なのかもしれません。
育児って、最初から正解なんてわからなくて、日々の中でちょっとずつ「わたしなりの正解」を見つけていくものですよね。
お下がりに対する気持ちも、その一部なのだと思います。
だからもし今、どちらかで迷っているなら、無理に決めつけなくて大丈夫。
あなたのペースで、あなたの選択でいいんです。
着なくなった子供服をどうする?おすすめの手放し方
子どもが成長するのは嬉しいけれど、どんどん増えていく“サイズアウトした服”に、ある日ふとため息がこぼれることってありませんか?
特に1歳~3歳くらいまでは、ほんの数ヶ月でサイズが変わることもあって、まだ着られそうなのにタンスの奥にしまったまま…なんて服がどんどん積み重なっていくんですよね。
- まだきれいだし、誰かに使ってもらえたら
- でも、捨てるには惜しいし、どうすればいいんだろう
そんなときにおすすめしたいのが、フリマアプリや寄付活動といった「無理なく、誰かにバトンを渡せる方法」です。
子ども服の“第二の人生”を考えてあげるような感覚で、優しさと実用性の両方を叶えられる選択肢をご紹介します。
フリマアプリは、お下がりをつなぐ新しいかたち
最近では、育児中のママたちの間でも当たり前になってきたフリマアプリ。
「メルカリ」や「ラクマ」など、大手のアプリを使えば、匿名でのやり取りや安心の取引サポートも充実しているので、初めてでも不安は少なめです。
我が家でも、着られなくなったロンパースやパーカーをフリマアプリに出品したところ、すぐに「探していました!」というコメントと一緒に購入されたことがありました。
「必要としている誰かに、ちょうど届いたんだ」と思うと、ただの“いらない服”が、“誰かの役に立つモノ”に変わる瞬間に立ち会えた気がして、じんわりと嬉しくなりました。
もちろん、出品や梱包、発送の手間はゼロではありません。
でも、家の中が少し片付いて、しかも少額でもお金に換えられるなら、気持ち的にもリフレッシュにつながるという声はとても多いんです。
YMYLの観点から見ても、しっかり衛生的に洗濯・除菌した上で販売することや、商品説明に
- 何回着用したか
- 目立つ汚れがあるか
“信頼できるお下がり”というかたちで、次のご家庭に渡っていくなら、それはもう立派な社会的貢献です。
寄付というあたたかい選択肢も
もうひとつ、ぜひ知っておいてほしいのが「寄付」という選択肢。
日本国内でも、子ども支援団体や母子家庭支援施設、保育所などに向けた衣類の寄付活動が数多く存在します。
また、海外支援プロジェクトとして発展途上国へ届けられる活動もあり、しっかりとした団体を選べば、安全で意義のある支援が可能です。
フリマアプリのように収益が出るわけではないけれど、あのとき着ていた小さな服が、またどこかの誰かの暮らしを支えることになる。
その想像だけでも、心がほっとあたたかくなるのを感じるはずです。
もちろん、寄付する前には洗濯をして、なるべく状態の良いものを選ぶことが大切。
肌着や下着などは受け付けていない団体もあるので、事前に確認しておくと安心です。
「捨てられない思い出」を、無理に捨てなくてもいい
それでも、「これは特別だったから」「この服は思い出があるから」と、どうしても手放せないものがあることも、全然おかしくないんです。
それはきっと、服そのものよりも、その服を着ていた“あの時間”を覚えていたいから。
そんなときは、無理に処分せず、思い出ボックスに数点だけ残しておくのもひとつの方法。
あるいは、写真に撮ってアルバムに残すという手段もあります。
手放すことがすべてではありません。
「ありがとう」と思えたとき、「次に活かしたい」と思えたとき、それが“手放すタイミング”なんだと思います。
お下がりをどう捉えるかは、愛のかたちのひとつ
「大事にしたい気持ち」はどちらにもある
お下がりをもらうこと、使うこと、そして手放すこと。
それぞれに対して人によって感じ方が違うのは、当たり前のことだと思います。
たとえば
- 「せっかく譲ってもらったけど、使うかどうかはわからない」と迷ったり
- 「なんとなく気が進まないけど、失礼にならないように受け取っておこう」と戸惑ったり
- 「この服、大切にしてくれていたんだな」と感謝が込み上げてきたり…
新品にこだわる人もいれば、もらえるものはありがたく使いたいという人もいる。
どちらが正解というわけではなく、どちらの中にも、しっかりとした“親の愛”が存在しています。
たとえば「うちの子には新品を着せたい」と思う人の中には、
- 「この子のためにちゃんと準備してあげたい」
- 「きれいなものを着せてあげるのが私なりの愛情」
一方で「お下がりで十分」と思う人にも、
- 「ものを大事にする心を伝えたい」
- 「家計を守ることも家族の幸せのため」
そのどちらも、すごく尊いし、どちらも間違いなんかじゃない。
むしろ“どちらにも大事にしたい気持ち”がちゃんとあるからこそ、選び方に違いが出るのだと思うんです。
愛情のかたちはひとつじゃなくていい
子育てって、正解があるようでなくて、日々迷って、考えて、決めて、また迷って…
その繰り返しの中で「自分らしいやり方」が見えてくるものですよね。
お下がりに対する考え方も、それと同じ。
最初は抵抗があっても、時間が経つにつれて気持ちがやわらかくなったり、誰かの優しさに触れて考えが変わったりすることだって、自然な流れです。
だから、「いる派」「いらない派」といった言葉で分けるよりも、
「今の自分にとって、何が心地よいか」「この子にとって、どんな選択がやさしいか」
そうやって少しずつ、暮らしの中で選び取っていけばいいんじゃないかと思います。
そして、たとえ考えが変わったとしても、それは恥ずかしいことじゃない。
むしろ、変われたこと自体が、経験を通して得た柔らかさや、気づきの証なんです。
お下がりをどう捉えるか。
それは他人に決められるものではなくて、あなた自身の「家族を想う心」が自然に導いてくれる答え。
どんな選択をしても、そこに愛があるなら、それはもう、十分に正しい選び方なんだと思います。
まとめ
お下がりって、ただの服の話のようでいて、実はすごく繊細で、感情や価値観がぎゅっと詰まったテーマなのだと、あらためて感じます。
「いるか、いらないか」だけでは測れない、たくさんの背景や想いが、それぞれの家庭の中にちゃんと存在しているんですよね。
譲る人にも、もらう人にも、そして使う人にも、それぞれの“やさしさ”や“こだわり”があります。
「汚れていたらいやだな」「誰が着たかわからないと不安」と感じることもあれば、「物を大切に使いたい」「節約になるから助かる」と感じることもあって、どちらの気持ちにもちゃんと理由がある。
YMYLの観点でも大切なのは、“正しさ”よりも“納得感”。
誰かに決められた答えではなく、自分自身の価値観や生活スタイル、そして子どもへの想いに寄り添って、「今のわたしが心地よくいられる選択」をしていくことこそが、本当に大切なことなのだと思います。
もしも、今クローゼットに眠っているお下がりたちを見て、少しでも心が動いたなら、それはあなたの中に“やさしい選択”をしたい気持ちが芽生えている証拠かもしれません。
無理せず、自分のペースで。
あなたらしい子育てのかたちを、これからも大切にしていってくださいね。