 言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学 「かるた」の漢字と由来を知るともっと楽しい!歴史や意味をやさしく解説
「かるたって、漢字で書くとどうなるの?」と子どもに聞かれて、答えに詰まってしまったことがありました。私自身、かるた遊びは好きでしたが、そこまで深く考えたことがなかったので、その場でスマホを取り出して調べてみたんです。すると「歌留多」という漢...
 言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学 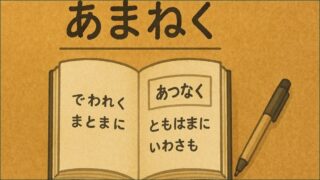 言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学 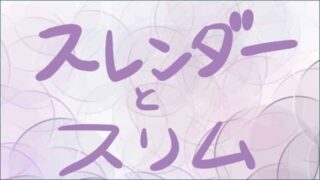 言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学