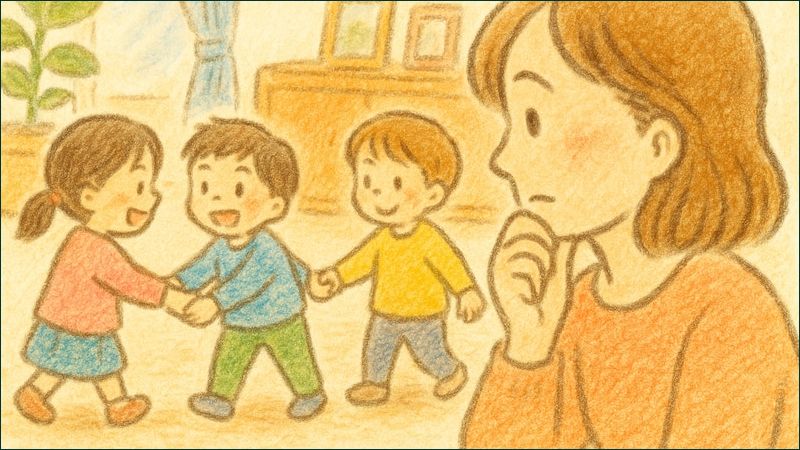
子どものころに「はないちもんめ」で遊んだ経験がある、という方は多いかもしれませんね。
学校の校庭や公園、放課後の時間などに、わらべ歌に合わせて友達と手をつないで遊んだ記憶がよみがえる方もいるのではないでしょうか。
懐かしさとともに、楽しかった思い出がある一方で、実はこの遊びが今の時代では問題視されることも増えてきています。
最近では、「はないちもんめ」を禁止にしている学校や保育園も出てきているんです。
昔から伝わる素朴な遊びのひとつだと思っていたのに、どうして禁止されるようになっているのでしょうか?
その背景には、現代ならではの子ども同士の関係性や、いじめなどのトラブルの問題が関係していると言われています。
この記事では、「はないちもんめ」がなぜ禁止されるようになっているのか、その理由や背景をできるだけわかりやすく解説しながら、
「本当にこの遊びを禁止するべきなのか?」
という問いについても一緒に考えていきたいと思います。
今まで深く考えたことがなかった方も、この記事を読んでいただくことで、子どもの遊びを見直すきっかけになるかもしれません。
はないちもんめは本当に禁止にすべき?
はないちもんめとはどんな遊び?
はないちもんめは、昔から親しまれてきたわらべ歌に合わせて楽しむ、子どもたちのチーム対抗型の遊びです。
遊び方としては、ふたつのグループが向かい合って手をつなぎ、「勝ってうれしい はないちもんめ~」という歌を一緒に歌いながら前後に揺れます。
そして歌の後半になると、どの子がほしいかをチームごとに相談し、相手チームの子を一人指名します。
選ばれた子同士がじゃんけんをして、勝ったチームにその子が移動するという流れです。
このように
- 歌
- 相談
- じゃんけん
- 移動
多くの人が幼少期に一度は体験したことがあるような、懐かしい遊びのひとつですね。
最近なぜ「禁止」が話題になっているの?
ところが、近年ではこの「はないちもんめ」が学校や保育園などで禁止になるケースも出てきています。
その理由としてよく挙げられるのが、「いじめにつながる可能性があるのでは?」という懸念です。
具体的には、「ほしい子を決める」というルールが、子どもたちの間に人気・不人気の線引きを生み、選ばれない子が傷ついてしまうという心配があります。
いつも選ばれる子と、毎回最後まで残ってしまう子が分かれてしまうことで、遊びの場面が子ども同士の関係性を浮き彫りにし、仲間外れの原因になることも。
また、大人であれば「ただのゲームだし気にしない」と割り切れる場面でも、まだ心が成長途中の子どもたちにとっては、選ばれなかったという事実が強く印象に残ってしまい、自己肯定感を下げるきっかけになってしまうこともあるのです。
こうした理由から、保護者や教育現場の先生たちの間で見直しの声が高まり、
「はないちもんめはもう教えない」
「遊び時間でやらないように指導する」
といった対応が増えてきているのです。
禁止にした学校や園の具体的な理由とは?
実際に「はないちもんめ」を禁止している保育園や小学校では、いくつかの共通した問題点が指摘されています。
たとえば、
- 「子ども同士のトラブルが増えた」
- 「遊びのあとに泣いてしまう子がいる」
- 「特定の子が繰り返し選ばれずに自信をなくしてしまう」
特に、何度も選ばれない子が出てしまうことで、
- 「どうせ私なんて…」と自分に対してネガティブな気持ちを抱くようになったり
- 選ばれた子が無意識に優越感を持ってしまったり
また、遊びの中でのやりとりがきっかけで、日常生活の中にも人間関係のぎくしゃくが持ち込まれるケースも報告されています。
友達の間で
「なんであの子を選んだの?」
「あの子を選ばなかったのは意地悪」
といったような発言が出てしまうこともあり、先生たちも細かいケアを必要とする場面が多くなるそうです。
このように、ぱっと見にはにぎやかで楽しそうな「はないちもんめ」でも、その裏で心を傷つけてしまう子がいるという点が、禁止に踏み切る大きな理由となっています。
はないちもんめが禁止される理由
遊びの中に“いじめ”の構図がある?
はないちもんめの中では、相手チームの子をひとり選ぶという場面がありますよね。
この「選ぶ・選ばれない」という構図が、実は子ども同士の間にある
- 序列
- 人気の差
たとえば、毎回選ばれる子がいる一方で、何度やっても一度も選ばれない子がいたとします。
その状況が続くことで、選ばれなかった子は
「自分は必要とされていない」
「みんなに嫌われているのかも」
と感じてしまい、ただの遊びだったはずの場面で深く傷ついてしまうこともあります。
一方、選ばれる側の子どもにもプレッシャーはあります。
- 「なんで自分が選ばれたの?」と戸惑ったり
- 「次も選ばれなきゃいけない」という妙な競争意識が芽生えたり
このように、単純なルールに見えても、子どもたちの心の中では複雑な感情が入り交じっている可能性があるという点に、大人たちは注意を向ける必要があります。
仲間外れや人間関係のトラブルが起きやすい
「いつも残る子」「いつも選ばれる子」というように、遊びの中での役割が固定化されてしまうことがあります。
こうした状態が続くと、子どもたちの間で無意識のうちに“ランクづけ”のような感覚が生まれてしまい、
「あの子は選ばれない子」
「この子は人気者」
といった目で見られるようになるんです。
また、遊びの中で交わされる言葉の中にも、小さなトゲが隠れていることがあります。
「なんで○○ちゃんを選ばなかったの?」とか、「○○はいつも最後まで残ってるね」などの言葉が、仲間外れや人間関係の悪化につながることも。
本来、遊びは子どもたちが楽しく過ごし、互いに関わり合うことで学びや喜びを感じられる場であるはずです。
けれども、はないちもんめのように
- 選ぶ
- 選ばれない
教師や保護者からの心配の声が増えている
現場で子どもたちと日々関わっている先生たちや、家庭で子育てをしている保護者の方々からは、
「はないちもんめのような遊びが、子どもにとって本当に安全なのか?」
という疑問や不安の声がたびたび上がっています。
とくに、
- 「選ばれなかった子が悲しい思いをしていないか」
- 「目立たない形でいじめが始まっているのではないか」
子どもたちは日々の遊びを通じてたくさんのことを学びますが、その中で受ける言葉や態度の影響もとても大きいものです。
大人が気づかないうちに、遊びの中で心が傷ついていたり、自信をなくしていたりするケースもあるのです。
そのため、遊びの内容やルールに目を配り、些細なサインも見逃さないようにすることが、先生や保護者には求められています。
また、保護者の中には、子どもが家に帰ってきて「今日は○○ちゃんが選ばれなかった」とポツリと言ったことから問題に気づいたという方もいます。
本人は何気なく話したつもりでも、実際にはその場で誰かが傷ついていたかもしれません。
こういった小さな気づきを積み重ねて、遊びのあり方を見直す動きが広がっているのです。
だからこそ、ただ禁止にするかどうかだけではなく、「どんな遊びが子どもにとって本当に良いのか?」を大人が一緒に考え、安心して遊べる環境をつくるためのサポートが大切になってきています。
でも「はないちもんめ」には良い面もある
ルールを守る力や協調性が身につく
はないちもんめは、チームで相談して作戦を立てたり、じゃんけんの結果を受け入れたりする中で、子どもたちが自然とルールを守る大切さを学べる遊びです。
誰かが勝って誰かが負けるというシンプルなルールの中で、悔しさを受け入れる力や、相手の立場を考える気持ちが育まれていきます。
また、チームで作戦を立てる過程では、意見を出し合ったり、相手を思いやって譲ったりする場面も出てきますよね。
こうしたやりとりを通して、協調性やコミュニケーション力といった、社会で生きていく上で欠かせない力が少しずつ育っていくんです。
大人が教え込まなくても、子ども同士のやり取りの中から自然と学べるというのが、こうした昔ながらの遊びのいいところだといえます。
さらに、遊びの中ではトラブルが起きることもありますが、それをどう乗り越えるかを自分たちで考えることも大きな学びになります。
先生や大人の手を借りずに、子どもたちが自分たちの中で解決していく姿は、とてもたくましいものです。
昔ながらの遊びでコミュニケーション力アップ
わらべ歌を使った遊びには、リズムや言葉のやりとりが含まれているので、子どもたちの言語発達や表現力の向上にもつながります。
「あの子がほしい」
「相談しよう」
といった掛け合いの中で、相手にどう伝えるかを考えたり、言葉のニュアンスを感じ取ったりと、実はたくさんのやりとりが詰まっているんですね。
また、グループで遊ぶことで、誰かが間違えてもそれを笑いに変えたり、困っている子に声をかけたりと、思いやりや共感の心も自然と育ちます。
今の時代、デジタル機器でのやり取りが多くなる中で、こうした顔と顔を合わせたコミュニケーションの経験はとても貴重です。
昔ながらの遊びには、単なる懐かしさだけではなく、子どもたちの人間関係づくりや心の発達を助けてくれる力があるんですね。
だからこそ、大人たちもその価値を見直して、どうすれば安全に続けられるかを一緒に考えていくことが大切です。
見直しや工夫で安全に楽しむ方法も
選ばれた子が移動するのではなく、じゃんけんで勝った子が称えられるなど、ルールを少し変えるだけで、トラブルのもとになる場面をやわらげることができそうです。
たとえば、選ばれた子が移動するのではなく、
- 勝った子に拍手を送ったり
- 特別なポーズを取って楽んだり
また、「あの子がほしい」などの直接的な表現を、「○○チームの仲間が増えたよ」などのやわらかい言い方に変えるだけでも、雰囲気はぐっと和らぎます。
歌詞や言葉の選び方にも一工夫加えることで、遊びに含まれる心理的なプレッシャーを減らすことができるんですね。
さらには、じゃんけんで勝った子が相手チームの誰かにありがとうのメッセージを伝える、などのコミュニケーション要素を取り入れるのもおすすめです。
遊びの中に自然とあたたかいやり取りが生まれれば、子どもたち同士の関係性もより良いものになっていくでしょう。
こうした少しの見直しや工夫で、古くからの遊びを今の時代に合わせて安全に楽しく続けていける可能性はじゅうぶんにあります。
大人が一緒に工夫しながら見守ってあげることで、子どもたちはより安心してのびのびと遊ぶことができますよ。
禁止にするだけでいいの?大人にできる工夫
ルールを工夫してトラブルを防ぐ
「選ぶ・選ばれる」という要素を取り除くだけでも、はないちもんめをもっと安全に楽しめる遊びに変えることができます。
たとえば、
- じゃんけんの勝ち抜き戦にする
- 歌のあとにランダムにペアを作ってじゃんけんする
- 勝った子がポーズを決めてみんなでマネする
また、役割をあらかじめローテーションにしておけば、「いつも選ばれない」「いつも同じ子が目立つ」といった状況も防げます。
ゲームのルール自体を柔らかくしておくことで、どの子も楽しく参加できるようになるんですね。
さらに、子どもたちはとても柔軟で創造力があります。
「こんなルールにしたら面白いかも!」と子ども自身が新しいアイデアを出してくれることもあります。
大人が方向性を示しつつも、子どもの意見やアイデアを取り入れることで、より楽しくて安全な遊び方が広がっていくでしょう。
子ども同士の関係を見守る姿勢が大切
禁止するだけではなく、大人がそっと寄り添って子どもたちの様子を見守ることも、とても大切です。
遊びの中でどんな言葉が交わされているか、どんな表情で遊んでいるかをしっかり観察することで、トラブルの兆しや子どもたちの心の動きをいち早く察知することができます。
また、子ども同士のちょっとした言い合いも、放っておくとあとあと大きな問題になることがあります。
そうなる前に、「何か困っていることある?」「どうやったらもっと楽しくできるかな?」と声をかけるだけでも、安心して遊べる雰囲気が生まれます。
遊びを見守る中で、子どもたち自身が自然と学び、気づきを得ていくようサポートすることが大人にできる一番の役割かもしれません。
目立たないサポートこそが、子どもたちの成長を支える大きな力になります。
他の遊びで代替できる?おすすめの遊び紹介
集団遊びをやめるのではなく、「フルーツバスケット」や「だるまさんがころんだ」など、ルールがシンプルで誰もが楽しめる遊びを取り入れてみてください。
こうした遊びは、年齢差や運動能力に左右されにくく、どの子も気軽に参加しやすいのが魅力です。
また、動きのある遊びの中でも、ルールが明確で公平なので、トラブルも起きにくくなります。
他にも「ハンカチ落とし」や「じゃんけん列車」など、誰かを選んだり排除したりしないタイプの遊びもおすすめです。
子どもたちが自然と協力し合い、みんなで笑い合えるような遊びを増やすことで、グループの雰囲気もぐっとよくなっていくでしょう。
みんなが主役になれる遊びを積極的に取り入れることで、子どもたちは自分の居場所を感じやすくなり、自然と笑顔も増えていきますよ。
まとめ:はないちもんめを禁止すべきかの判断ポイント

はないちもんめは、子どもの成長に良い影響を与える面もある一方で、
- 選ばれる
- 選ばれない
楽しく遊べて、コミュニケーション能力やルールを守る力を育てられる半面、その裏で一部の子が
- 孤立したり
- 心を痛めたり
だからこそ、大切なのは単純に「遊びをやめるかどうか」を白黒で判断することではなく、
「どうすれば子どもたちが安心して楽しく遊べるか」
「誰もが笑顔でいられる工夫はないか」
といった視点で考えることだと思います。
子どもたちは遊びの中で多くのことを学びますし、その経験が将来の人間関係や社会性の土台になっていくからです。
昔から受け継がれてきた遊びには、今の時代にそぐわない部分もあるかもしれません。
ですが、それをまるごと否定するのではなく、今の子どもたちに合った形に見直すことで、新たな価値が生まれるはずです。
ルールを工夫したり、大人がそっと見守ったりすることで、「はないちもんめ」が単なる遊び以上の、心あたたまる時間として子どもたちの記憶に残っていくと素敵ですね。