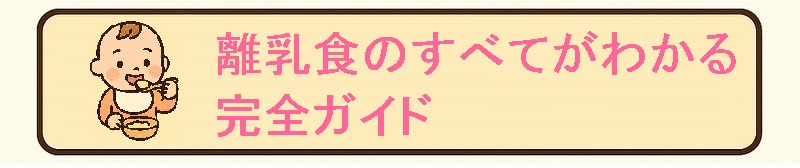はじめての離乳食づくりって、ほんとうに緊張しますよね。
おっぱいやミルク以外のものを口にするのが初めての赤ちゃんを前にして、
「これでいいのかな」
「ちゃんと飲み込めるのかな」
と心の中がそわそわしていたのを今でも覚えています。
スプーンをそっと口元に近づけたときの不安と期待、そして一口食べてくれた瞬間の安堵。
その小さな動作ひとつひとつが、親にとっては大きな一歩でした。
だけど、いざ始めてみると
「裏ごしって必要?」
「すりつぶすだけじゃダメなの?」
と、聞いたことはあっても具体的に何をどうすればいいのかわからないことだらけなんですよね。
ネットや本を調べても「どっちが正しいの?」と迷ってしまうし、周りのママたちの意見もさまざまで混乱してしまうこともあると思います。
でも、そんな不安を抱えるのは自然なことです。
なめらかな食感にする理由は、赤ちゃんの体の発達段階や飲み込む力に関係があるからで、決して「完璧にやらなければいけない」ものではありません。
大切なのは、赤ちゃんのペースに寄り添って「今のうちの子にはどんな形が合うのか」を感じ取ってあげることなんです。
ママやパパが“食べる練習”を見守りながら、その日その日の変化を楽しむようにすれば、離乳食づくりはぐっと気持ちがラクになりますよ。
「裏ごし」と「すりつぶし」、どう違うの?
見た目は似てるけど、実は全然ちがう
離乳食を始めたばかりの頃、「裏ごし」と「すりつぶし」ってどちらも“なめらかにする”って意味で使われがちですよね。
私自身もそうだったんですが、両方なんとなくやってるつもりだったのに、うまく飲み込めず赤ちゃんがベーッと吐き出してしまったことがあって、「えっ、やり方ちがうの?」と焦った覚えがあります。
実際には「すりつぶし」は、茹でたり蒸したりして柔らかくした食材を、スプーンやフォーク、ブレンダーなどを使って潰す工程のこと。
野菜や果物の繊維や粒感は多少残ってしまうこともありますが、比較的簡単にできて時短になります。
一方で「裏ごし」は、すりつぶしたものをさらに細かい網目の道具でこして、舌触りをより滑らかにし、固形や繊維を取り除いて飲み込みやすく仕上げる方法です。
つまり、すりつぶしよりも裏ごしのほうが、赤ちゃんにとって口あたりがやさしくて、ごっくんしやすい状態になります。
どちらが優れているということではなく、目的や赤ちゃんの成長段階によって使い分けるのがポイントなんですね。
「なめらかさ」には理由がある
生後5~6ヶ月頃に離乳食をスタートする赤ちゃんは、まだ舌を前後に動かす動きしかできずもぐもぐ噛むことも、左右に舌を使って食べ物を口の中で動かすことも難しい状態です。
この時期の赤ちゃんにとっては、噛むというより“飲み込む”ことが食事の中心なんですね。
そのため、食材に少しでも繊維や粒が残っていると、舌の上でうまくつぶせず、喉に引っかかったり、吐き出してしまったりすることもあります。
とくに、繊維の多い葉野菜や皮付きの果物、プチプチとした種のあるものは、大人にとっては気にならない程度でも、赤ちゃんにはかなり大きなハードルになることがあるんです。
なめらかさは、赤ちゃんにとって「安全に食べられる」という安心感につながります。
「食べるって楽しいな」と思ってもらうためにも、最初の数週間だけでも裏ごしを丁寧にしてあげることは、すごく意味のあることなんですよ。
ブレンダーだけじゃ足りない?裏ごしの“ひと手間”の大切さ
最近では、ブレンダーやフードプロセッサーなど便利な調理家電も増えてきて、「すりつぶし=なめらか」って思いやすいんですが、じつはこれだけでは十分じゃないこともあります。
ブレンダーで一見なめらかに見えても、実際には舌に残る繊維や種が混じっていたり、微細な固まりがあって飲み込みづらかったりすることがあるんですね。
我が家の長男も、にんじんをブレンダーでペーストにしたのに全然飲んでくれなくて、「なんで?」とよく見たら、繊維がモソモソと残っていたことがありました。
その後、茶こしで裏ごししてみたらスムーズに食べてくれて、「たったこれだけの差で、こんなに違うんだ…」と驚いたものです。
毎回きっちり裏ごしする必要はないですが、赤ちゃんの食べにくそうな様子があれば、ほんの少し手間を加えてあげるだけで「食べられるようになる」ことって、けっこう多いんですよ。
「どっちを選ぶ?」じゃなくて「どっちも使う」が正解
「裏ごし」と「すりつぶし」、どっちが正しいの?と悩むこともあるかもしれません。
でも実は、どちらも使い分けながら進めていくことが一番の近道なんです。
最初の頃は裏ごしで、飲み込みやすさ重視。
その後少しずつすりつぶしに切り替えて、舌や口の筋肉を育てていく。
こうして段階的に進めることで、赤ちゃんの食べる力も自然とついていきます。
そして、なにより大切なのは「赤ちゃんの様子を見ながら無理なく進めること」。
今日ちょっと食べにくそうにしていたら、明日はもう少しなめらかに。
逆に元気にモグモグしていたら、ほんの少し形を残してみてもいいかもしれません。
親が「こうしなきゃ」と思い詰める必要はなくて、毎日のごはんの中で「今日はどんなふうに食べられるかな?」と赤ちゃんと一緒に試していくことこそが、一番の正解だと思いますよ。
裏ごしはいつまで、どんなときに必要?
「いつまで裏ごしすればいいの?」という不安
離乳食を始めると、だんだん気になってくるのが「裏ごしって、いつまでやればいいの?」という疑問ですよね。
最初のうちはしっかり裏ごししていたけど、赤ちゃんが慣れてくると「もうそろそろ卒業してもいいのかな?」と迷ってしまう方も多いと思います。
実際には、裏ごしを続ける期間に明確なゴールがあるわけではなく、目安としては離乳食開始から1~2ヶ月程度が多いと言われています。
ただし、これはあくまで目安。
赤ちゃん一人ひとりの成長ペースや食べる力によって、必要な期間は変わってくるんですよ。
赤ちゃんのサインを見逃さないで
私が意識していたのは、「なめらかすぎるものを嫌がるようになったかどうか」でした。
たとえば、裏ごししたにんじんペーストを何度もべーっと出すようになったり、口に入れてもあまり喜ばなくなったりしたとき、「もしかして、そろそろ変えてみてもいい?」と気づけたんです。
赤ちゃんがモグモグするしぐさをし始めたら、それは「そろそろ形のあるものにチャレンジしたいよ」というサインかもしれません。
スプーンを見たときに前よりも積極的に口を開けるようになったり、ごっくんが上手になってきたら、すりつぶしや刻み食へのステップアップを考えてみても良い時期ですよね。
「早すぎたかも」と思ったら、また戻ればいい
実は、我が家でも裏ごしをやめてすりつぶしにしたとき、「あれ?あんまり食べないな」と感じたことがありました。
そんなときは、無理に次の段階に進まずに、もう一度裏ごしに戻してあげるのが正解なんです。
赤ちゃんの食の成長は、一直線ではありません。
調子のいい日もあれば、なんだか食が進まない日もありますし、それは大人だって同じですよね。
「せっかく次のステップに進んだのに」と気負わずに、少し戻ることも全然アリなんです。
それくらい柔軟でいいんですよ。
「裏ごし=卒業」じゃなくて「選べる手段」のひとつ
裏ごしを卒業することが目的ではなく、赤ちゃんが心地よく食べられる形に合わせていくことがいちばん大事です。
野菜によっては、離乳中期以降でも裏ごしが向いているものもありますし、体調によって「今日はちょっと調子悪そう…」というときは、あえて裏ごしに戻すことで食べやすくなることもあります。
離乳食づくりは「段階通りに進めなきゃいけない」ものではなく、「赤ちゃんが心地よく食べてくれるかどうか」で決めていいんです。
その判断ができるようになってくると、親としての自信も少しずつついてきますし、赤ちゃんとの食事がもっと穏やかで、楽しい時間になっていきますよ。
すりつぶしだけでOKなとき・裏ごしが特に有効な食材
「すりつぶしだけ」でいける食材もある
裏ごしって正直ちょっと面倒だなって感じること、ありますよね。
特に育児の合間でバタバタしているときは、「少しでも工程を減らせたら…」という気持ちになるのも当然だと思います。
そんなときに覚えておくと気がラクになるのが、「すりつぶすだけで大丈夫な食材」も意外と多いということなんです。
たとえば、しっかり柔らかく加熱した
「じゃがいも」
「さつまいも」
「かぼちゃ」
は、スプーンやフォークで簡単につぶせて、舌ざわりもなめらかになりやすいので、裏ごしせずにそのまま与えることができます。
また、バナナやアボカドなどの果物類も、完熟していればすりつぶすだけで十分滑らかになるので、急いでいるときや気持ちに余裕がない日でも取り入れやすい食材ですよね。
私も子どもが小さかった頃、アボカドをスプーンでそのままつぶして出したらパクパク食べてくれて、「これ、神食材じゃない?」って感動したことがありました。
裏ごしが活きる食材の見極めポイント
一方で、すりつぶすだけでは飲み込みにくかったり、繊維が気になる食材もあるんですよね。
とくに葉物野菜は代表的で、たとえば
「ほうれんそう」
「小松菜」
「キャベツ」
「白菜」
などは繊維が細かく残りやすいので、すりつぶしだけでは口当たりが悪くなることがあります。
さらに、トマトやいちご、なすなどの種がある食材も注意が必要です。
小さな種って大人の私たちからすればまったく気にならないのに、赤ちゃんにとっては喉に引っかかったり飲み込みづらくなったりする原因になることがあるんです。
我が家でも、すりつぶしただけのトマトをあげたとき、赤ちゃんがうまく飲み込めずに少しむせてしまったことがあり、それからはしばらくトマトだけは裏ごしを徹底してました。
「ちゃんとごっくんできた」という体験を積み重ねることも、赤ちゃんにとっての食事への安心感につながるんですよね。
「すりつぶし」か「裏ごし」か迷ったときの考え方
全部に裏ごしが必要かというと、そんなことはありません。
「赤ちゃんの成長段階+食材の特徴」を見ながら、すりつぶしでいけるときはそのままでOK、飲み込みにくそうだったら裏ごししてあげる。
そんなふうに“必要に応じて使い分ける”ことで、無理なく続けられますし、赤ちゃんもごはんが楽しい時間になります。
すりつぶしで食べられるならそれがベストだし、裏ごしが必要なら遠慮なく手間をかけてあげればいい。
そのときどきで「この子にはこれが合いそうだな」と思うほうを選んでいく柔軟さが、いちばんの正解なんだと思います。
裏ごし器がない!そんなときの代用方法
「今すぐ裏ごししたいのに、器具がない…」そんなときどうする?
離乳食づくりをしていると、「あ、裏ごし器がない!」って気づく瞬間があるんですよね。
私もまさにそうでした。
離乳食を始めたばかりの頃、「まあ最初はなんとかなるかな」と思っていたら、思っていた以上に裏ごしって必要で。
しかも今すぐ必要なときに限って、専用の道具が手元にないという…。
でも大丈夫です。
裏ごし器がなくても、家にあるもので代用できますし、ちゃんと赤ちゃんが食べやすい状態に仕上げてあげられますよ。
大事なのは「裏ごしすること」よりも、「赤ちゃんがごっくんしやすい形にしてあげること」ですからね。
代用におすすめなのは「茶こし」や「ザル」
私がよく使っていたのは、「茶こし」です。
お茶をこすための細かい網目が、離乳食の裏ごしにもぴったりなんですよ。
とくに、量が少ない初期段階の離乳食にはちょうどいいサイズ感で、小さなスプーンで押しながらこせばしっかり滑らかなペーストができます。
ただし注意点もあって、茶こしの目はかなり細かいので、繊維の強い野菜や粘りのある食材だと詰まりやすくなります。
そんなときは、ほんの少しずつ入れてスプーンの背で押しつけるようにしてみるとやりやすいです。
それから、使い終わった後はすぐに水に浸けておくと、詰まった繊維が落ちやすくなってお手入れもラクになりますよ。
キッチンにある「意外な道具」も使えるかも
茶こし以外にも、意外と使えるのが「ストッキングタイプの水切りネット」や「目の細かいザル」「ガーゼ」などです。
たとえば、ガーゼにペースト状の野菜を包んで指で押しながら裏ごしすれば、かなりなめらかな状態にできますし、洗って繰り返し使えるのも嬉しいポイントでした。
離乳食用の道具って、専用で揃えると便利ではあるけれど、全部を一度に買わなくても、手持ちのものや100円ショップのアイテムで十分代用できます。
私も「ベビー用品店であれこれ揃えなきゃ」と思い込んでいた時期があったけれど、実際は身の回りのもので十分間に合ったことが多かったです。
道具よりも「やってみる勇気」と「気楽さ」
「ちゃんとした道具がないから裏ごしできない」と思っていた頃の私は、正直、完璧を求めすぎてちょっと疲れてしまっていました。
でも、実際に茶こしやガーゼを使って工夫してみるうちに、「これでいいんだ」と肩の力が抜けて、離乳食づくりがぐっと気楽になったのを覚えています。
大切なのは、赤ちゃんに無理なく食べてもらえるように整えること。
それを叶えられるなら、どんな道具でも十分立派な“裏ごし器”になれるんですよね。
「今あるもので、できることをやってみよう」そんな柔らかい気持ちで取り組めたら、それだけで十分すぎるくらい立派です。
裏ごし&すりつぶしを進めるときの「安心のためのポイント」
「これで合ってるのかな?」と感じたら
離乳食を作っているとき、誰もが一度は「これ、ちゃんと飲み込めるのかな?」「なめらかさってどのくらい?」と不安になるものです。
私も最初の子のときは、何度も匙加減が分からず迷っていました。
でも、そんなときにいちばん大切なのは、“赤ちゃんの反応をよく見ること”なんですよね。
スプーンを口に入れた瞬間の顔、舌の動き、飲み込んだ後の表情。
これがすべてのヒントになります。
もし嫌そうに顔をしかめたり、何度も舌で押し出してしまうようなら、少しだけ滑らかさを足してみましょう。
逆に嬉しそうにモグモグしていたら、少しずつ形を残していくステップに進んでみるのもいいタイミングです。
赤ちゃんの「舌と喉の成長」に合わせてあげよう
離乳食を通して発達していくのは、単に食べる力だけではありません。
舌の動き、喉の筋肉、そして噛むための準備が少しずつ育っていく過程でもあります。
裏ごしやすりつぶしの段階は、その“準備体操”みたいなもの。
だから焦らなくて大丈夫です。
なめらかにして飲み込みやすくすることは、赤ちゃんが「食べるって楽しい」と感じる第一歩でもあります。
あの小さな口で一生懸命ごっくんしている姿を見ていると、こちらまで胸がいっぱいになりますよね。
もしむせてしまったり、飲み込みにくそうな様子が見られたら、すぐに少し前の段階に戻してあげましょう。
それは後退ではなく、ちゃんと「この子のペースを大切にしている」証拠なんです。
「正解」はマニュアルではなく、わが子の中にある
離乳食に正解はありません。
マニュアルやSNSで見る他の赤ちゃんの様子はあくまで参考であって、「うちの子」にぴったり合う答えは、実際に食べさせてみないと分からないんです。
だから、うまくいかない日があっても、それを“失敗”とは思わないでくださいね。
食べる量が少なかったり、今日は裏ごしに戻したりしても、それは赤ちゃんが安心して進むための自然な流れ。
少しずつ、確実に成長していく姿を見守る時間を楽しんでほしいなと思います。
不安なときは、専門家や先輩ママの声を頼っていい
ひとりで悩みすぎないことも大切です。
保健師さんや栄養士さんに「この状態で大丈夫ですか?」と聞いてみると、思っていた以上に温かくアドバイスしてくれます。
それに「うちの子もそうだったよ」と話してくれるママ友の存在も大きな支えになります。
食事は、赤ちゃんの成長だけでなく、親の心も育ててくれる時間です。
だからこそ、頑張りすぎず、相談しながら、笑顔で過ごせるほうがずっと素敵ですよ。
まとめ
離乳食における「裏ごし」と「すりつぶし」の違いを知ることで、赤ちゃんにとってより安全で食べやすい形を選んであげられるようになりますよね。
ただ単に“柔らかくする”という調理の工夫だけでなく、その裏には「飲み込みやすさ」や「口内の発達に合わせる」という大切な意味があることが見えてきます。
すりつぶすだけで充分な食材もあれば、裏ごししたほうがよいものもあって。
それを“正解・不正解”ではなく“赤ちゃんに合うかどうか”で判断していけることが、親としての自信にもつながっていくのだと思います。
私自身、何度も食べてくれなかったりむせてしまったりして、落ち込むこともありました。
でも、それらすべてがわが子を知るきっかけになり、結果として“その子にぴったりの離乳食”が見えてくるようになったんです。
裏ごし器がなくても、キッチンにある道具で代用できることを知ると、気持ちもグッと軽くなりますし、育児の負担が少しだけやさしくなりますよね。
何よりも、赤ちゃんの笑顔や「おいしいね」と伝わってくる反応が、親にとって一番のごほうびになるはずです。
日々の離乳食づくりに正解はありません。
その日その時の赤ちゃんの様子を見ながら、「今日はどう食べられそうかな」と対話するような気持ちで、無理せずに。
でも丁寧に向き合っていけたら、それが何より素敵な育児の時間になりますよ。