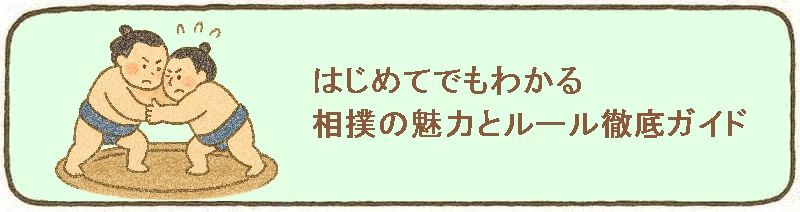皆さんは、相撲はお好きですか?
相撲といえば、日本の国技で、伝統や格式を重んじる日本独自のスポーツです。
本来は神事のような役割をもつ競技でしたので、そのルールや決まり、言葉などにも独特なものがありますよね。
相撲をテレビ中継で何気なく見ていてふと気になったのが、力士が回しにつけているヒラヒラした紐状のものです。
直接取り組みには関係なさそうなものですが、あれはいったいどんな意味で付けられているのでしょうか??
力士が付けているヒラヒラした紐状のものは何?種類はどれくらいあるの?
相撲の力士のまわしについたヒラヒラしたひも状のものは、一般的には「下がり(さがり)」と呼ばれています。
江戸時代のころの力士は、化粧まわしをつけて相撲をおこなっていたそうです。
現在では土俵入りの際につけている化粧まわしですが、あれを付けたままの状態で相撲を取るのは、正直やりづらそうですよね(;^_^A
実際にやはり相撲をとるさいに妨げになるとして、現在のまわしに落ち着いたという説が有力です。
つまり、現在の“下がり”は、化粧まわしの名残ということですね。
さがりは何のためについている?どんな役割があるものなの?
江戸時代の化粧まわしや、現在の“下がり”。
これをつける理由は、やはり「局部を隠すためのもの」といわれています。
取り組み中にまわしがずれてしまった際の防具としての役割ということです。
現在の“下がり”はひも状のものがヒラヒラしている簡易的なものなので、少しこころもとないような気もしちゃいますよね(;’∀’)
この“下がり”には特に種類があるわけではありませんが、材質にはいくつかの種類があるようです。
決まりとして、この下がりの本数は必ず奇数になるように決められています。
奇数であれば数に制限はなく、体の大きな力士ほど、この下がりの本数も多くなるというわけです。
スリムな力士であれば大体13本くらいが一般的で、アンコ型の大型力士の場合は15~17本、巨漢で知られる小錦の場合は21本だったそうです。
いかにお腹周りが大きかったか良くわかりますよね( ゚Д゚)
相撲のさがり事情!幕下と関取では何がどう違うものなの?
力士たちがつけている下がりは、幕下以下と関取では少し違いがあります。
十両以上の関取の場合は、締め込みの共布で下がりをつくり、布糊で固めて作ります。
のりで塗り固めるので、材質としては少し硬めなものとなります。
一方、幕下以下の力士のさがりは、綿の紐をつかって作り、布糊で固めずに作られます。
布糊で固めて作るよりも柔らかな下がりとなります。
色についても違いがあって
- 十両以上の関取の場合は締め込みと同色
- 幕下以下の力士たちの下がりの色は原則自由
下がり一つにしても、番付によって材質が違うとはビックリしました。
相撲のさがりはおさがりって本当?自分でさがりは決めれないの?
相撲における“下がり”、一見すると“お下がり”の意味のような気もしますが、
そんなことはないようです。
決しておさがりをもらうから“下がり”という名前がついているわけではありません。
相撲取りのさがりはずっとつけていなくちゃいけないの?
現在の“下がり”は、取り組み中の激しい動きで外れることがよくあります。
この“下がり”が取組前に取れたら反則負けになるという噂もありますが、そんなことは一切ないようです。
下がりは、挟み込む面を前褌に挟み込んでいるだけなので、相手力士にちょっと引っ張られただけですぐにとれてしまいます。
これは、無理やり外れない状態にしておくと、手や足が万が一絡まってしまうと大変なので、意図的に外れやすくしているというわけです。
確かに、全力でぶつかり合っている際に、下がりが手や足にからまってしまうと、そのせいで足を取られて転んでしまうかもしれません(><)
そんな事になったら、せっかくの取り組みが台無しですよね(><)
そうならない為にも、下がりは外れやすくなっているんです。
さらには、
- 取り組み中に取れてしまった下がり
- 取れそうになっている下がり
取り組みの最中にサッと素早い動きで下がりを拾い上げる行司を見たことがある方も多いのではないでしょうか(^^)
相撲のさがりを取り直しのときには外すのはなぜ?
化粧まわしのなごりであるさがりですが、取り直しのときに外している力士もいますよね。
実は、取り直しのときには外さなければいけないというルールがあるわけではありません。
外しても外さなくてもどちらでも構わないのです。
最初の取り組みでさがりが取れなかったときは、取り直しのときもさがりはそのままの状態で取り組むこともできるのです。
ただ実際には、取り直しではさがりを外す力士が多いですよね。
やはり、さがりがあると取り組みの邪魔になったり、指などに引っかかって危険だったりするので、外してしまうのかもしれません。
さがりは飾りの意味合いが強いため、あってもなくてもよいのなら外しちゃおうということなのでしょう。
確かに足の前に紐がたくさん垂れていたら、気になって動き辛いですよね。
特に激しい取り組みをする相撲なら、さがりは外しちゃった方が便利だったりするのでしょう。
最初の取り組みでさがりが取れなかったとしても、「この後の取り直しのために付けたままにしておこう」と考える力士はめったにいません。
勝敗が決まって取り直しをしないかもしれない状態だと、「さがりは必要ないから外そう」と思うのは当然のことです。
なので、結果的に取り直しのときはほとんどの力士がさがりを外している状態になるわけです。
相撲で珍しい「さがり待った」!?どんなことが起こったの?
あまりなじみのない「さがり待った」という言葉。
「待った」はやむを得ない事情により相撲の取り組みを中止することを指します。
では、「さがり待った」とはどういうことなのかというと、「さがりが髷に引っかかってしまい取り組みが中止になる」という状態です。
腰の周りにつけているさがりが、頭の上の髷に引っかかる!
そんなことってめったにありませんよね!
だから、「さがり待った」は極めて珍しい待ったになるのです。
かなりレアなさがり待ったですが、なんと2023年の大相撲夏場所でさがり待ったで中止になった一番がありました。
栃丸と東俊隆の取り組みで、激しくぶつかり合った拍子に栃丸のさがりがはね上がって、自分の髷に引っかかってしまったのです。
写真で見ると、栃丸の髷からさがりが数本ぷらんと垂れさがっている状態でした。
そこで行司が「さがり待った」で一旦取り組みを中断し、髷からさがりを外しました。
さがりを取り除いた後は、仕切り直して取り組みを再開しました。
めったにないさがり待ったなので、当の本人の栃丸は「面白くて笑いをこらえるのに必死だった」そうです。
確かにさがりが髷に引っかかったら、真剣勝負の土俵の上でも、思わず「ふふふ」と噴き出してしまいそうですね。
珍しいさがり待ったですが、実際に起きたことにびっくりです。
相撲のさがりの意味は?のまとめ
相撲のさがりの意味について見てきました。
“下がり”ひとつにしても、番付によってルールが決められているとは、さすが伝統と格式のある相撲の世界だなぁと感心してしまいました。
ちなみに、この下がりはそもそも大切な所を隠すためのものとのことでしたが、中にはこの下がりが活躍せずにもろ見えになってしまった取り組みもあるそうです。笑
次に相撲中継を見る際には、この下がりと、それを回収する行司の動きにも注目して、相撲観戦をしてみてはいかがでしょうか?(^^)