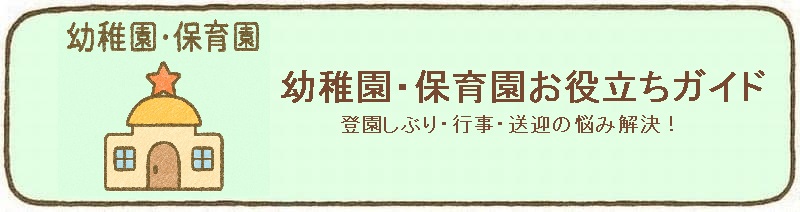夏休みが明けた朝、幼稚園に行く準備をしている最中に「行きたくない…」と泣き出す子どもの姿を見て、思わず一緒に泣きたくなってしまった…そんな経験はありませんか?
楽しかった夏休みが終わり、また集団生活に戻るのは、大人以上に子どもにとって大きなハードルです。
子どもにとって、長い休みの間に築いた“家族といる安心感”から一歩離れるのは勇気が必要なこと。
それでも大丈夫。
子どもは必ずまた笑顔で登園できるようになります。
親の優しいサポートがあれば、ほんの少しずつですが確実に前に進めるのです。
そのために親ができることや、ちょっとした声かけの工夫を、私の幼稚園担任時代のエピソードも交えながら、より丁寧にお伝えします。
あなたの心が軽くなり、子どもの不安を和らげるヒントになりますように。
夏休み明けに幼稚園に行きたがらないのはよくあること
なぜ夏休み明けに登園しぶりが起こるの?
年少さんにとっての初めての夏休みは、これまでの人生で最も長くて濃密なお休みかもしれません。
毎日ママやパパと一緒に過ごし、大好きな家で安心感いっぱいの日々を送ると、やっと慣れてきた園生活が遠く感じられるのも無理はありません。
その間に家族と過ごした「特別な時間」が強く記憶に残り、園よりも家がいい…という気持ちが芽生えるのです。
さらに、生活リズムが崩れた子や、園でのちょっとしたトラブルの記憶がよみがえって不安になる子もいます。
「またあの子に意地悪されたらどうしよう…」「みんなについていけるかな…」と、子どもなりに色々なことを考えているのです。
こうした気持ちは決して珍しいものではなく、子どもの心が成長している証でもあります。
親が知っておくと安心する「よくある姿」
泣きながら登園した子が、園についた途端にケロッと笑顔で遊び始める姿を、私は何度も見てきました。
送り出すときに涙が出てしまうのは、お母さんに甘えたいから。
でも実際は、園に着いて先生や友達の顔を見ると安心して楽しめる子も多いのです。
成長の一過程だと考えて、必要以上に心配しすぎず、子どもを信じて見守ることが大切です。
時には涙で出発した朝も、その日の帰りには「楽しかった!」と話してくれることだってありますよ。
親が「大丈夫、あなたならできるよ」という気持ちで送り出してあげることが、子どもにとって何よりの安心材料になります。
無理に行かせるのは逆効果?親のNG対応とOK対応
こんな声かけは逆効果
つい「早くしなさい」「なんで泣いてるの?」「他の子は頑張ってるよ!」と言ってしまいたくなる気持ち、私も親として本当によく分かります。
時間に追われていると、つい強い言葉で促したくなりますよね。
でもこれらの言葉は、子どもの不安や寂しさを無視してしまい、かえって不安を強めてしまうのです。
子どもは「自分の気持ちを分かってもらえなかった」という寂しさからさらに泣いてしまい、登園どころではなくなることもあります。
「行きたくない」というのは甘えやワガママではなく、小さな心が頑張った末に出しているSOSなんだと捉えてあげてください。
寄り添う姿勢が何よりも大切です。
子どもに寄り添う声かけのコツ
まずは「嫌だよね、寂しいよね」と共感してあげましょう。
それだけで子どもは心が軽くなります。
大切なのはすぐに解決しようとするのではなく、子どもが「わかってくれている」と感じられることです。
私は担任時代、保護者に「今日は泣かずに玄関まで行けたね!」「自分で靴を履けたね!」と、小さな成長を一緒に見つけて喜ぶようお願いしていました。
小さなできたことの積み重ねが、子どもの大きな自信につながっていきます。
「次も頑張ってみようかな」という気持ちを引き出してくれます。
こうして、ほんの少しずつですが子どもの心に安心感と達成感が芽生えていくのです。
明日からできる!夏休み明けの登園しぶり対策
生活リズムを整える
夏休みの夜更かしや遅起きが習慣になっている子は、少しずつ元のリズムに戻しましょう。
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 決まった時間に寝る・起きる
- 昼寝を調整する
できれば朝ご飯も一緒にしっかり食べて、「今日も一日がんばろうね」と声をかけてあげると気持ちが前向きになります。
休日でも起床・就寝時間をなるべく一定にして、身体がリズムを思い出しやすいようにしてあげるとさらに効果的です。
夜はスマホやテレビを早めに消して、親子でリラックスできる時間を作るのもおすすめです。
楽しい園生活を思い出させる
「先生に見せる絵を描いてみようか」「お砂場で新しいお山作ろうね」など、園での楽しい経験を具体的に話して期待を持たせてみましょう。
担任の頃、子どもに「今日は給食に◯◯が出るよ!」「お友達が待ってるよ!」と伝えるだけでぱっと笑顔になる場面を何度も見ました。
前日に園の話を親子でしながら、楽しみなことを一緒にリストアップしたり、園での思い出の写真を見返して「このとき楽しかったね」と振り返るのも効果的です。
園からもらったプリントやおたより帳を一緒に読み返して、子どもが自分のペースで思い出を整理できる時間を作ってあげましょう。
朝の支度を親子で楽しむ工夫
- お気に入りの洋服やハンカチを一緒に選ぶ
- カレンダーにシールを貼る
- 出発前に一緒に深呼吸する
小さな習慣が子どもに安心感を与え、「今日はこれがあるからがんばれる!」という気持ちを後押ししてくれます。
さらに、支度が終わったら少しだけ親子で遊んだり、簡単なストレッチやダンスをしたりするのもおすすめです。
笑顔の時間が増えると、子どもは安心して登園の一歩を踏み出せます。
時間に余裕を持って、なるべく笑顔で「今日も楽しい一日にしようね」と送り出してあげてください。
それでも長引くときは…専門家に相談するのも一つの手
登園拒否が長期化する場合のチェックポイント
1か月以上続く場合や、家でも常に不安定な様子が続く場合は、無理をせずに専門家や園に相談してみてください。
心理士や保健師に相談することで、家庭では見えなかった子どもの気持ちや背景が見えてくることもあります。
親が一人で抱え込まず、サポートを受けることも大切ですし、子どもにとっても安心材料になります。
園や先生と連携してみる
先生に子どもの不安や状況を詳しく伝えることで、園でも特別な配慮をしてもらえますし、親の気持ちもぐっと楽になります。
担任だけでなく、園長や副担任とも相談することで新たな視点が得られることもあります。
「今日は泣いても大丈夫ですから、こちらでしっかり見守りますね」という一言に救われる親御さんも多いです。
先生たちは子どものペースに寄り添うプロです。
どんな些細なことでも共有して、二人三脚で乗り越えていきましょう。
まとめ
夏休み明けの「行きたくない」は、子どもが成長している証拠でもあります。
親の寄り添いと、小さな一歩の積み重ねが、必ずまた笑顔で登園できる日につながります。
今は不安や戸惑いでいっぱいかもしれませんし、時には親のほうがくじけそうになることもありますが、それでも大丈夫。
子どもは親が思う以上にたくましく、毎日少しずつ成長し、優しい笑顔で新しい毎日を迎えられるようになります。
泣いても、ぐずっても、それは前に進もうとしている証しです。
どうかあなたの温かい声と見守る気持ちで、今日も、そして明日も背中をそっと押してあげてくださいね。
その一歩一歩が、かけがえのない親子の思い出にもなっていきます。