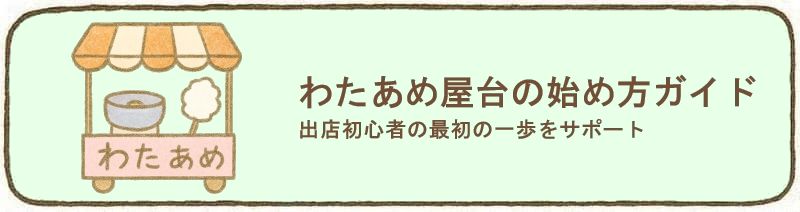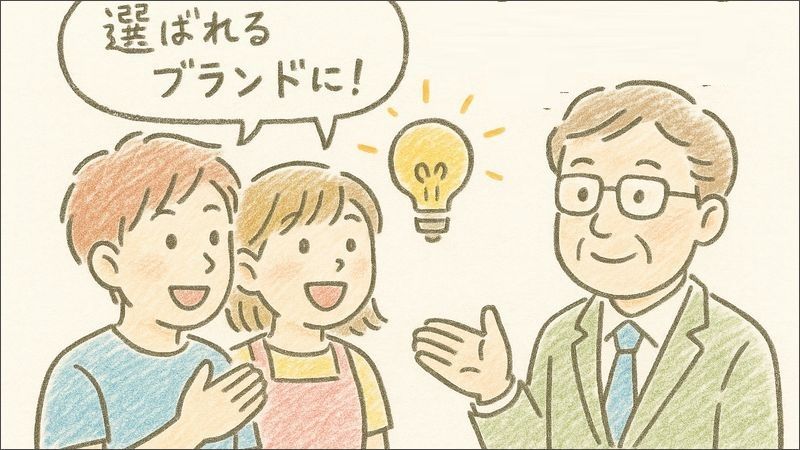
祭りの喧騒の中で、ふわりと立ちのぼる甘い香り。
カラフルなわたあめを手にした子どもたちの笑顔を見て、「いつか自分もこんな屋台を出してみたい」と思ったことがある人は多いのではないでしょうか。
でも実際に出店するとなると、かわいいだけでは通用しません。
イベントの主催者は、あなたの屋台を「お客さんが安心して楽しめる空間として運営できるか」という視点で見ています。
どれだけ味や見た目が素敵でも、衛生管理が曖昧だったり、設営や対応に不安があると、次に呼ばれるチャンスを逃してしまうのです。
私自身も初出店のとき、楽しさばかりに気を取られて、細かな準備を怠った経験がありました。
その日、思わぬトラブルに慌てる自分を見て、「このままじゃもう呼ばれないかも」と冷や汗をかいたのを今でも覚えています。
けれど、その経験こそが「信頼される出店者とは何か」を学ぶきっかけになりました。
イベントの世界では、見た目のかわいさよりも“信頼感”こそが最大のブランド力です。
このページでは、そんな私の経験も交えながら、主催者に安心して選ばれるわたあめ屋のブランディングの作り方を、やさしく丁寧にお伝えしていきますね。
なぜ“ブランディング”が出店成功を左右するのか
「見た目」だけでは選ばれない時代
かわいくて目を引く屋台を作ること。
それは出店において大切な第一歩です。
でも今のイベントの現場では、「見た目が良ければ売れる」という時代は終わりつつあります。
主催者が出店者を選ぶときに見ているのは、ただの“見た目”ではなく“信頼できるかどうか”です。
実際、私はあるイベントで見かけた屋台のデザインに惹かれて足を止めたのですが。
でもよく見ると、テントがぐらついていたりスタッフの方が素手で食品に触れていたりして、不安を感じたことがありました。
どれだけかわいく飾っていても、こうした“安心感を損なう部分”があると、親子連れのお客さんはそっと離れていってしまうんです。
そしてそれは、主催者の信頼も同じように削られてしまいます。
主催者が見る“安全・信頼・雰囲気”の3要素
主催者にとって出店者は「一緒にイベントをつくる仲間」です。
だからこそ、その屋台が安心して任せられる存在かどうかをよく見ています。
イベントによっては事前に企画書の提出を求められることもあり、そこでは見た目の写真よりも、
「衛生管理」
「安全対策」
「運営体制」
がきちんと明記されているかどうかが問われます。
特に最近は、出店において“食品を扱う責任”が問われることが増えています。
例えば
「火気使用のルール」
「食品保管の方法」
「ゴミ処理のルール」
「子どもが列を乱さずに並べるような導線の設計」…
そういった一つひとつの配慮が積み重なって、「この人なら安心して任せられる」という評価につながっていくんですね。
私が以前、主催者の立場で出店者をまとめる機会があったのですが、そのときに感じたのは「トラブルを起こしそうにない人」を選びたくなるということでした。
派手な演出よりも、片付けが丁寧だったり、お客さんへの声かけが柔らかかったり。
そういう“安心できる雰囲気”がある屋台のほうが、主催者としては心からありがたく感じるんです。
「選ばれる」ためには“終わり方”が大切
実は、一番主催者に印象を残すのは“イベントの最後”だったりします。
屋台の撤収時にバタバタしてゴミがそのままだったり、主催者に挨拶もなく帰ってしまうと、「あの人には次は声かけづらいな」と思われてしまいます。
私が初めて出店したイベントのときも、終了時間ちょうどにすぐ片付けに入ろうとして、主催者さんから「ちょっと待ってください、お客さんがまだ少し並んでます」と言われたことがありました。
そのときに「終わりの配慮も“ブランド”なんだな」と痛感したんです。
主催者にとって“イベント全体がスムーズに終わること”も重要な評価軸のひとつです。
「撤収時の気配り」
「出店後のお礼のメール」
「SNSでの報告と感謝の投稿」
など、イベントが終わったあとに丁寧さが伝わると、「またこの人にお願いしたい」と自然に思ってもらえるようになります。
“ブランディング”とは安心の空気を届けること
ブランディングというと、見た目を整えたりロゴを作ったりすることをイメージしがちですが、本質はそこではありません。
出店者としてどういう思いで商品を届けたいのか、どんな空気感を大切にしたいのか、その“在り方”がすべてににじみ出てくるのです。
たとえば、親子で来場してくれたお客さんに向かって「よかったら一緒に記念撮影しますか?」と声をかける一言もブランディングのひとつ。
ささやかな心配りを積み重ねていくことが、主催者や来場者の記憶に残る“信頼のブランド”へと育っていくのだと思います。
イベント主催者が「また呼びたい」と思う出店者の特徴
衛生・安全対策をきちんと見せているか
イベント出店で「呼ばれ続ける人」と「一度きりの人」の違い。
それは“主催者の安心感をどれだけ引き出せるか”にかかっています。
その中でも、とくに大事にされているのが“衛生”と“安全”の管理です。
私が以前出店した子ども向けイベントでは、
「ゴミ箱が見当たらなかった」
「手袋をしていなかった」
といった声が、あとから主催者経由で届いたことがありました。
自分では気をつけているつもりでも、それが“見える形”になっていなければ、主催者やお客さんに伝わらないんですよね。
たとえば、
「手洗い用のアルコールスプレーを見える場所に置く」
「トングや手袋の使い分けを明確にする」
「使用後のゴミの処理も「ここにまとめています」と示す」
そういった“見せ方の配慮”こそが、「この人なら任せても大丈夫」と思ってもらえる大きな要因になります。
対応や接客が丁寧で安心できるか
どんなに商品がおいしくても、スタッフの態度が冷たかったり、慌ただしい印象を与えてしまうと、その屋台の評価は一気に下がってしまいます。
特にイベントは“非日常”を楽しみに来ている人が多いので、接客の温度が高いか低いかが、その場の空気感を左右することがあるんです。
私が出店していたとき、前に並んでいた子がなかなか注文を決められずにいたんですね。
そこで「ゆっくりでいいよ、どれにするか迷うよね」と声をかけただけで、その子が一気に笑顔になって、「じゃあこれにする!」と選んでくれたんです。
そのとき、後ろで見ていた親御さんがこっそり「ありがとうございます」と言ってくれて、あの瞬間が今でも心に残っています。
こういう小さなやり取りが、実は主催者さんにも伝わっていたりします。
「あの屋台の人、すごく丁寧だったね」と後日言ってもらえたこともあって、対応ひとつで信頼は育つんだと実感しました。
看板や装飾がブランドを感じさせるか
“なんとなく可愛い”はたくさんあるけれど、“この屋台は他とちがうな”と感じてもらえるには、しっかりとした世界観が必要です。
たとえば、価格表が手書きでもバラバラで雑だったり、色や書体がごちゃごちゃしていると、どうしてもチープな印象になってしまいます。
私が実践したのは、まず「テーマカラーを決める」こと。
今回は“ミントグリーンと白”を基調に、POPや看板もその色で統一しました。
使うフォントも「丸みのある読みやすいもの」にそろえ、料金も写真付きで子どもでもわかるようにしました。
こうした視覚の一貫性は、主催者さんにとって「この人は細部まで気を配っているな」という安心材料になるんです。
かわいいだけじゃない、整理されていて信頼感がある。
それが、また声をかけてもらえる理由になっていきます。
家族や子どもにも安心してすすめられる雰囲気か
家族連れのイベントでは、親が「安心して子どもを近づけられるかどうか」が非常に重要な判断基準になります。
屋台の高さ、機械の熱さ、列の整理、落とし物への対応など、細かい部分での“子ども目線の配慮”があると、それだけで評価がぐっと上がります。
私が工夫したのは、まず「手が届く台」を用意して、子どもたちがわたあめを作る様子を見やすくしたこと。
そして「近づいてもいいよ」と声をかけることで、“ちょっと特別な体験”をしている雰囲気を演出しました。
親御さんはスマホでパシャリ、子どもは笑顔でぴょんぴょん。
その一瞬が、屋台という空間を“記憶に残る場”に変えてくれます。
主催者さんもその様子を見ていて、「この屋台、雰囲気がいいですね」と声をかけてくれました。
お客さんの安心=主催者の安心。
これは、どんなテクニックよりも強いブランディングになります。
信頼されるブランド作りの3ステップ
STEP1:ブランドのテーマを決める
まず一番最初に大切なのは、自分の屋台が「どんな世界観を持っているか」をはっきり言葉にすることです。
これは単なる“雰囲気”や“かわいさ”じゃなくて、「誰に、どんな気持ちを届けたいか」を明確にするということなんです。
たとえば私は「写真を撮りたくなる、やさしい雰囲気のわたあめ屋さん」というテーマで最初の出店を決めました。
テーマカラーはくすみピンクとミント。
看板やPOPの文字も、丸みのあるフォントに統一しました。
すると、想像以上に親子連れが立ち止まり、写真を撮ってくれたんです。
こうしてブランドの“芯”ができると、他の屋台と並んでもブレない存在感が出てきます。
お客さんも「この屋台、なんかいいよね」と感覚で選んでくれるようになるんですよね。
そして、それは主催者にとっても「この出店者さん、ちゃんと考えてるな」という信頼につながります。
STEP2:見た目と行動を統一する
テーマを決めたら、次はそれを“全体に行き渡らせる”こと。
これは、見た目のデザインだけじゃなくて、接客の言葉遣いや動き方、商品の提供方法などもすべて含まれます。
私が意識していたのは「やさしく、ていねいな印象を伝える」ということでした。
たとえばお釣りを返すときは「どうぞ、ありがとうございました」だけでなく「今日のイベント楽しんでくださいね」と声を添えるようにしていたんです。
装飾だけでなく、言葉や所作の“空気”までテーマにそろえていくと、「この人の屋台は、なんか居心地がいい」と感じてもらえます。
そして、料金表示や材料表示も、統一感あるフォントや色で整えていくと、“細かいところまで手が届く人”という印象に。
主催者側は、そういった「ちゃんとしてる空気」を無意識に見ています。
ブランディングとは、おしゃれに飾ることじゃなくて、“想いを隅々まで届かせること”なんですよね。
STEP3:主催者やお客さんとの関係性を育てる
ブランドというのは「一度作って終わり」ではなく、「関係性の中で育っていくもの」です。
屋台が終わってテントをたたんだそのあとも、あなたのブランドは“人の中に”残ります。
私がしていたのは、イベントが終わったあとに主催者さんへ写真付きで「今日は本当にありがとうございました。
皆さんのご配慮のおかげで楽しく出店できました」とメッセージを送ること。
そして、SNSにも「今日出会ってくれた皆さんありがとう」と投稿して、来てくれたお客さんの写真や声を紹介していました。
すると次のイベントのときに、主催者さんから「あのSNS見ました!すごく温かくて素敵でした」と言っていただけて。
そのとき、「ああ、ブランディングって“発信”でもあり“感謝”でもあるんだな」って感じました。
関係性を育てることは、ファンを増やすことでもあり、主催者の中で「またお願いしたい人リスト」に入れてもらうことでもあるんです。
人と人とのやりとりの中で、ブランドは少しずつ、強く、あたたかく育っていくものだと思います。
“安心感”がブランドを強くする
食品衛生法・火気管理の基礎をおさらい
「かわいい」や「映える」は、確かに人の目を引きます。
でも、それだけでは選ばれ続ける屋台にはなれない。
イベント出店というのは“食品を提供する”という責任も背負っているからこそ、安全や衛生への取り組みが、ブランドの信頼感をつくる柱になるんです。
私が出店した地域イベントでは、事前に保健所へ確認し、必要な申請や届出をきちんと出したうえで、食材の保管温度や調理スペースの清潔さにも細心の注意を払いました。
ザラメの保管にジッパー付きの密閉袋を使い、製造機は営業中でも定期的に表面を拭くようにしました。
こうした取り組みは、ぱっと見ではわかりづらいかもしれません。
でも主催者さんや来場者の中には、そういう“見えにくい部分”こそ気にしている人が必ずいます。
「この人、ちゃんとしてるな」と思ってもらえたら、それだけで他の屋台との差はグッと開きます。
雨・風などのトラブル対応マニュアルを準備しておく
野外イベントでは、天気との戦いがつきものです。
晴れていたと思ったら突然の強風、急な通り雨。
そんなときに、ただオロオロしてしまう屋台と、サッと行動に移れる屋台。
どちらが主催者にとって安心できるかは、もう言うまでもないですよね。
私も一度、風の強い日に出店したことがあるんですが、そのときは前日からテント用の重しとロープを用意していて、「これでもか」ってくらい固定していたんです。
おかげで隣の屋台が慌てて荷物を押さえている中、うちのテントだけはピクリともせず。
主催者さんが「準備が完璧ですね」と声をかけてくれたとき、あの準備が“信用”に変わった瞬間だと感じました。
天候に限らず、延長コードが抜けた、機械が一時停止した、子どもが機材に近づいてきた…。
こういった“もしも”に備えて、事前に対応マニュアルを作っておくだけでも、落ち着いて対処できるし、周囲の信頼も自然と高まっていきます。
安全な運営を“見える化”する
どれだけ丁寧に準備していても、それを相手が知らなければ伝わりません。
だからこそ、“見える化”はとても大事。
あなたが安全のためにしていることを、さりげなくでもちゃんと「伝える」こと。
それが“安心できる出店者”として認識される近道になります。
私は衛生面での取り組みをA4用紙にまとめて、テーブルの前に小さなスタンドで掲示していました。
「手袋・マスク着用中」
「使用器具はアルコールで都度清拭」
「食品は個包装済み」
など、読みやすくイラスト付きで書いただけですが。
それを見たお客さんが「こういうのあると、親としてほんとにありがたい」と言ってくれたんです。
安心感って、ただ“ある”だけじゃ足りなくて、相手に“伝わる”ことが大事なんですよね。
その一枚の掲示が、家族の信頼も主催者の信頼も、静かに支えてくれるんです。
出店ブランドを長く育てるコツ
イベントごとのテーマや雰囲気に合わせて微調整する
「自分のブランドを持つ」ということは、「どんな場所でも同じことをする」という意味ではありません。
むしろ、ブランドの“芯”を保ちながらも、その場その場の空気や客層に合わせて“ほんの少し変化させる”ことが、信頼を重ねていくためにはとても大事なんです。
私が春の桜まつりに出店したときには、わたあめを淡いピンクと白の二層にして「さくら味」に見えるように工夫しました。
逆に夏の夜店では、蛍光カラーのカラフルザラメを使って、夜でも目立つ「光るわたあめ」に挑戦してみたんです。
どちらもベースの“やさしくかわいい世界観”は変えずに、その場の雰囲気に合わせて見せ方を変えたら、お客さんの反応がグンと良くなりました。
「毎回同じ」では、主催者にも「使いまわし感」が伝わってしまうことがあります。
けれど、“このイベントに合わせて考えてくれた”と伝わると、「またお願いしたい」と自然に思ってもらえるんです。
リピート依頼を増やす“お礼と発信”の習慣
出店が終わったら「お疲れさまでした」で終わりにせず、もう一歩踏み込んで「お礼」と「発信」を習慣にしてみてください。
これがブランドを“次へとつなげる力”になります。
私はイベントが終わったあと、主催者さんに
「今日はありがとうございました!安全に運営できました」
と短いメッセージと、お客さんが楽しんでいる様子の写真を送るようにしています。
写真があると、主催者さんがSNSやHPで使ってくれることもあり、「あの屋台、雰囲気いいよね」と印象に残るきっかけになります。
また、Instagramなどで「ご来場ありがとうございました」と当日の様子を投稿することで、お客さんからのコメントやフォローが増えたり、次の出店イベントの情報を求められたりすることも。
感謝と報告の発信は、次のご縁の種まきになります。
「わたあめ屋さん=あなた」という印象を残すSNS発信術
今の時代、SNSの力は本当に大きいです。
ただ宣伝をするだけじゃなくて、「あなたらしさ」がちゃんと伝わる発信ができると、「またこの人のわたあめが食べたい」と思ってもらえるようになります。
私は投稿する写真にこだわっていて、特に「お客さんの表情」を主役にするようにしています。
「カラフルなわたあめを持って嬉しそうに笑っている子どもの写真」
「親子で一緒に屋台を覗き込んでいる後ろ姿」
など、あたたかさのある一枚は、たった一瞬でも「この屋台、いいな」と感じてもらえるんです。
投稿には「どんな想いでこの屋台をやっているのか」「今日はどんなお客さんと出会えたのか」といった、あなただけのストーリーも添えてみてください。
主催者さんは、その“人柄”を見て次の出店依頼を決めていることもあります。
イベントでの実績とSNSでの発信がつながると、「あのわたあめ屋さん、また呼びたいね」と思い出してもらえる力になる。
あなたのブランドは、言葉や写真、ふるまいのひとつひとつの中に、少しずつ積み重なっていくものなんです。
まとめ
出店って、ただ商品を並べて売るだけじゃないんですよね。
特に「また呼ばれたい」「次もこのイベントに出たい」と思うなら、見た目のかわいさや一時的な盛り上がりよりも、安心感や信頼感の積み重ねが何より大切になってきます。
実際に出店を重ねてきて思うのは、主催者さんの目線ってとても現実的なんです。
「トラブルがないか」「お客さんからの評判はどうか」「イベント全体の雰囲気を壊さない人か」。
そのすべてが、次の出店依頼につながる判断材料になっているんだと、何度も実感しました。
だからこそ、屋台の装飾、接客、運営マナー、SNS発信、そして感謝の伝え方まで、ぜんぶが“あなたのブランド”になるんです。
ブランディングって難しそうに聞こえるかもしれないけど、実は「ちゃんとした人だな」って感じてもらう積み重ねのこと。
今日からできることはたくさんあります。
ほんの少しの心がけで、あなたの屋台は「また呼びたい」と思われる存在になりますよ。
信頼されるわたあめ屋さん、一緒に目指していきましょうね。