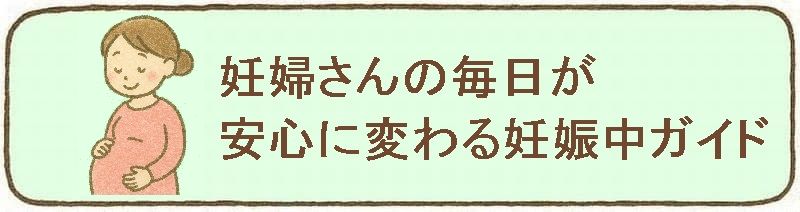年が明けるあの瞬間って、どこか空気が澄んでいて、心が引き締まるような感覚になりますよね。
毎年のように初詣に出かけていた人にとっては、妊娠中であっても「やっぱり行きたいな」と思うのはごく自然なことだと思います。
新しい命を授かった今だからこそ、赤ちゃんの無事やこれからの家族の幸せを祈りたくなる。
そんな気持ち、私も経験があるからこそ痛いほどわかります。
でも、妊娠中の体って、自分が思っている以上にデリケートで、気温の変化やちょっとした無理にすぐ反応してしまうんです。
混雑した神社で転倒したり、寒さでお腹が張ったりすることが、赤ちゃんにとって思わぬリスクになる場合もあります。
私自身、妊婦のときに「行けるかな?」と軽く考えて出かけたら、思った以上の人混みに圧倒されてしまって、結局参拝どころじゃなかったという苦い思い出があるんです。
だから今回は、妊娠中でも安心して初詣に行くために、避けるべき時間帯や冷え対策、そして気になる甘酒についてなど、具体的なアドバイスを込めてお伝えしたいと思います。
大切な赤ちゃんと一緒に過ごすお正月が、あたたかく穏やかなものになりますように。
そんな想いを込めて、お話を進めていきますね。
妊婦さんが初詣に行くとき、避けたいのはどんな時間帯?
妊娠中でも初詣に行きたい。
そう思う気持ちに、誰かが「やめておいた方がいいよ」なんて言ったとしても、その想いはそう簡単に消えるものじゃないですよね。
だけど、赤ちゃんをお腹に抱えている今だからこそ、少しだけ「行きたい気持ち」と「守るべきもの」を天秤にかけてみてほしいんです。
初詣の時期の神社は、想像以上に混み合います。
特に「この時間帯」は妊婦さんにとって危険が増すため、できるだけ避けていただきたい時間帯があります。
夜中から元旦にかけての時間帯は、妊婦さんにとって最も過酷
初詣といえば、年が明ける瞬間に「明けましておめでとう」と言いながら参拝したいという気持ちになる方も多いでしょう。
けれどその時間帯、つまり12月31日の深夜から1月1日の早朝にかけては、どの神社も一年で最も混み合う時間帯です。
大きな神社になると、何万人という人が一斉に押し寄せます。
列に並んでいるときはまだ良くても、本殿前では人の流れが止まらず、いわば「前の人に押されて前進する」ような状態になることもあります。
妊婦さんの身体は、見た目以上に転倒や圧迫に弱く、こうした環境は明確なリスクになります。
私の知人で、妊娠7ヶ月のときに夜中の参拝に付き合った人がいるのですが、途中で息苦しくなって動けなくなってしまい、救護テントに運ばれたということがありました。
幸い赤ちゃんに異常はなかったのですが、そのときの不安と後悔の話を聞いて、私は二度と夜中の初詣には行かないと心に決めました。
夜の冷え込みは、お腹にじわじわ響いてくる
真冬の夜って、本当に冷えますよね。
妊婦さんにとって冷えは大敵。
お腹が張りやすくなったり、血流が悪くなったり、時には寒さが原因で体調を崩すこともあります。
特に妊娠中期以降は、冷えによる子宮の収縮が不安定な状態を引き起こす可能性があり、夜間の外出は慎重になる必要があります。
厚生労働省や助産師の方々も、冬の夜の長時間外出には注意が必要だと呼びかけています。
しかも初詣では、立ちっぱなしや長時間の待機が続きます。
防寒対策を万全にしたとしても、身体の芯まで冷える寒さは、妊婦さんの身体にとって予想以上のストレスになります。
人混みと治安、どちらも「夜」はリスクが高い
もうひとつ、見落としがちなポイントとして「夜の雰囲気の違い」があります。
元旦の昼間は、家族連れや高齢の方など穏やかな人たちが多く、全体的に落ち着いた雰囲気です。
けれど夜中になると、若者グループやテンションの高い人たちが多くなり、お酒が入っている人も増えてきます。
ふざけて走ったり、大声で話したり、たむろしている様子を見かけたとき、「ちょっと怖いな」と感じるのは当然です。
妊婦さんはとっさに避けたり、早歩きでその場を離れたりするのが難しいため、こうした環境そのものがストレスになってしまいます。
それに、こうした場所ではたばこの煙や強い香水など、妊婦さんが苦手とするものが思わぬところから漂ってくることもあるんですよね。
ちょっとした刺激臭で気分が悪くなったり、息苦しくなったりすることもあるので、夜中はできるだけ避けた方が安心です。
初詣で気をつけたいのは「転倒」だけじゃない
実は意外と見落とされがちなのが「感染症リスク」です。
年末年始はインフルエンザや風邪、ノロウイルスなどが流行しやすく、密集した場所に長時間いることで、知らないうちにウイルスをもらってしまうこともあります。
妊婦さんは免疫が低下している状態ですから、たとえ軽い風邪でも長引いたり、高熱を出してしまったりといったリスクが高くなります。
「元旦の人混みで風邪をもらって、その後寝正月だった」という話はよく聞きます。
妊婦さんの場合はそれが母体にも胎児にも影響することを、少しだけ頭に置いておいてほしいんです。
おすすめは、日中の空いている時間帯に行くこと
「それじゃあ、妊婦は初詣に行っちゃダメなの?」と思うかもしれません。
そんなことはありません。
行くタイミングと方法さえ選べば、無理なく、安全に参拝することはできます。
おすすめなのは、1月2日や3日の午前中。
人もだいぶ落ち着いていて、寒さも夜ほど厳しくありません。
それに、明るい時間帯なら足元も見やすく、転倒リスクもぐっと減ります。
また、できるだけパートナーや家族と一緒に行くことで、万が一のときにも支えてもらえる安心感があります。
私は実際、朝9時に家族と近所の神社へ行って、ゆっくり手を合わせ、温かい日差しの中でおみくじを引きました。
短い時間だったけれど、なんだかすごく満たされた気持ちになれたのを覚えています。
甘酒は妊婦さんが飲んでも大丈夫?注意してほしいポイント
初詣で冷えた体にふうっと湯気が立つ甘酒を手にすると、心まで温まるような気がしますよね。
私も妊娠前は、毎年あのやさしい甘さを楽しみにしていたタイプでした。
寒さで冷えきった手をあたためながら、ゆっくりと飲む甘酒の美味しさって、冬のごほうびみたいで。
だけど妊娠中となると、ちょっと立ち止まって考える必要があるんです。
甘酒には「2種類」あるって知っていましたか?
実は、ひとくちに甘酒と言っても、原料によって2つのタイプに分かれているのをご存知でしょうか?
ひとつは「酒粕(さけかす)」から作られるもの、もうひとつは「米麹(こめこうじ)」を使ったものです。
この2つ、見た目はほとんど変わりません。
だけど大きな違いは「アルコールが含まれているかどうか」。
酒粕甘酒には、ごく微量とはいえアルコールが含まれていることがあります。
一方、米麹甘酒は発酵の過程でアルコールを含まず、ノンアルコール飲料として扱われます。
つまり、妊婦さんが安心して飲めるのは「米麹」の甘酒だけということになります。
手作りの甘酒は原料がわからないことも
では、初詣で配られる甘酒はどちらなのか?
……これが、実はわからないことが多いんです。
多くの神社では甘酒を無料でふるまってくれたり、屋台で販売されていたりしますよね。
ですがこういった甘酒にはラベルがついているわけではなく、「酒粕使用なのか米麹使用なのか」を確認するすべがありません。
私自身、ある年の初詣で甘酒をいただいたとき、「これは米麹?」と屋台のおじさんに尋ねたら「うーん、たぶん酒粕かなあ」とあいまいな返事が返ってきて、そっと手を引っ込めたことがありました。
その場の空気や周りの人の「美味しい~!」という声に流されそうになりつつも、もし万が一アルコールが入っていたら……と思うと、口に運ぶ勇気が出ませんでした。
妊娠中のアルコール摂取は、わずかでも避けたい
妊娠中は「アルコールはできるだけゼロに」と指導されることが多いですよね。
ごく少量でも、胎児の発達に影響を与えるリスクがあると言われており、厚生労働省のガイドラインでも妊婦さんへのアルコール摂取は禁忌とされています。
「ほんのひとくちなら」「昔は気にされてなかった」といった声を聞くこともありますが、今は医学的にそのリスクが広く知られるようになりました。
赤ちゃんの未来を守るためにも、「判断に迷うものには手を出さない」が一番安全な選択だと思います。
どうしても体を温めたいときのおすすめドリンク
「甘酒がダメなら、どうやって温まればいいの?」という疑問もありますよね。
特に冷え性の妊婦さんにとって、外出先での体の冷えは本当にツラいものです。
そんなときは、ノンカフェインの温かい飲み物を持参するのがおすすめです。
たとえば、しょうが湯・ハーブティー・カフェインレスのココアや麦茶など。
最近ではコンビニや自販機でも「妊婦さん向け」にも安心な飲み物が増えてきているので、成分表示を確認して選ぶと安心です。
私はマイボトルに、蜂蜜入りのしょうが湯を作って持って行ったことがありました。
ふたを開けた瞬間、ふわっと立ちのぼる香りに、心までホッとゆるんだのを今でも覚えています。
もしも甘酒を飲むなら「事前に確認」を
どうしても甘酒を楽しみたい場合は、事前に原料を確認できるものを選ぶのがポイントです。
スーパーやネットで販売されている甘酒には「米麹使用」「ノンアルコール」など明記されているものが多く、安心して飲める商品もたくさんあります。
初詣にはマイ甘酒を持参して、休憩所でひと息つくのもいいかもしれませんね。
「自分の身体は自分で守る」という意識を持つことが、赤ちゃんの安全にもつながります。
妊婦さんが初詣に行くなら、できるだけ避けてほしい日と時間
「妊娠中だけど、やっぱり初詣に行きたい」
そう思う気持ちを、私は全力で肯定したいです。
新しい命を授かった今だからこそ、神様に手を合わせて「どうか無事に生まれてきてくれますように」って願いたくなりますよね。
その気持ちは、どれだけ慎重派の妊婦さんでもきっと心の中にあると思います。
ただし、行くタイミングだけは、少しだけ慎重に選んでほしいんです。
妊娠中の身体は思っている以上に繊細で、混雑や寒さといった外的な刺激にとても影響を受けやすいから。
無理なく、安全に、そして心穏やかに参拝するために、避けておいた方がよい「日」と「時間帯」について、しっかりお伝えさせてくださいね。
最も混雑するのは「12月31日の夜~1月1日」
まず真っ先に避けていただきたいのが、年越しから元旦にかけての時間帯です。
この時間は、多くの人が一斉に神社へ向かい、年明けの瞬間を境内で迎えようと集まってきます。
大きな神社であれば、列は何百メートルにもなり、数時間並ぶのも当たり前。
本殿の近くでは人の流れが滞り、まさに“押しくらまんじゅう”状態になります。
私自身、この時間帯に参拝したことがありますが、前からも後ろからも押される感覚は、正直かなり怖かったです。
特に妊婦さんは、転倒やお腹への衝撃が心配なので、物理的な安全が確保できない時間帯は避けるべきです。
また、この時間帯は気温が最も低くなりやすく、冷えやすい上に長時間の立ちっぱなしが重なります。
お腹の張りや、足のむくみ、息苦しさなど、妊婦さんにとっては体調を崩すきっかけになりかねません。
意外と見落としがちなのが「元旦のお昼」
「夜を避ければ元旦のお昼ならいいよね?」と思う方も多いかもしれません。
確かに夜に比べれば冷え込みはマシになりますが、実は元旦の昼間もかなり混雑します。
ファミリーや観光客が集中し、参拝だけでなく駐車場や交通機関も大混乱。
お正月ムードの賑やかさに気分が高揚して無理をしてしまう人も多く、結果的に「帰宅後に体調を崩した」という話も耳にします。
特に年始は病院も休みが多く、何かあったときにすぐ受診できない可能性も考えると、元旦はできれば“避けた方が安全”な一日だと私は思います。
おすすめなのは「1月2日以降の午前中」
では、妊婦さんにとって比較的安全な時間帯はいつなのか?
それは、1月2日か3日の午前中です。
このタイミングなら参拝客も落ち着き始めていて、人の流れにも余裕があります。
空気も冷たすぎず、陽が高くなる前に行動できれば、冷えによる負担も最小限に抑えられます。
私の出産前、1月3日の朝9時ごろに近所の小さな神社へ参拝に行ったことがあるのですが、空いていて、参道ものんびり歩けて、静かな気持ちでお参りできました。
おみくじを引いたり、お守りを選んだりする時間もゆっくり取れて、帰宅後も体調を崩すことなく、心から「行ってよかった」と思えたんです。
体調に不安があるときは「無理に行かない選択」も立派な決断
どんなに気をつけても、その日の体調次第では外出自体が負担になることもありますよね。
「せっかくの元旦だから」「今年だけは特別だから」と気持ちが焦ることもあるかもしれませんが、無理をしないことが赤ちゃんへの一番の思いやりになります。
もし「今日はやめておこうかな」と思ったときは、その感覚を信じて大丈夫です。
神様は日付を重視しているわけではないし、「行けなかったから罰が当たる」なんてことは絶対にありません。
むしろ、おうちでお守りを手に、静かに手を合わせるだけでも、きっと心は届いているはずです。
初詣に神社に妊婦が行くのは危険?のまとめ
妊娠中の初詣は、行く・行かないという白黒では割り切れないものだと思います。
家族の健康を願いたいという気持ちも、新しい命の誕生を前に神様にご挨拶したいという思いも、すごくよくわかります。
私自身、妊娠中に「今年はお参りできないのかな」とちょっと寂しくなった年がありました。
でもだからこそ、無理せずに過ごせたことが、あとから「よかった」と思える出来事になったんです。
混雑する時間帯や場所を避けたり、甘酒を遠慮したり、寒さ対策を万全にしたり。
そうやって工夫をしながら、自分と赤ちゃんを守る選択をしていくことが、すでに「お母さんとしての第一歩」なんじゃないかと私は思います。
大事なのは、「みんながやっているから」ではなく、「私はこうする」と自分で決めること。
もし今年は行かないと決めても、来年、赤ちゃんと一緒に行ける初詣はきっと何倍も尊く感じるはずです。
あなたと、これから生まれてくる小さな命が、新しい年を心穏やかに迎えられますように。
その願いが、ちゃんと届きますように。
そんな気持ちで、そっとエールを送りますね。