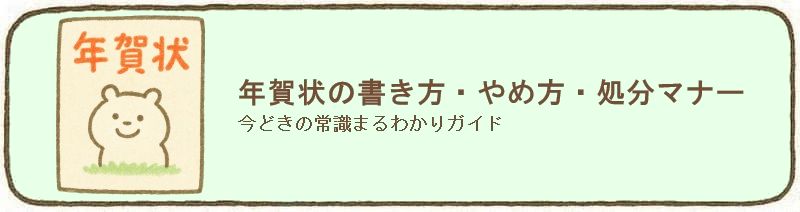近年、年賀状を出さないという選択をする人が着実に増えています。
特に20代の若い世代では、その割合が半数近くにものぼるという調査結果もあり、「年賀状はもう古い文化かも?」と感じている人も少なくありません。
一方で、職場や年配の方との関係では「出さないと失礼では?」と悩む声も多く、マナーとのバランスに迷うケースもあるようです。
この記事では、年賀状を出さない人が実際にどれくらいいるのか?
その理由や背景をデータと共に紹介しながら、出さない場合に気をつけたいマナーや、代わりの挨拶方法までをやさしく解説していきます。
時代とともに変化する年始のあいさつ事情を押さえて、無理のないスタイルで気持ちのよい新年を迎えるヒントを見つけてみてくださいね。
年賀状を出さない人はどのくらいいるの?
大手メーカー調査で判明!出さない人は若年層に多い
最近では「年賀状を出さない人」が確実に増えています。
特にここ数年でその傾向は加速しており、年末の忙しさやデジタル化の進展など、さまざまな要因が関係しているようです。
ある大手文具メーカーが行った調査によると、年代が若くなるほど「年賀状を出さない」と答える人の割合が高くなっていて、若年層を中心に年賀状離れが進んでいることが明らかになっています。
20代では半数が「出さない」と回答
この調査では、特に20代の若者たちの約半数が「年賀状は出さない」と回答していました。
スマホやSNSでのやりとりが主流の今、紙の年賀状を準備して手書きで出すという行為自体が、手間に感じられるのかもしれません。
さらに、住所を知らない・聞きづらいという点も年賀状を送らなくなる理由の一つと考えられます。
形式よりもスピード感や気軽さを大事にする今の若者たちにとって、年賀状はやや古いコミュニケーションの手段なのかもしれませんね。
年配層や職場文化による「出す」圧力もまだ根強い
一方で、年賀状文化が根強く残っている層も確実に存在しています。
特に年配の方や、昔ながらの慣習を大切にする職場では、「年賀状は社会人としての常識」という考え方が根強く残っていることも多いようです。
そうした環境にいると、「出さない=失礼」と受け取られてしまうのではと不安になる人も少なくありません。
職場での空気や上司・取引先の反応を気にして、やめたくてもなかなかやめられないという声も聞かれます。
年賀状を出さない理由とは?
「面倒」「コストがかかる」からやめた人が多数
年賀状を出さない理由として、まず最も多くの人が挙げるのが「準備が面倒」という点です。
印刷するにも文面やデザインを考えたり、手書きのメッセージを添えるとなると、かなりの時間と労力がかかりますよね。
さらに、年末は何かと忙しい時期でもあるため、「わざわざ年賀状のために時間を割くのが難しい」と感じる人も多いようです。
また、「コストがかかる」というのも大きな理由のひとつです。
はがき代だけでなく、プリンターのインク代や印刷代、宛名書きのための手間まで含めると、家族や知人が多ければ多いほど負担が増します。
「何十枚も出すのはちょっと厳しい」と感じる人にとっては、費用の面でもやめる決断に至りやすいのかもしれません。
SNSやメールの普及で代替可能に
年賀状をやめた人たちの多くが活用しているのが、LINEやSNS、メールといったデジタルツールです。
これらの方法は、年賀状と違って事前に準備しておかなくても、元日やその前後にサッと送ることができてとても便利です。
メッセージに写真やスタンプを添えたり、デジタル年賀画像を作って一斉送信したりと、工夫次第で個性を出すこともできます。
特に若い世代を中心に、こうしたツールを使って気軽に新年のあいさつを交わす文化が根づいてきています。
SNSでは複数人にまとめて挨拶ができ、コメント欄でやりとりが続くのも魅力ですね。
企業文化の変化と「虚礼廃止」の影響も
加えて、年賀状を出さないことが「非常識」とされなくなってきた背景には、企業文化の変化も大きく関係しています。
特に「虚礼廃止(きょれいはいし)」という考え方が広まりつつあり、形式的なやりとりや義理での贈答を廃止する動きが加速しています。
この「虚礼廃止」は、年賀状に限らず、暑中見舞いやお中元、お歳暮など、これまで当たり前とされていた社交儀礼の多くを見直す流れのことです。
実力主義が浸透してきた今の企業風土では、そういった形式的な交流よりも、実質的な成果や関係性が重視されるようになってきました。
こうした動きにより、「出さないこと=マナー違反」という意識は少しずつ薄れてきているのかもしれません。
職場で年賀状を出さないのはマナー違反?
本来は遠方の人に送るものだった
年賀状は、そもそも新年の挨拶に直接行けない相手に向けて書くものなんです。
つまり、遠方に住んでいたり、なかなか会う機会がない相手に、代わりの手段として送るというのが本来の目的なんですね。
ですから、毎日顔を合わせて仕事をしているような同僚や上司に対しては、あえて年賀状を送る必要はないともいえます。
むしろ、文面での形式的な挨拶よりも、直接言葉で気持ちを伝える方が、よほど心がこもっていると感じてもらえることもあります。
毎日顔を合わせる職場では不要なケースも
職場で日々顔を合わせている同僚や上司に対して、改めて年賀状を送るのは、かえって不自然に感じられることがあります。
例えば、毎日一緒に仕事をしているのに、形式的な文章での挨拶が届くと「わざわざそれいるかな?」という印象を持たれることも。
そう考えると、年始の出社時にきちんと対面で「今年もよろしくお願いします」と挨拶することの方が、自然で気持ちが伝わりやすいものです。
普段の関係性が良好であればあるほど、無理に年賀状を送る必要は感じなくなるかもしれませんね。
新年の挨拶は「直接言う」のが丁寧な対応
社内では、新年の最初の出勤日こそが、自然な挨拶のタイミングです。
「おはようございます。
今年もよろしくお願いします」と一言伝えるだけで、十分に新年のご挨拶は成立します。
形式ばった文書よりも、その場で交わす会話の方が親しみも感じられて、温かみがありますよね。
忙しい朝の中でも、相手の目を見てしっかりと挨拶を交わすことが、何よりの礼儀にもなりますし、良い関係づくりの第一歩になります。
年賀状を出さないときの代わりの挨拶方法
メールでの新年挨拶のポイントと注意点
メールで新年の挨拶を送るときは、やっぱり相手との関係性に応じて送り方を工夫することが大切です。
例えば、同僚や部署内の仲間であれば、ある程度ラフな言い回しや一斉送信でも問題ないケースが多いです。
ですが目上の人や取引先の場合は、必ず一人ひとりに丁寧に個別のメッセージを送るようにしましょう。
文章もテンプレートをそのまま使うのではなく、
- 相手の名前をきちんと入れたり
- 一言でも相手に合わせた内容を添える
また、年始のメールはあまり長文にせず、簡潔で心のこもったメッセージにするのがポイントです。
「新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします」といった基本の文面に加え、「今年も一緒に頑張っていきましょうね」といった温かみのある言葉を加えると、より好印象につながりますよ。
SNSでスマートにまとめてあいさつ
最近では、SNSを使って年始の挨拶をする人もとても増えてきました。
FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などに「新年のご挨拶」の投稿をして、それを見た人たちとコメント欄でやり取りするスタイルも一般的になりつつあります。
この方法なら、気軽にたくさんの人に向けて挨拶ができるうえ、コメントのやりとりでコミュニケーションも広がるというメリットがあります。
さらに、無料の年賀イラストや写真アプリなどを使って、オリジナルの画像を添えて投稿すれば、華やかで楽しい印象になります。
海外の友人がいる場合には英語やその国の言葉を使ったメッセージも添えると、より親しみが伝わりますね。
ただし、会社の同僚や上司などとはSNSで繋がっていないこともあるため、その場合はメールや直接の挨拶に切り替えるようにしましょう。
SNSは便利なツールですが、相手に応じた配慮が必要です。
相手や関係性に応じた使い分けが大切
年賀状やメール、SNSなど、年始の挨拶方法はたくさんありますが、大事なのは
「誰に」
「どうやって」
伝えるかを意識することです。
たとえば、親しい友人にはSNSの投稿で十分かもしれませんが、ビジネスの場ではやはりきちんとした挨拶が求められることもあります。
- 相手との関係がカジュアルであればSNSやLIN
- 少しかしこまった関係であればメール
- さらにフォーマルな関係であれば年賀状や直接の挨拶
どの手段であっても、「一人ひとりに向き合う気持ち」が伝わるように心がけることで、相手にも好印象を与えられますよ。
年賀状じまいをスマートに伝える方法
「今年で最後」の一言を年賀状に添える
「年賀状をやめたいけど突然やめたら失礼かも…」と感じる方は多いものです。
そんなときは、最後に出す年賀状に「今年を最後とさせていただきます」とさりげなく書き添えるのがおすすめです。
いきなりやめるよりも、相手に事前に意図を伝えることで誤解を防ぐことができます。
このときに「今後はSNSやメールなどで新年のご挨拶をさせていただきます」といった一文を加えると、相手も安心して受け止めてくれるでしょう。
また、
「これまでお付き合いいただきありがとうございました」
「今後も変わらぬご縁をよろしくお願いいたします」
といった感謝や前向きな言葉を添えることで、年賀状をやめること自体が失礼に感じられにくくなります。
直接会話やメールでの事前宣言も有効
年末の時期に、軽い感じで「今年から年賀状は控えるようにしてるんです」と口頭で伝えておくのも自然な方法です。
相手にとっても構えずに受け入れやすく、無理なく伝えることができます。
また、近年はメールでの年始挨拶も浸透しているので、「私は来年からはメールでご挨拶させていただきますね」と先にお知らせしておくのもスマートな方法です。
私自身も、年末の雑談の中で「うちは今年で年賀状卒業しようと思ってて」と気軽に話しておくだけで、相手の反応も柔らかくなった経験があります。
無理なく、自分らしい伝え方を選んでみてくださいね。
相手を気遣う一文を添えて印象アップ
たとえ年賀状をやめる選択をしても、ちょっとした一文で印象は大きく変わります。
「今後も変わらぬお付き合いをよろしくお願いします」
「これからもどうぞよろしくお願いいたします」
など、相手との関係を大切にしたい気持ちが伝わる一文を添えるだけで、やわらかく丁寧な印象になります。
年賀状を出さないからといって、相手との縁を切るわけではありません。
むしろ、これからもよい関係を築いていきたいという気持ちを文章で表現することで、相手に安心感を与えることができるんですね。
気持ちのこもった一文が添えられていれば、たとえ形式が変わっても、人間関係はきちんと続いていきますよ。
年賀状をやめても印象を悪くしない工夫とは?
取引先へのメールは送信タイミングに注意
年末年始のご挨拶メールを取引先に送るときは、タイミングがとても重要です。
基本的には、年末の場合は仕事納めの数日前から、年始の場合は松の内(1月7日頃)までに送るのが一般的なマナーとされています。
年末の時期は企業によって仕事納めの日が違うため、相手先の営業日やスケジュールを事前に確認しておくと安心です。
また、年始のご挨拶を送る場合は、取引先の仕事始めの日程も把握しておくと、迷惑にならずにスムーズな対応ができます。
業務開始直後は忙しい可能性もあるので、1月4日~5日ごろの落ち着いたタイミングを見計らって送るのがおすすめです。
さらに、メールの送信時間帯も朝の早すぎる時間や深夜は避け、相手がメールをチェックしやすい午前中~昼過ぎを選ぶと、より丁寧な印象を与えることができますよ。
名前の誤記・一括送信のリスクに気をつけて
ビジネスメールで最も気をつけたいのが、相手の名前を間違えることです。
特に新年のご挨拶メールでは、最初の印象が非常に重要になります。
うっかり名字を間違えたり、敬称を省略してしまったりすると、相手に失礼な印象を与えてしまうこともあるので要注意です。
また、一括送信によるリスクも見逃せません。
複数の宛先に同じ文面を一斉に送ると、CCやBCCの設定ミスで他の宛先が見えてしまうなどのトラブルが発生する可能性があります。
特に取引先の場合は、必ず1件ずつ個別にメールを作成しましょう。
そして、文面にもその相手に合った内容を少し加えるだけで、丁寧な対応として好印象を持ってもらえますよ。
送信前には必ず宛先・名前・文面を見直してから送るようにしましょう。
年賀状をもらったら“遅れてでも返す”のがマナー
自分が年賀状を出さないと決めていた場合でも、相手から年賀状が届いたら、何らかの形でお返しするのが礼儀です。
返信が遅れてしまったとしても、「挨拶が遅れて申し訳ありません」と一言添えてお返しすれば、失礼にはなりません。
むしろ、きちんと対応することで丁寧な印象を残すことができます。
もし年賀状の用意がない場合でも、メールや寒中見舞いという方法で返すこともできます。
「年賀状をいただきありがとうございました。
今年もどうぞよろしくお願いいたします」といったシンプルな一文だけでも、誠意が伝わりますよ。
重要なのは、気づいた時点ですぐに行動に移すことです。
タイミングを逃さず、誠意をもって対応すれば、良い関係を保つことができます。
まとめ|年賀状を出さない人が増える中で気をつけたいこと
形式よりも“気持ちが伝わる方法”を大切に
昔は年賀状が新年のあいさつの主流でしたが、今ではその形も人それぞれに変化してきました。
年賀状を出すか出さないかという選択よりも、「どのように気持ちを伝えるか」がより大事な時代になってきたと言えます。
紙に書かれた挨拶状でなくても、LINEやSNSのメッセージ、あるいは直接の一言など、形は変わっても相手に気持ちが伝わることのほうが価値があるんですね。
特に最近では、年始の忙しい時期に無理して年賀状を出すこと自体が負担に感じられることもあります。
そんな中でも、たとえば「今年もよろしくね!」と直接声をかけたり、短いメッセージを添えたりするだけでも、相手の心に響くことはあります。
大切なのは、形式よりも気持ちの温かさや思いやりです。
自分に合ったスタイルで、気持ちを込めた新年の挨拶を届けてみてくださいね。
関係性や相手によって柔軟に対応しよう
全員に年賀状を送る、あるいは全員に出さないという一律な対応ではなく、
「この人にはメールで」
「この人には直接言おう」
など、相手との関係性に合わせて柔軟に挨拶の方法を選ぶのが、今の時代の自然なマナーになってきています。
たとえば、長く会っていない親戚には年賀状を送るけれど、日常的に会う友人にはLINEであいさつする、というような使い分けがあると、お互いに違和感なく過ごせるかもしれません。
自分の生活スタイルや相手の好みにも配慮して、無理なく気持ちよく続けられる方法を探すことが大切です。
「こうしなければいけない」という枠にとらわれず、自分らしいスタイルを見つけていけるといいですね。
「出さない派」でも円滑な人間関係は築ける!
年賀状を出さないという選択をしたからといって、決して人間関係が悪くなるというわけではありません。
むしろ、年賀状以外の場面でこまめに連絡を取ったり、日頃の感謝の気持ちを言葉にしたりすることで、よりよい関係が築ける場合もあります。
たとえば、久しぶりに会ったときに「今年もよろしくね」と一言添えるだけでも、それは立派な新年の挨拶です。
また、誕生日や季節の節目など、別の機会に気遣いを見せることで、年賀状がなくても関係性はしっかり保てます。
大事なのは、形式ではなく「心の通い合い」。
相手を思いやる気持ちや、さりげない行動の積み重ねが、信頼関係を深めていくのです。