 子育て
子育て 雛人形をお下がりでも大丈夫?お祓いの必要性と正しい引き継ぎ方
雛人形を譲り受けるとき、「このまま飾ってもいいのかな?」「お祓いはしたほうがいいのかしら?」といった疑問や不安がふと頭をよぎることってありますよね。とくに自分の娘や孫など、次の世代の子どもに使わせるつもりでいる場合は、やっぱり縁起やしきたり...
 子育て
子育て  子育て
子育て 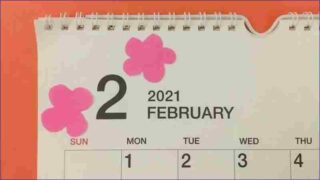 子育て
子育て  子育て
子育て