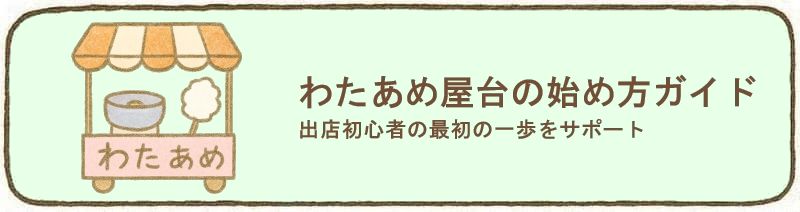わたあめって、見ているだけでなんだか心がふわっと軽くなるような、そんな魔法みたいなお菓子ですよね。
だからこそ、お祭りやイベントで「自分もわたあめを作ってみたい」と思う人が増えているのもすごくわかるんです。
けれど、実際に出店しようと準備を始めると、最初に必ずぶつかる壁があります。
それが衛生管理なんです。
あまりにも素朴で優しい食べ物だから、つい手軽に考えてしまいがちなのですが、実際はお客さんの口に入るものとしてしっかり向き合っていく必要がありますよね。
特にイベント会場は風や人の動きが激しくて、普段のキッチンとはまったく違う環境なんです。
わたしも初めて出店したときは、思っていた以上に気をつけるポイントが多くてびっくりしたのを覚えています。
汗を拭いた手でそのまま作業しそうになったり、湿気でザラメが固まりかけたり、子どもがお店の台にぐっと手を伸ばしてきたりと、ひやっとする場面がいくつもありました。
でもそのたびに感じたのは、ちゃんとした衛生管理は誰かを守るための大事な安心材料だということです。
お客さんが安心して食べられるという気持ちはもちろんですが、自分自身が胸を張ってお店に立てるという心の安定にもつながるんですね。
この冒頭を読んでくれているあなたもきっと同じような不安や疑問を抱えていると思います。
その気持ちにそっと寄り添いながら、現場で本当に役立つ衛生管理の知識を一つずつ丁寧に届けていきますね。
まず知っておきたい「わたあめ販売の衛生ルールの基本」
「わたあめって砂糖だけでできてるから、特別な衛生対策なんていらないんじゃない?」なんて思っていたのは、かつての私です。
ですが、実際にイベントに出店してみると、それがどれだけ浅はかだったか痛感しました。
わたあめは確かに腐りにくい食品ではあるけれど、それを作る
「人の手」
「空気中のホコリ」
「風に舞う髪の毛」
まで含めて考えると、意外と衛生リスクって多いんです。
しかも、子どもが笑顔で口にするものだからこそ、「安心して提供できる環境」を整えることがとても大切になってくるんですね。
販売する時点で「わたあめは食品」になる
まず大前提として、イベントなどでわたあめを販売するという行為は、単なる「遊び」や「体験」ではなく「食品の提供」として扱われます。
つまり、提供する以上は食品衛生法の基本的な考え方を踏まえて、安全に提供する責任が生まれるということなんですね。
これは、たとえキッチンカーや模擬店のような一時的な出店であっても変わりません。
実際、自治体の保健所でも「露店営業」や「臨時の簡易営業」にあたるケースとして扱われることが多く、その場その場で求められる衛生基準をきちんと理解しておくことが求められます。
わたあめが腐りにくくても油断は禁物
たしかに、わたあめの原料はほぼ純粋な砂糖なので、日持ちはしますし、細菌が繁殖しやすい食品ではありません。
けれども、実際の現場で問題になるのは「糖分そのもの」ではなく、それを取り扱う人の手指の衛生状態や、湿度や気温などの環境要因なんです。
汗ばんだ手でザラメをすくえば、その一瞬の接触から湿気が入ってしまったり、異物が混入したりすることもあります。
また、綿あめのフワフワの繊維はとても軽く、風に舞いやすい性質がありますから、空気中のゴミや髪の毛、虫なども簡単に付着してしまうリスクがあります。
つまり、わたあめだからこそ、目に見えないところで起こる“見落としやすいトラブル”に気づいておくことが大切なんですね。
お祭りやイベントの現場は衛生面の落とし穴がいっぱい
これは実体験からですが、屋外の出店では風の影響、テントの影、直射日光、周囲の騒がしさなど、思っていた以上に予想外のことが次々に起こります。
風が吹けばわたあめが飛んでしまうし、お客さんの列ができれば焦って作業が雑になりがちです。
そして一番多いのが、「子どもが手を伸ばして機械やザラメに触れようとすること」。
これ、ほんとに多いです。
だからこそ、準備段階からブースの設計や動線の工夫も含めて「清潔に保ちやすい配置」を考えておくことが、当日の安心にもつながっていくんですね。
自治体やイベントによって基準が違うからこそ事前確認が命
「前のイベントでは大丈夫だったのに、今回はNGってどういうこと?」というのは、イベント出店経験者なら一度は感じたことがあるかもしれません。
それくらい、地域の保健所によって衛生に関する指導内容や解釈が異なることがあります。
ある自治体では「手洗いタンクが必須」と言われる一方、別の地域では「アルコール消毒でもOK」とされることも。
こうした差異があるからこそ、事前にしっかりと出店先のイベント主催者や自治体の保健所に確認を取っておくことが重要なんですね。
「このくらいで大丈夫だろう」は後でトラブルの元になります。
私も一度、「給水用タンクが足りない」と指摘されてヒヤリとしたことがありますが、事前に一言確認しておけばよかったと本当に後悔しました。
「安心して食べてもらう」ことがいちばん大切な理由
どんなに見た目がかわいくて、どんなに味がおいしくても、お客さんにとっての「食の不安」が一度でも生まれてしまえば、それはもう立ち直るのが難しいこともあります。
特に、小さな子どもに買ってあげる親御さんにとっては、「このお店、大丈夫かな?」という印象はとても大きな判断材料になりますよね。
だからこそ、わたあめ販売では「安全」と「清潔感」を伝える努力が必要なんです。
それは、消毒の徹底や機材の手入れだけじゃなく、清潔なエプロンや帽子、整えられたブース、手際よく動く姿勢など、トータルで伝わるものなんですよね。
見た目の印象も含めて、衛生対策は出店者自身の信頼を高める力になるんです。
食品衛生法のポイント|ここだけ押さえれば大きく間違わないよ
法律って聞くと、なんとなく小難しそうな雰囲気がありますよね。
でも実際にイベント出店で求められることって、「ちゃんとしたお店として、安全に食べ物を出してね」というごく当たり前のことばかりなんです。
とはいえ、どこからが違反になるのか、何を準備すれば安心なのかがわからないままでは、不安なまま当日を迎えてしまうことになりますよね。
ここでは、わたあめを販売する上で絶対に押さえておきたい、基本的な衛生ルールと法律のポイントをやさしく整理してお伝えしますね。
イベント販売は「簡易営業」や「露店営業」にあたるケースが多いよ
一時的な販売であっても、食品を扱う場合には「営業許可」や「届出」が必要になることがあります。
イベントの規模や主催者の意向にもよりますが、多くの場合は「簡易営業」として扱われるケースが多くって。
自治体によっては正式な申請は不要でも、一定の衛生基準を満たしているかどうかを確認されることがあるんですね。
出店するイベントのタイプによって、求められる対応が異なることもあるので、「このイベントではどんなルールがありますか?」と主催者や保健所に確認しておくことが安心につながります。
手洗い・消毒・手袋は「見た目の安心」も含めて大切
イベント会場って手を洗う場所がなかったり、手袋をしていても汚れていたりする出店者さんを見かけることがありますよね。
でもそれって、お客さんから見ると「うーん…」と感じてしまう大事なポイントなんです。
わたあめ販売では、手洗い用の簡易タンクやペーパータオル、石けんなどを持参しておくことが基本になります。
そしてその後に使い捨て手袋をつける。
この流れを準備段階からきちんと整えておくだけで、「あ、このお店ちゃんとしてるな」と思ってもらえるきっかけにもなるんですね。
実際に、あるお母さんが「子どもがアレルギー持ちだから、ちゃんと手袋してるお店じゃないと買えないんです」と話してくれたことがありました。
誰にとっても「清潔な環境で作られているかどうか」が大切な判断材料になっているんです。
ザラメ・色粉・トッピングの取り扱いにも注意が必要だよ
わたあめって、シンプルに見えて意外と繊細な素材を使っているんです。
特にフレーバーや着色用の色粉は湿気を吸いやすいです。
なので、容器のフタを開けっ放しにしていたり、屋外に出しっぱなしにしていたりすると、空気中のホコリやゴミが入り込んでしまうリスクもあります。
なので、開封後は密閉容器に移して、できれば使う分だけを小分けにして取り出すなど、衛生的に管理しやすい工夫をしておくと安心です。
「ちょっとのことだから」と思ってそのままにしてしまうと、思わぬトラブルの原因になることもあるので、ここは丁寧に気を配りたいところですね。
保健所からよく見られる3つのチェックポイント
私自身が出店許可を取る際に聞かれたことや、実際にイベント会場で見られたことから考えて、保健所が特によくチェックするのはこの3つです。
1つめは「手洗い設備の有無」。
簡易的なものでOKですが、水が出る状態であること、排水できる容器があること、そして石けんとペーパーがあることが求められます。
2つめは「食材・材料の保管状態」。
湿気や高温、直射日光を避けた適切な保存方法をしているかどうかを見られます。
3つめは「機械や備品の清潔さ」。
糖分が飛びやすいわたあめ機は特に汚れが付きやすく、油断しているとベタつきやホコリが目立つこともあります。
清掃が行き届いているか、使い終わった道具が雑に置かれていないかも、印象に大きく影響しますよ。
原料(ザラメ)・資材の保管方法|湿気と温度に気をつけるだけで安心できるよ
わたあめの魅力は、そのふわふわと甘くてやさしい口どけにありますよね。
でもその「ふわふわ」を生み出すザラメは、見た目以上にとっても繊細。
湿気や温度、ちょっとした保管ミスが思わぬ失敗を呼ぶこともあります。
実際に、わたしも最初は普通のタッパーにザラメを入れて持ち込んだら、途中で固まってしまって綿が出てこなくなってしまったことがありました。
あのときの焦りったらもう…。
でも、正しい保管のポイントさえおさえておけば、こうしたトラブルはちゃんと防げるんです。
ここでは、ザラメや色粉などの原料を清潔に、そして安定した状態で扱うための具体的な工夫をまとめていきますね。
ザラメは「開封後すぐの対応」が大事になるよ
ザラメはとにかく湿気に弱いです。
開封した瞬間から、空気中の水分をどんどん吸ってしまって、気づいたら中でゴロゴロと固まりになっていた…なんてこともよくあります。
だからこそ、開けたらすぐに密閉容器に移し替えるのが鉄則です。
チャック付きの保存袋を使うのもおすすめですが、できればさらにその袋ごとタッパーなどのしっかりしたケースに入れて“二重保存”しておくと安心感が違います。
わたしもそれを始めてからは、天気に振り回されることが本当に減りました。
湿度と温度差が品質を左右するって知ってた?
保管場所の気温や湿度も、ザラメや色粉にとってはかなり影響があります。
例えば、冷房の効いた部屋から急に暑い屋外に持ち出すと、容器の内側に結露が発生して中が湿っぽくなることがあるんです。
この「結露」がクセモノで、ほんのわずかでも水分が混ざるとザラメが均一に回らなくなってしまいます。
ベストなのは、気温の変化が少ない場所に保管しておくこと。
屋外での販売時は、なるべく日陰を選び、テント内でも直射日光が当たらない位置に置くなどの工夫が効果的ですよ。
フレーバー粉・色粉はしっかり密閉して取り扱おう
カラフルで可愛いわたあめを作るために欠かせない色粉や香料入りの粉も、扱いには十分な注意が必要です。
特に開けっ放しで放置すると湿気だけじゃなく、飛んできたホコリや髪の毛が入ってしまうこともあるので、使用するたびにきっちりフタを閉める癖をつけておきましょう。
容器にラベルを貼って「開封日」を書いておくと、どのくらい使っているかの目安にもなりますし、品質管理にもつながりますよ。
異物混入を防ぐために意識しておきたいこと
わたあめはその性質上、とっても軽くて空気中のものをすぐにまとってしまいます。
だからこそ、「袋が開いていたからゴミが入っちゃった」なんてことにならないように、原料や備品を置く場所は、風やホコリが入りにくい場所を選ぶのがポイントです。
また、地面近くに材料を置かないようにするのも大切です。
実際に私も以前、机の下に置いていたザラメ袋に、子どもの靴がぶつかって砂が入りかけたことがありました。
ちょっとした油断が、衛生面のトラブルにつながることもあるので、「どこに何を置くか」も意識して準備すると安心できますよ。
販売当日の衛生管理(実践編)|初心者が迷いやすいポイントを全部まとめたよ
準備がどれだけ万全でも、いざ当日になってみると「あれ?こんなときどうすればいいの?」って場面がいくつも出てくるものなんですよね。
とくに初めて出店する場合は、お客さんの対応と作業とでいっぱいいっぱいになって、衛生管理まで手が回らなくなりがちです。
でも、実はちょっとした気配りと工夫だけで、衛生面はぐんと安心できるものになるんです。
ここでは、出店当日に慌てないための動線づくりや身だしなみ、作業中のポイントなど、初心者さんがよく迷う“リアルな現場”の視点でお伝えしていきますね。
販売前のチェックリストは「5つだけ」でいいよ
当日の朝はバタバタしてしまいがちなので、チェックポイントはあえて少なめにしておくと気持ちに余裕が生まれます。
- 手洗い用の水・石けん・ペーパータオルはすぐ使える場所にある?
- 材料やトッピング類は密閉されてる?
- わたあめ機は清掃済みで、セットも問題ない?
- 手袋やトングなどの清潔な備品がそろってる?
- お客さんとの受け渡しスペースに無駄がない?
この5つがOKなら、だいたいの不安はカバーできます。
服装・髪型・アクセサリーは意外と見られてる
「飲食店じゃないし、そこまで気にしなくても…」と思っていた時期が私にもありました。
でも、お客さんは意外と見ているんです。
わたあめ屋さんがニコニコしていても、髪の毛がボサボサだったりブレスレットがカチャカチャ当たってたりすると、それだけで「ちょっと不安…」と感じる人もいます。
エプロンや帽子はもちろん、髪は後ろでしっかり束ねる、ピアスや指輪は外すといった“お店としての清潔感”を意識することが、信頼につながるんです。
機械のセットは「手袋のまま」やらないのがコツ
わたあめ機を設置するときって、つい手袋をしたまま回転部に触っちゃうことありませんか?
でも、その手袋って材料を扱う用ですよね。
つまり、調整や設置で手が汚れた状態のまま、その手袋でザラメを触ってしまうと意味がないんです。
だから私は、「設置までは素手(清潔な手)で、作業に入る直前に手袋をつける」と決めています。
手袋はあくまで「清潔な状態で材料や袋を触るため」のものなので、機械の調整や移動には向いていないんです。
わたあめの受け渡しは「1人分ずつ」が基本
忙しいときに何本も一気に巻いて並べたくなる気持ち、すごくわかります。
でも、わたあめは空気中の湿気やホコリをすぐに吸ってしまうので、できるだけ1本ずつ作って、その場で袋詰めして手渡すのが一番安全で衛生的なんです。
とくに風がある日は、綿が飛んだり、ゴミが混じったりしやすいので、作ったら即パッケージ!を心がけましょう。
試食を渡すなら「手渡ししない」工夫をしてみて
試食を出すことは販促としてとても効果的ですが、衛生面でトラブルになるリスクもゼロではありません。
スプーンや小さな紙カップを使って「お客さんが自分で取れる形」にしておくと、触れ合いが減って安心ですし、何よりスマートに見えます。
一度でも「直接渡してきたのが気になった」という声を聞くと、その後のお客さんにも影響することがあるので、こういった配慮は本当に大切です。
わたあめ機の洗浄・メンテナンス|安全のために「どこを」どの程度洗う?
わたあめ機って、そんなに汚れないんじゃないの?って思っていたのは、使い始めたばかりの頃の私です。
でも実際は、使えば使うほどザラメの粉や飛び散った砂糖がこびりついて、放っておくとあっという間にベタベタになってしまうんですよね。
しかもそれだけじゃなく、湿気が残っているとカビやサビの原因にもなってしまいます。
機械は見た目の派手さよりも「清潔に保つこと」がなにより大切。
ここでは、実際にどこをどう洗えばいいのか、どのくらいの頻度で手入れが必要なのか、安心して使い続けるための洗浄とメンテナンスのコツをお伝えしていきますね。
イベント前の洗浄は「習慣化」しておくと楽になるよ
イベント当日の朝にバタバタと洗おうとすると、忘れ物や洗い残しが出てきやすくなります。
だから私は、イベント前日に必ず洗って、乾かしてから袋に入れるという流れを習慣にしています。
洗う場所は、わたあめが接触する部分全体。
とくに回転皿や側面の内側には細かいザラメの粒が残っていることが多いので、しっかり目視でチェックしましょう。
ここで手を抜いてしまうと、当日機械の動きが悪くなったり、見た目の印象もガタ落ちしてしまいます。
イベント後は「高温+甘さ」で汚れがしつこくなるよ
わたあめ機は高温になるので、イベント後には焦げたザラメが固まってこびりついていることも多いです。
そんなときに無理やりこすってしまうと、傷がついたりして劣化の原因になります。
中性洗剤をぬるま湯に溶かして、やわらかいスポンジで優しく拭き取るのが一番効果的。
しつこい汚れには、湿らせた布で少し時間をおいてから拭き取るとスルッと落ちやすくなりますよ。
金属部分にはなるべく水をためず、洗ったらすぐに拭き上げることも大切です。
使ってはいけない洗剤や道具に注意してね
漂白剤や強アルカリ性の洗剤、研磨剤入りのスポンジは絶対に使わないようにしましょう。
食材が触れる部分に使うことで有害成分が残るリスクもあるし、機械自体のコーティングが剥がれてしまう可能性もあるんです。
私は以前、ちょっと気を抜いて食器用の漂白スプレーを使いかけたことがあって、ギリギリで気づいてヒヤッとした経験があります。
安全のためにも、使う道具や洗剤は「食品対応のもの」に限定するのが安心ですよ。
乾燥が足りないと「サビやカビ」の原因になるよ
洗った後は乾拭きで終わりにしがちなんですが、それだけだと水分が細かい隙間に残ってしまって、**気づいたらサビが出てた…なんてこともよくあります。
**扇風機の風を当てて完全に乾かす、日陰で風通しのいい場所に数時間置くなど、内部までしっかり乾燥させることが機械を長持ちさせるコツなんです。
とくに保管場所が湿気の多い場所だと、なおさら乾燥はしっかり意識したいところですね。
よくあるトラブルと対処法|「こんなときどうするの?」に全部答えるよ
どれだけ準備をしっかりしていても、イベント当日はなぜか予想外のことが起こるものなんですよね。
わたしも何度「えっ、いま!?このタイミングで!?」と心の中で叫んだことか…。
特に屋外の出店では天気や湿度、機材のコンディションによってわたあめの出来が左右される場面も多いので、その場でどう対処するかがとても大切なんです。
ここでは、出店初心者さんがつまずきやすいポイントや「ありがちだけど困る!」というトラブルと、その乗り越え方を一つひとつわかりやすくお伝えしていきますね。
湿気でわたあめが溶けてしまうときの対策
わたあめが溶ける原因のほとんどは「湿度」です。
特に夏場や雨の日は空気中の水分が多く、巻いている途中でフニャっとしてしまったり、袋に入れた後でもべたつくことがあります。
そんなときは、とにかくスピードが命です。
綿が巻けたらすぐ袋に入れて、素早くしっかりと封をするのが基本。
それだけでも溶けにくさが全然違います。
さらに言うと、袋も厚手のものを使ったほうが湿気から守ってくれるので安心ですよ。
ザラメが固まって綿が飛びにくくなったとき
開封したザラメを長時間外に置いていたり、前日に湿気を吸っていたりすると、機械に入れてもうまく回らず、わたあめが出てこないことがあります。
そんなときは、まずザラメに固まりがないか確認して、もし粒が大きくなっていたらふるいにかけて細かくしてから再投入してみてください。
それでもダメな場合は、一度ザラメを全部出して、乾燥している新しいザラメに入れ替えることも考えてみて。
焦らず、落ち着いて対処するだけで、意外とあっさり復活することも多いんですよ。
風が強くて綿が飛んでしまう日
屋外出店で一番の敵ともいえるのが「風」ですよね。
風がある日は、せっかく巻いたわたあめがふわーっとどこかへ飛んでいってしまったり、綿が広がりすぎて巻けなくなったりしてしまうこともあります。
そんなときは、風よけのビニールシートやパーテーションをテント内に設置するのが有効です。
テントの向きを変えるだけでも風の流れが変わることがあるので、出店場所の地形や風向きを観察して調整してみてくださいね。
場合によっては、いったん機械を止めて様子を見る勇気も大切です。
アルコール消毒を使える場所・使えない場所の違い
手やテーブルなどにはアルコール消毒が有効ですが、**わたあめ機の中や、砂糖が直接触れる部分には使わないようにしましょう。
強力な消毒液は、素材を傷めるだけでなく、食材ににおいが移ったり、残留成分が残るおそれもあるんです。
基本的には、食品が触れる場所には中性洗剤で洗浄し、しっかりすすいで乾かすのが安心です。
どうしても消毒したい場合は、「食品衛生対応のアルコールスプレー」**を使用するようにしてくださいね。
衛生的に販売できる“ブース作り”|見た目の安心感が売上にもつながるよ
「衛生管理」って、手洗いや機械の洗浄だけじゃなくて、実は**お客さんが目で見て感じる“清潔感”**も含まれているんですよね。
特にわたあめは子ども向けのイメージが強いからこそ、親御さんは見た目で安心できるかどうかをしっかりチェックしています。
「このお店なら大丈夫そう」「ちょっと不安だからやめておこうかな」っていう判断は、実はブースの印象ひとつで大きく変わってしまうんです。
ここでは、販売場所そのものの清潔感やレイアウト、導線づくりのコツなど、衛生的に信頼される“見た目”のつくり方をお伝えしますね。
清潔感を伝えるには「お客さんの目線」を意識してみて
自分では気づきにくいけれど、お客さんの視線は常にカウンターの上や周辺を見ています。
だからこそ、テーブルの上には必要最低限のものだけを置いて、ごちゃつかないように整えておくのがポイントなんです。
特に、ザラメの袋や使用済みのペーパーなどが見える状態になっていると、それだけで「雑っぽい」と思われてしまうこともあります。
私はいつも、カラフルなテーブルクロスを敷いて、清潔な小物ケースに備品をまとめて入れておくようにしています。
「あ、このお店はちゃんとしてるな」と思ってもらえるだけで、手に取ってもらえる確率はぐんと上がりますよ。
汚れやすい場所を「最初に」決めておくと安心
実際に販売していると、どうしても**粉が飛ぶ場所や袋の出し入れで汚れがたまりやすい場所が出てきます。
**でも、これをあらかじめ予測して「ここはこまめに拭こう」と決めておくだけで、意外とストレスなく保てるんです。
わたしは、ザラメ容器の横や袋詰めスペースの手前など、人がよく触れる場所だけウェットティッシュを常備して、1時間ごとに軽く拭く習慣をつけています。
たったこれだけでも、ずいぶん清潔感は変わってくるんですよね。
子どもの手が届く位置はガードを考えておこう
思いがけないところでトラブルになるのが、子どもの“好奇心”による接触です。
わたあめ機に手を伸ばしたり、テーブルの下に潜り込んだりする場面、出店していると本当によくあります。
だからこそ、お客さんとの間には簡単な仕切りやガードを設けておくと安心です。
ビニールカーテンやロープ、場合によっては机を一段高くするだけでも効果があります。
「熱くないの?」と聞かれることもありますが、「機械が回っているので、近づかないようにお願いします」とやさしく伝えるだけで、しっかり配慮してくれる親御さんがほとんどですよ。
保健所に相談するときのコツ・よくある質問
「保健所ってなんか怖そう」「細かいこと聞いたら迷惑かな」なんて思って、聞きたいことがあってもつい後回しにしちゃう…。
わたしも最初はそうでした。
でも、実際に相談してみると、担当の方はとても親切で、「事前に聞いてくれて助かります」とまで言ってくれたんです。
それからは、出店の前に確認するのが習慣になりました。
わたあめのような簡易食品であっても、安全に販売するためには、「何がOKで何がNGなのか」を自分で把握しておくことがとても大切なんですね。
ここでは、保健所への相談がスムーズにいくためのコツや、よくある質問をまとめてお伝えします。
相談は「イベント名」を伝えて聞くとスムーズになるよ
保健所に相談するときは、「わたあめを出す予定なんですが」とだけ言っても、具体的なアドバイスがもらえないことがあります。
そんなときは、「〇月〇日に〇〇市で開催される△△イベントで出店予定です」というふうに、日時・場所・イベント名をセットで伝えるようにしてみてください。
すると、保健所の担当者もそのイベントに関する情報を持っていることが多く、
「このイベントでは届出はいりませんよ」
「簡易的な手洗い設備だけ用意してくださいね」
といった具体的な指示がもらえることがあります。
営業許可が不要でも「衛生的に」扱う責任はあるよ
わたあめは火を使わないし、その場で作ってすぐに渡すタイプの食品だから、「営業許可がいらないケース」も多いです。
ですが、それは「何をしてもいい」という意味ではありません。
むしろ、「届出不要な食品ほど、現場での衛生配慮が問われる」と思っておいた方が安心です。
保健所からも、
「正式な営業許可は不要ですが、できるだけ使い捨て手袋を使用してくださいね」
「食材の保管方法には気をつけてください」
といった形で、注意点をやさしく教えてもらえることが多いです。
よく聞かれる質問は事前に答えを用意しておこう
相談するときに、保健所の方からよく聞かれるのがこんな内容です。
「手洗い用の水や石けんは持って行きますか?」
「ザラメや色粉などの材料はどう保管しますか?」
「販売場所はテントの中ですか?日陰は確保できますか?」
「子どもが手を出せないような工夫はしていますか?」
こうした質問は、「ちゃんと考えてます!」とすぐに答えられるだけで、「この人は信頼できるな」と思ってもらえるポイントになります。
わたしはいつも、簡単なメモを作っておいて、それを見ながら質問に答えるようにしています。
ほんのちょっとの準備で、印象も不安もぐっと変わってきますよ。
まとめ|安全に気を配ることで“選ばれる出店者”になれるよ
わたあめって、見た目はふんわり軽くて、甘くて優しくて、どこか懐かしい味がしますよね。
でも、それを人に届けるってなったとき、ただふわふわ巻いて渡すだけじゃ済まされない現実があるんだなって、出店を経験して改めて感じました。
最初は「そこまで神経質にならなくても…」なんて思っていたけれど、
「風が吹いてザラメが舞い上がりそうになったり」
「子どもがお店の台に手をかけてきたり」
「雨上がりで地面がぬかるんでいたり」
そんな、想像してなかったことって本当にたくさん起こるんですよね。
でもね、ひとつひとつ対策を知っていくうちに、不思議と気持ちにも余裕が生まれていきました。
「これで大丈夫」と思える安心があると、お客さんへの笑顔にも自然と自信がにじんでくるんです。
保健所とのやりとりも最初はドキドキしたけど、きちんと準備して向き合えば、ちゃんと応援してくれる存在だってわかりましたしね。
衛生管理って、正直なところ見えにくいし、めんどくさいって感じる場面もあるかもしれません。
でも、誰かの口に入るものを自分の手で届けるというのは、やっぱり小さな責任であり、同時に大きな信頼をもらえる仕事なんですよね。
その信頼が「また買いたい」「誰かに教えたい」に変わっていく。
そんなふうに思えたとき、わたあめを巻く時間そのものが、すごく愛おしく感じられるようになりました。
この記事が、これから出店を考えているあなたにとって、少しでも背中を押せるような存在になっていたらうれしいです。
「きちんと衛生的に」「安心して食べてもらえるように」その気持ちがあるあなたなら、きっと大丈夫。
わたあめを通じて、たくさんの笑顔とつながっていけますように。