
「また折れた…」鉛筆を使うたびに芯がポキっと折れ、ついイライラしてしまう。
そんな経験、ありませんか?
私も子どもが宿題をしている姿を見ていて、短くなった鉛筆を見つめながら「もっと長持ちする方法があるのになぁ」とつぶやいたことがあります。
書いても書いても折れてしまうと、なんだか気持ちまで折れてしまうようで、勉強や仕事のモチベーションが下がってしまいますよね。
実は芯が折れる原因はひとつではなく、いくつもの要素が重なって起こるものなんです。
しかも、それぞれに簡単で今すぐできる解決策があるのです。
このページでは、そんなお悩みの原因をじっくり紐解きながら折れにくくするための鉛筆選びのポイントや、毎日のちょっとした使い方のコツまで丁寧にご紹介しますね。
読んでいただいたあとには、鉛筆を持つのが少し楽しみになれる、そんな記事になれば嬉しいです。
鉛筆の芯がすぐ折れる原因はこの3つ
芯の硬さや質が合っていない
安い鉛筆の中には、芯に不純物が混ざっていて均一性がなく、書いている途中でポロっと崩れやすいものがあります。
特に柔らかい芯は濃く書ける反面、折れやすさも増します。
「柔らかければいい」というわけではなく、自分の筆圧に合った硬さを選ぶことが大切です。
さらに、高級鉛筆の中には特殊な潤滑剤が練り込まれていて、滑らかさと耐久性を両立しているものもあります。
芯の素材の差でこれほどまでに書き心地と折れやすさが変わるのだと気付くと、選ぶ楽しみも増しますよ。
削り方や削り器の問題
一番多いのがこれ。
私自身、子どもの鉛筆削りの刃がサビているのに気づかず、「何本削っても折れる!」と嘆いているのを見たことがあります。
刃の劣化や斜めに差し込むクセ、力任せで削る…これらが芯のヒビ割れや中折れの原因になるのです。
特に小型のポケットシャープナーは刃が薄いので、繊細に扱わないと芯が欠けやすいですね。
加えて、電動削り器でも刃のメンテナンス不足や過剰な力が原因で芯が折れやすくなるので、定期的なメンテナンスが重要です。
削り器の性能は意外と大きな影響を与えるのです。
筆圧や持ち方が強すぎる
筆圧が強いと、柔らかい芯ではどうしても耐えられず折れてしまいます。
無意識に力が入る方は、意識して軽く書く練習をするか、硬めの芯を選ぶと良いでしょう。
私も試しに鉛筆を寝かせ気味にして持ってみたら、折れにくくなると同時に字もきれいになった気がします。
さらに、持ち方に工夫をして指先にかかる負担を分散させると、自然と筆圧も弱まり、芯の寿命が延びます。
こうした小さな意識の積み重ねが、芯折れのストレスを減らしてくれます。
折れにくい鉛筆の選び方
硬度(HB・Bなど)はどう選ぶ?
芯が硬いほど折れにくいのは確かです。
ただし硬すぎると書き味がカリカリして疲れやすいので、小学生なら4B~B、大人ならHB~Hが標準的です。
筆圧の強い人はH寄り、弱い人はB寄りと、少しずつ試しながら自分に合う硬度を見つけるのがおすすめです。
場合によっては用途に応じて何種類かの硬さを使い分けるのも効果的ですし、濃さや仕上がりの美しさの好みに合わせて選ぶと、書く時間がもっと楽しくなります。
芯の質が良いおすすめブランド
鉛筆の値段が高いものほど、芯がなめらかで均一に作られ、折れにくいです。
日本製の有名メーカー品を選ぶと安心。
私自身も、百均の鉛筆からブランド品に変えたときの書き心地と耐久性に驚きました。
価格差以上の価値を感じられるので、1本ずつでもいいので色々試してみると良いでしょう。
近年は海外ブランドでも高品質でユニークなデザインのものが多く、使い心地の違いを比べるのも楽しいものです。
シャープな先端を維持するポイント
削りすぎると芯が細く尖りすぎて、書き出しでポキっと折れがち。
少し丸みを残すと、耐久性も書きやすさもアップします。
書き進める中でこまめに先端を軽く調整するのもコツですし、使うたびに刃の状態を確認するだけでも仕上がりは大きく変わります。
書き心地のよさと芯の持ちのバランスを考えると、丸みのある芯先のほうが長時間の作業にも向いているでしょう。
今日からできる!折れ防止の使い方
正しい筆圧と持ち方を意識する
軽く書く練習をすると、字もきれいになり芯も長持ちします。
特に「書く時に息を止めてる」人は肩や手に力が入りやすいので、リラックスして呼吸するだけでも筆圧が軽くなります。
さらに、鉛筆を持つ角度を少し寝かせたり、指先の力を均等に分散させる練習をすることで、紙の摩擦が減り、芯の負担も軽くなります。
筆記時の姿勢や机の高さも見直すと、より理想的な筆圧に近づけます。
削り器の刃を定期的にチェックする
半年に一度は新しい削り器に替えるのが理想です。
刃が切れないと芯が裂け、折れやすくなるからです。
もし毎日多くの鉛筆を削るのであれば、より頻繁な点検や替刃も検討しましょう。
切れ味の良い削り器は芯先がなめらかになり、書き出し時の折れを防ぐことにもつながりますし、削りカスの処理も楽になります。
使わないときの保管の工夫
筆箱の中で転がって芯が割れるのを防ぐため、芯先を上にしてケースに入れたり、芯カバーを付けるのもおすすめです。
特に外出先で持ち運ぶときは、芯先がぶつからないように仕切り付きのペンケースを選ぶと安心です。
さらに、落としたり強い衝撃を受けると芯が中で折れることもあるので、しっかり保護できるケースやクッション性のあるペンポーチに入れるとより効果的です。
芯が折れてしまったときの応急処置
芯が中で折れて出てこない場合
中折れした芯は爪楊枝などでそっと押し出し、再度削り直しましょう。
強く突くとさらに割れるので注意が必要です。
奥まで折れている場合は、芯の破片を少しずつ取り除くようにし、先端を軽く叩いて内部の芯を浮かせる方法も有効です。
爪楊枝が入らない場合は細いピンセットやクリップを伸ばしたもので代用すると便利です。
焦らず慎重に作業するのがコツです。
急いでいるときの簡単な対応法
芯が折れても削って丸くしてすぐ使えます。
削りカスをよく払い落としてから書くと滑らかに書けますよ。
さらに、芯先が折れやすい状態であれば少し多めに削って芯の内部まで出し、先を軽く丸めると耐久性が増します。
短時間なら、多少芯が欠けていても書き始めに注意して力を入れすぎずに使うことで乗り切れます。
予備の鉛筆を持っておくと、より安心です。
おすすめの「折れにくい鉛筆」3選
低筆圧でも濃く書ける柔らか芯
Bや2Bは筆圧が弱い人にぴったり。
濃く書けるので力を入れずに済みます。
特にお子さんや高齢者など、手の力が弱い方にもおすすめです。
芯が柔らかいので紙にしっかりとした黒が残り、視認性も高く、勉強や手紙を書くのが楽しくなります。
デッサンなどでも重宝される柔らか芯の魅力をぜひ試してみてください。
高耐久タイプの硬め芯
図面や細かいメモにはHBや2Hが向いています。
私も仕事用にはHBを愛用中です。
硬い芯は細い線が引きやすく、長時間使っても芯が丸くなりにくいので、消耗が少ないのもメリットです。
紙に跡が残りにくいので、試験やコピー用紙での筆記にもぴったりです。
硬度の高い鉛筆は、力強く書きたい時にも頼れる一本です。
子ども向けの折れにくい練習用鉛筆
芯が太く折れにくい設計の練習用鉛筆は、初めて鉛筆を使うお子さんに最適です。
持ちやすい太軸のモデルや三角形の形状で正しい持ち方も身につきやすく、書くのが楽しくなるようです。
芯が折れにくいので親も安心ですし、鉛筆に興味を持ってもらえるきっかけにもなります。
小さな達成感が、学習意欲にもつながりますよ。
まとめ
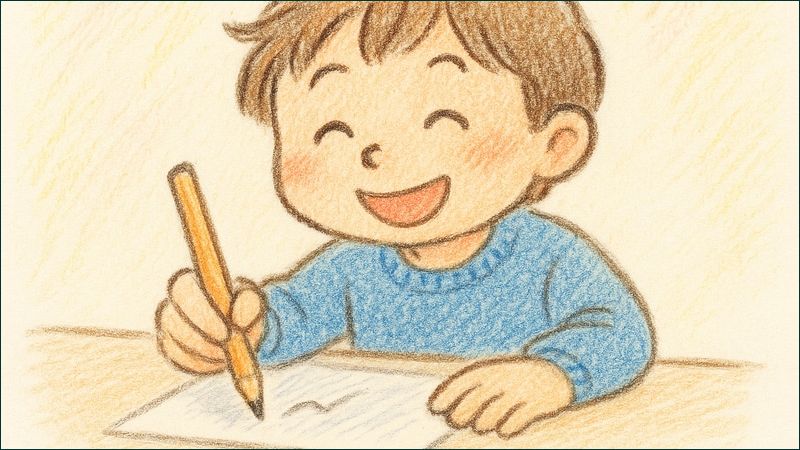
鉛筆の芯が折れる原因は、鉛筆の質や削り方、そして書き方のクセなど、意外といろいろあります。
けれども、少し視点を変えて見直しをするだけで劇的に折れにくくなりますし、書くことがもっと楽しく感じられるようになります。
私自身も、子どもと一緒にいくつもの鉛筆を試しながら、芯の硬さや削り方の工夫など少しずつコツを覚えていきました。
その過程で「こうすれば長持ちするんだ」という気づきが増えると、鉛筆選びそのものも楽しい時間に変わりました。
ぜひあなたも、この記事を参考にして、自分にぴったりの鉛筆と、より快適に書ける使い方を見つけてみてください。
きっとストレスのない筆記が実現し、書くことが、もっと心地よく、もっとワクワクする時間になりますように。