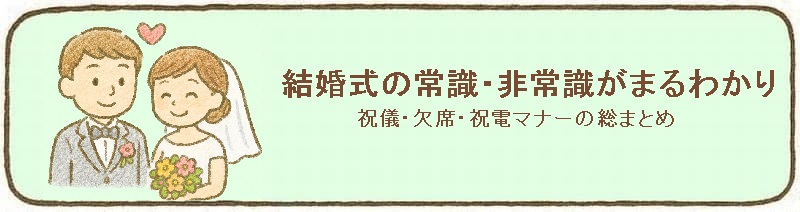結婚式の招待状が届くと、嬉しさとともに少しだけ緊張するような、そんな感情がわいてきませんか?
とくに、どうしても都合がつかず欠席せざるを得ない場合は、さらに複雑な気持ちになる方も多いはずです。
「出られないなんて申し訳ないな」
「欠席でもご祝儀は必要かな?」
「送らないのは非常識だと思われる?」
そんなふうに、正解のない“人付き合いのマナー”に頭を悩ませてしまう瞬間は、誰にでもあるものです。
しかもご祝儀には“お金”が関わるので、ちょっと間違えると非常識に思われないか、相手との関係が気まずくならないかと、気を揉んでしまうのも無理はありません。
実際、ネットで調べても「ご祝儀は渡すべき」「いや、関係が薄ければ不要」など情報はバラバラで、かえって混乱してしまったという声もよく耳にします。
でも本当に大切なのは「常識」よりも、「自分と相手との関係性」なんですよね。
この記事では、ご祝儀を渡すか迷ったときの判断の目安や、気持ちを丁寧に伝える方法について、読者の不安に寄り添いながら一緒に考えていきます。
あなたの中で、モヤモヤがすっと晴れるようなヒントが見つかるように願いを込めて、お届けしますね。
仲の良い友人なら、欠席してもご祝儀を贈るのが自然な思いやり
人生の中で、何度も会ったり長く付き合いが続いていた友人が結婚すると聞いた時って、胸がじんわり温かくなりますよね。
仕事や子育てで忙しくなって、しばらく会えていなかったとしても、「あの子がついに結婚か…」と、心の中にふわっとお祝いの気持ちが湧いてくる。
それが本当に仲の良かった友人への感情だと思うんです。
そんな友人の晴れ舞台に、もしどうしても出席できない事情があったとしたら。
やっぱり何かしら“気持ちをカタチにして伝える”ことが、お互いの今後の関係にとっても自然で心地よいんじゃないかなと私は思っています。
「気持ちだけじゃ足りないかも…」と思ったときにできること
出席できないときでも、ご祝儀を贈るという行為には、「あなたの結婚を心から祝福しているよ」という想いを形にして渡す、という意味合いがあります。
ただのお金ではなくて、関係性の中で生まれる優しさの表現なんです。
私自身も、学生時代からの友人が地方で結婚式を挙げることになってどうしても行けなかったとき、1万円を包んでお祝いの手紙を添えて郵送しました。
すると、あとから「本当にありがとう。
気にかけてくれて嬉しかった」と連絡がきて、泣きそうになるくらい嬉しかったのを覚えています。
もし金額で迷うなら、友人としてのご祝儀の“欠席時の相場”はだいたい1万円が目安。
これはあくまでマナーの範囲内ですが、何より大切なのは金額よりも「あなたのことを想っているよ」という心のこもった姿勢です。
ご祝儀のかわりにプレゼントという選択肢も
最近では現金ではなく、相手のライフスタイルに合ったプレゼントを贈る人も増えてきています。
たとえば、新居で使えるちょっといいキッチングッズや、ペアカップ、癒やし系のアロマグッズなど。
「あなたの新しい生活があたたかいものでありますように」という願いを込めて選ぶと、相手もきっと喜んでくれます。
私の友人は、欠席した親友のためにちょっと高級なブランケットと手書きのメッセージカードを贈ったそうです。
そしたら「こっちのほうが嬉しかった」と言われたんですって。
ああ、そういう関係って素敵だなって思いました。
もちろん、どんなものを贈ればいいか迷ってしまう場合は、無理せず現金でOK。
それでも十分にお祝いの気持ちは伝わります。
ご祝儀を渡すことで、これからの関係もあたたかく
結婚式って、ただのお祝いの場ではなくて、その人の人生の新しいスタートをみんなで後押しするような時間なんですよね。
その瞬間に直接立ち会えなくても、少しでも力になりたい、笑顔を応援したいという気持ちがあるなら、それはご祝儀という形にしても全然おかしくないんです。
それに、ご祝儀をきちんと渡しておくことで、今後も友人関係が気まずくならず、自然な形でつながっていけます。
「あの時、何もしてくれなかったな…」なんて変な誤解を生まずに済むのも、大人同士の付き合いとして大事なポイントかもしれません。
「お金」よりも大切なのは、祝う気持ちの伝え方
ご祝儀って、どうしても“金額”に注目しがちだけど、実は本当に大切なのは「心の込め方」なんですよね。
LINEひとつ、メッセージカード1枚で、相手の心にぽっと灯がともるようなことだってあるんです。
だからもしあなたが、
「式に行けなくて本当に残念」
「でも心からお祝いしたい」
と感じているなら、ぜひそれを素直に伝えてみてください。
お金や品物よりも、たった一言の気持ちが相手の心にずっと残ることもあるから。
正直、ちょっと疎遠…そんな相手には無理しなくてOK
「え、なんで私が?」戸惑いの招待状に出くわしたら
社会人になってしばらく経つと、ふと届く結婚式の招待状に、思わず首をかしげることってありますよね。
「あれ?最後に話したの、いつだっけ?」
「連絡先すら知らないのに…」
そんな相手から届いた招待状に、正直、戸惑いを隠せなかった経験、ありませんか?
私もかつて、大学で同じサークルにいたけれど、ほとんど会話をしたこともなかった人から突然招待状が届いたことがありました。
「どうやらグループ全員に声をかけたらしい」と後から聞いて、少しホッとしたのを覚えています。
でもそのとき、同時にすごく悩んだんです。
欠席するつもりだったけれど、ご祝儀だけは渡した方がいいのかな…って。
でも、結論から言うと「無理に渡す必要はない」です。
“常識”よりも“関係性”。今の距離感を冷静に見て
世間の「結婚式マナー」は、もちろん参考にはなります。
でも、それがすべてのケースに当てはまるわけじゃありません。
とくにご祝儀は、相手とのつながりの深さによって意味合いが変わってくるもの。
- もう何年も会っていない、SNSですら交流がない。
- 共通の友人もいない。
むしろ形式的な贈り物は、かえって相手も気を遣わせてしまう可能性だってあります。
「呼ばれたからには…」と律儀に対応する優しさも素敵ですが、自分の気持ちにウソをつく必要はありません。
誰にでも、ちょうどいい“人付き合いの距離”ってありますから。
「義理ご祝儀」をしないと気まずい…そんなときの選択肢
とはいえ、同窓会などで顔を合わせる機会がありそうな相手の場合、「完全スルーはちょっと気まずいかも」と不安になることもありますよね。
そんなときは、1万円のご祝儀までしなくても、小さな雑貨や日用品を郵送したり、ちょっとしたメッセージカードを添えて気持ちを伝えるだけでも十分です。
最近は500円~2,000円程度で、シンプルで上品なギフトもたくさんあります。
あるいは、「今度会ったらお祝いにご飯でもおごるね」とさりげなく伝えておくのも、大人らしいスマートな対応。
形式よりも“今の関係性に合ったやり方”を選ぶことが、結果的に自分も相手も心地よくいられるコツなのかもしれません。
あなたが気まずさを感じない、が一番の判断軸
こういったケースで一番大事なのは、「あとで自分が後悔しないかどうか」です。
「あの時スルーしたのがずっと引っかかってる」
「会った時に気まずくて避けてしまった」
そういう小さな心のざらつきって、じわじわ残ってしまうもの。
逆に、まったく未練も心配もないなら、何もしないという選択だってもちろんOK。
不必要な金銭的な負担を避けることは、自分の生活を守るうえでも大切な判断です。
昔は仲良しだったけど今は疎遠…この“微妙なライン”の判断基準
あの頃は親友、でも今は連絡もしていない
学生時代って、毎日のように顔を合わせて、自然と深く仲良くなれる時間がありますよね。
部活帰りに寄り道して語り合った放課後や、くだらない話で何時間も笑い転げたあの頃。
でも、卒業して数年たつと、自然と距離ができてしまうこともあります。
お互い就職した場所が違えば、ライフスタイルも大きく変わっていく。
あんなに仲が良かったのに、気づけば「最後に話したの、いつだったっけ…?」と指折り数えるような関係になってしまうこともあるんですよね。
そんな相手から、ある日ぽんと結婚式の招待状が届いたら…
少しうれしい、だけど戸惑う気持ち。
これって、きっと多くの人が経験している“絶妙に悩ましい瞬間”だと思います。
今の気持ちと、これからの関係性を静かに見つめてみて
この「昔は仲良しだったけど今は疎遠」な相手に対して、ご祝儀をどうするか…
答えは一つじゃありません。
でも大切なのは、「相手が今でも自分を友人として思ってくれているかどうか」、そして「自分自身がその人をどう思っているか」という2つの気持ちです。
相手からすると、「久しぶりだけどお祝いしてもらいたい」と素直に思っているかもしれません。
実際、当時の楽しかった思い出が色濃く残っていると、少し距離があっても招待したくなる気持ちはよくわかります。
もしあなたの中に「行けないけど、おめでとうの気持ちは届けたい」と感じるものがあるなら、それは十分にご祝儀を贈る理由になります。
お金でなくても構いません。
手紙やちょっとした贈り物、メッセージひとつでも、あの頃のあたたかい記憶にそっと触れるようなやさしい気持ちが伝わります。
思い出を汚したくないなら、少しだけ丁寧にしておこう
私の友人は、高校時代にとても仲の良かったグループの子から、7年ぶりに招待状が届いたそうです。
実際には全然会っていなかったけれど、「あの頃の自分を大事にしてくれたんだな」と感じて、欠席の連絡とともにご祝儀1万円を送ったんです。
そしたら後日、その子からとても丁寧なお礼のメッセージが届いて、2人はまた少しやり取りをするようになったとか。
関係が戻るかどうかはわからないけれど、「あの子、ちゃんとしてたな」と思ってもらえるって、すごく素敵なことだと思うんです。
思い出の中にある自分の姿を、大人になった今もきれいなままで残しておく。
そういう意味でも、心に引っかかる相手には少し丁寧な対応をしておくと、後悔が残りません。
無理して祝う必要はないけど、線引きは自分の心で決める
もちろん、当時は仲良かったとしても、今となってはお互いの近況も知らない、もう会う予定もない。
そんな場合は無理して祝う必要はありません。
むしろ、“今の関係”を大切にするなら、何もしない選択だってアリなんです。
このあたりの線引きは本当に微妙で、ネットにある「正しいマナー」では測れない部分。
だからこそ、自分自身の気持ちを見つめることが大切です。
- 「ちょっと気がかりだな」と感じるなら、できる範囲でやさしい気遣いを。
- 「今はもう他人同然だ」と割り切れるなら、潔くスルーでも構わない。
大切なのは、あなた自身が納得できる選択をすること。
そしてそれが、後々の自分の気持ちを守ってくれるということです。
結婚式に欠席する時のご祝儀マナー:どう渡す?どう伝える?
会えないとき、ご祝儀はどうやって渡すのが正解?
欠席を決めたあと、悩ましいのが「ご祝儀の渡し方」ですよね。
とくに相手が遠方に住んでいる場合や、今すぐに直接会う予定がないとき、「渡したい気持ちはあるけど、どうすれば失礼にならない?」と悩む人は多いと思います。
基本的なマナーとしては、ご祝儀を渡すならなるべく結婚式の1週間前までに届けるのが理想です。
これは、相手が披露宴の準備などで忙しい中、金銭的なことを早めに把握しておけるようにという配慮でもあります。
現金は「現金書留」で送るのが正しいマナー
現金をご祝儀として郵送する場合は、必ず「現金書留」を使いましょう。
これは郵便局で扱っている、現金専用の封筒で送る方法です。
普通郵便で現金を送るのはNGなので注意が必要です。
手順としては、まずご祝儀袋に1万円などのお祝い金を入れて、そのまま現金書留の専用封筒に収めます。
そして郵便局の窓口から手続きをすればOK。
この時、ご祝儀袋にはきちんと表書き(寿や御結婚御祝)と名前を書き、内袋にも金額と住所・氏名を記載しておくのが正式です。
小さな手間ですが、これを丁寧にしておくことで“しっかり祝う気持ち”が相手にも伝わります。
「会えないから送る」だけじゃない、気持ちの伝え方
たとえ現金で送るとしても、それだけではどうしても“無機質”になってしまいがち。
だからこそ、メッセージカードを添えるのがとても大切なんです。
手書きの一言でもいいんです。
「直接お祝いできず残念だけど、心から幸せを願っています」
そんな言葉があるだけで、ご祝儀が“ただの金銭”ではなく“心のこもった贈り物”になります。
私は以前、欠席する友人にメッセージカードを同封してご祝儀を送ったところ、式後に「あなたの手紙が一番心に残った」と言われて泣きそうになったことがあります。
人の心って、ほんの一言であたたかくなるものなんですよね。
LINEやメール、電話でもいいから「言葉で伝える」こと
もし手紙が苦手だったり時間がない場合でも、LINEやメール、または電話でもかまいません。
欠席を伝えると同時に、
「ご結婚、本当におめでとう」
「直接言えずごめんね」
とひと言添えるだけで、相手の受け取り方はまったく違ってきます。
人間関係における“誤解”や“気まずさ”は心の健康に大きく関わってきます。
だからこそ、言葉を添えることはただのマナーではなく、「相手との信頼関係を守る」大切なケアでもあるんです。
もちろん、気心の知れた相手なら「今度ご飯行こうね!そのとき改めてお祝いさせて!」という言い方でもOK。
大事なのは形式ではなく、「ちゃんとあなたのことを気にかけているよ」という気持ちが伝わるかどうかです。
まとめ
結婚式に欠席する時のご祝儀は、「常識」と「気持ち」のちょうど真ん中を探す、まさに“心のバランス感覚”が問われる場面かもしれません。
ネットやマナー本には形式的な答えが書いてあるけれど、それがすべての人に当てはまるとは限らないんですよね。
大切なのは、相手との関係性をふまえて、自分の中で納得できる選択ができるかどうか。
それが何よりも安心につながります。
無理してご祝儀を渡す必要はないけれど、「あの人になら、やっぱり祝いたい」と思う気持ちがあるなら、金額や方法にとらわれず、あなたらしい形でお祝いを伝えてみてください。
それが現金でも、手紙でも、小さな贈り物でも、どんな方法であっても心は伝わるものです。
そして、「何もしない」と決めた場合でも、それが思いやりのない行動になるわけではありません。
むしろ、お互いの関係性を尊重した大人の判断だと思います。
人付き合いって目に見えないものだからこそ、余計に迷ったり不安になったりするけれど、この記事が少しでもあなたの気持ちを軽くするきっかけになったら嬉しいです。