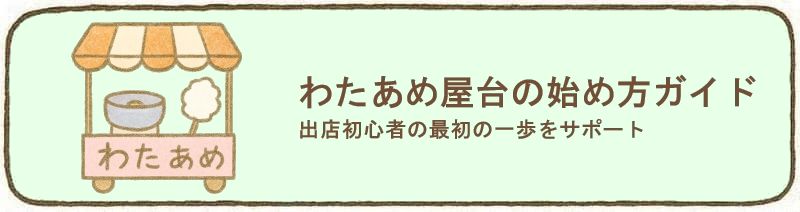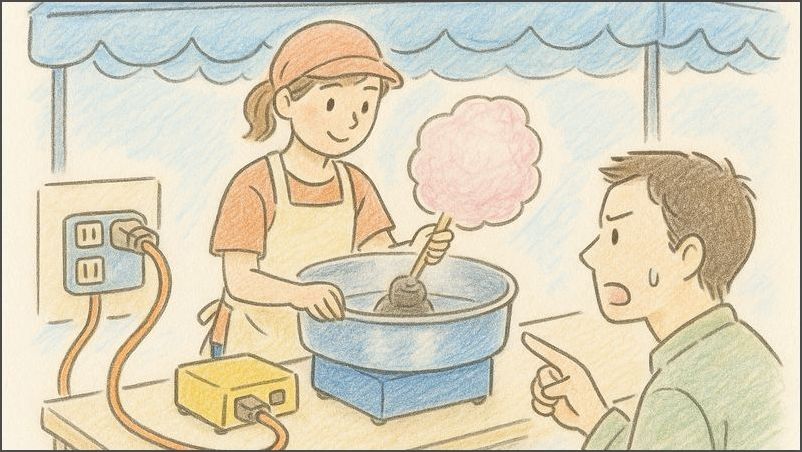
「わたあめ屋さんって楽しそう!」そう思って軽い気持ちで出店を決めたのに、いざ準備に取りかかってみると、最初につまずいたのは機械の使い方でも材料の仕入れでもなく。
まさかの“電源”でした。
どの延長コードを使えばいいのか、イベント会場に電源はあるのか、雨が降ったらどうなるのか……
考えれば考えるほど不安ばかりが募っていって、正直なところ「出店、やめたほうがいいかも」と思った瞬間もありました。
実際、私が初めて出店したときは、家庭用の細い延長コードを使ってしまって、コードが熱を持って焦げたような匂いがしてきたときには心臓がバクバクしました。
あのとき冷や汗をかきながら慌てて電源を切った経験は、今でも忘れられません。
わたあめの出店って、見た目のかわいさや味ばかりに目がいきがちですが、安心して販売するためには電源や設営まわりの安全対策が本当に大切なんですよね。
この記事では、そうした私自身の失敗や学びをふまえて、初めての出店でも安心して準備ができるように、電源・延長コード・屋外設営に関するポイントをひとつずつ丁寧にお伝えしていきます。
これを読んでくれているあなたには、私と同じ失敗でヒヤッとしてほしくないから。
イベント出店では「電源」が成功のカギ
わたあめ機は“電気”がなければ動かない
わたあめ屋台と聞くと、まず浮かぶのはカラフルでふわふわな見た目や、甘くてやさしい香りかもしれません。
でもその裏側には、しっかりとした「電気の準備」が必要不可欠なんですよね。
実際、わたあめ機は熱を発生させてザラメを溶かし、空気の力で繊維状に飛ばすという構造なので、意外と電力を食います。
可愛くて軽そうに見えても、裏ではヒーターとモーターがフル稼働。
だからこそ「電源」が確保できないと、そもそも出店が成り立たないんです。
出店場所によって「電源の有無」はまったく違う
出店する場所によって、電源の提供状況は大きく異なります。
商業施設や自治体主催の大規模イベントでは、テントごとにコンセントが用意されていることもあります。
でも、個人経営のマルシェや地元のお祭りでは「電源は自前で持参してください」と言われることも珍しくありません。
私もかつて、電源があると思い込んで出店の申し込みをしたら「現地には何もないですよ」と言われて青ざめたことがあります。
事前に主催者さんへ「電源は使えますか?延長コードはどれくらい必要ですか?」と確認しておくことが、トラブルを防ぐ大事な一歩です。
電源が足りなくて泣いた…実体験から学んだこと
はじめて出店したイベントでは、同じ区画に2店舗が割り当てられていて、私はそのうちのひとつでした。
主催者の方から「2軒で電源をシェアしてもらえますか?」と言われて、「まあ大丈夫だろう」と思っていたんですが。
でもふたを開けてみると、隣の方も高出力の調理器具を使っていて、ブレーカーが何度も落ちるという大惨事に…。
お客さんの列ができていたのに、わたあめ機が動かず頭が真っ白になりました。
自分だけの電源が確保できるか、容量は足りているかを必ず確認しておかないと、どんなに準備しても水の泡になってしまいます。
電力容量の見方と基礎知識は絶対に知っておこう
わたあめ機に限らず、出店用の調理機器は1000Wを超えるものが多くあります。
一般家庭の延長コードの多くは10A(アンペア)までしか対応していないことが多いため、使い方を誤ると過熱やショートの原因にもなりかねません。
ワット数(W)とアンペア数(A)の関係式をざっくり覚えておくと便利で、目安としては「W ÷ 100(電圧)=A」で計算できます。
つまり、1200Wの機械なら12A必要だということ。
出店で使う延長コードや電源は、それにしっかり対応したものを選ぶ必要があります。
安心して使える電源確保が、売上にも直結する
電源トラブルがあると、お客さんを待たせたり、最悪の場合販売が中止になることもありますよね。
逆に、電源の心配がない状態だと、気持ちにも余裕が生まれて、お客さんとのやり取りも自然と楽しくなります。
準備段階で電源環境をしっかり整えておくことは、結果的に売上やリピート率にもつながっていく大切な“土台”なんだと、私自身何度も痛感してきました。
延長コード選びは「耐久性」と「電流容量」で決まる
細いコードで大丈夫?その油断が危険を呼ぶ
正直、私も最初は「延長コードなんて家にあるものでいいでしょ」と思っていたんです。
どこにでも売ってるし、家庭で普通に使えているんだから問題ないはず、って。
でも、実際に出店当日、家庭用の細いコードをわたあめ機につないでみたら、途中からコードが熱くなってきて、焦げたような匂いがしてきたんです。
心の中は一気にパニック。
「もし火花でも出たらどうしよう」「お客さんの前で火事になったら…」そんな不安が頭をよぎりました。
あとで調べてみたら、そのコードは10Aまでの対応で、私のわたあめ機は1200W。
完全にキャパオーバーだったんです。
安全のために見るべき「A(アンペア)」と「W(ワット)」
延長コードのパッケージや本体には「15Aまで」や「1500W対応」といった表示があります。
これはつまり、1500Wまでの電気製品なら安全に使えるという意味。
でも、同時に複数の機械をつなぐと、それだけであっという間に容量を超えてしまうこともあるんですよね。
例えば、わたあめ機だけで1200W、照明や扇風機を足すともう限界。
そのあたりを甘く見てしまうと、発熱やショートの原因になります。
必ず自分が使う機材の合計W数を確認して、それに見合ったコードを準備するようにしてくださいね。
屋外イベントには「防水・耐熱タイプ」が安心
晴れていれば気持ちのいい屋外イベントも、急に曇って雨が降り出すなんてこと、よくありますよね。
私は一度、テントの端から延びたコードが雨水を含んだ地面に触れてしまって、コードの根本がびしょ濡れになっていたことがあります。
幸い何事もありませんでしたが、もし接続部分に水が入っていたら…と考えるとゾッとします。
それ以来、私が必ず使うようにしているのが「防水キャップ付きの屋外用延長コード」です。
コード自体が分厚くて丈夫なのも心強いし、キャップがあるおかげで急な雨でも安心できます。
安さより「信頼性」を選ぶのが大事
イベント準備って、何かと出費がかさみますよね。
だからつい、安いコードで済ませたくなる気持ちもすごくわかります。
でも、たった数百円の差でトラブルになるくらいなら、最初から
「屋外使用OK」
「高耐久タイプ」
「大手メーカー製」
のしっかりしたコードを選ぶ方が絶対にいいです。
私は今でも、初出店のときに焦ってネットで買った安い延長コードを見るたびに、あのときのヒヤッとした瞬間を思い出してしまいます。
おすすめは「3口+防水キャップ+太めコード」
私が愛用しているのは、3口タイプで防水キャップ付き、そして太めでしっかりした屋外対応の延長コードです。
3口あると照明やスマホ充電もできて便利ですし、太さがあると安心感が違います。
荷物にはなるけれど、「安全」と「安心」を一緒に運んでいると思えば、重さも気にならないですよね。
屋外設営で必ず確認したい安全ポイント
テント内での設置位置がトラブルを左右する
屋外イベントって、思っている以上に人の流れが読みにくいものなんですよね。
テントの中で機材をどこに置くか、それだけでも動線がガラッと変わってしまいます。
私は以前、出店ブースの中央にわたあめ機を置いてしまったことで、延長コードがテントの出入口を横切る形になり、通るたびに足を引っかけそうになってヒヤヒヤしました。
後から「テントの隅に沿わせるようにコードを回していれば、こんなに気を使わずに済んだのに…」と反省したことがあります。
お客さんも、自分も、安全に動ける空間配置って本当に大事なんです。
コードの配線ルートは「踏まれない・引っかからない」が鉄則
人通りの多い場所では、延長コードはあっという間にトラブルの元になります。
子どもがうっかりつまずいたり、ベビーカーの車輪に絡まったり、想像もしなかった事態が起こるんですよね。
私は最近では、コードを地面に這わせるときには必ず「コードカバー」や「養生テープ」で固定するようにしています。
それだけでも見た目がすっきりするし、安全性が全然違います。
目立つカラーのテープを使えば注意喚起にもなって、一石二鳥ですよ。
雨・湿気のリスクは「高さ」と「位置取り」で減らせる
コードの接続部分が地面に近い場所にあると、急な雨で水たまりになったときに危険です。
防水仕様のコードを使っていたとしても、接続部分が水に浸れば感電やショートの恐れがあります。
私の出店仲間は、コードのつなぎ目をプラスチックケースの中に入れて、さらにブロックや台の上に設置するという方法をとっていました。
これがかなり賢くて、見た目も整っているし、何より安心感がありました。
それ以来、私もコードは「高く、目立たず、安全に」を意識して配置するようにしています。
風対策も忘れずに!コードと機材の固定が命
風が強い日は、テントの幕がバタバタするだけじゃなく、延長コードが浮いたり絡まったりしてしまうことがあります。
最悪、コードが引っ張られてわたあめ機ごとガタンと倒れてしまうことも…。
そんな事態を防ぐために、私はコードをテントの骨組みに結束バンドで固定したり、地面にはペグとロープで補強しておくようにしています。
ちょっとした手間だけど、そのおかげで一度も転倒事故を起こさずに済んでいます。
風の日は「コードも風に吹かれる」という意識を持っておくと、本当に安心です。
「見えない危険」を想像する力が出店トラブルを防ぐ
屋外の出店って、天気や地形、人の流れなど、想定外のことがたくさん起こります。
でもだからこそ、
「ここにコードを置いたら誰かつまずくかも」
「雨が降ったらここが危ないかも」
といった“見えない危険”を先にイメージしておくことが、結果的にトラブルを減らすことにつながるんですよね。
私も何度も出店を重ねていくうちに、ようやくそういう「想像力」が身についてきたなと感じています。
当日トラブルを防ぐためのチェックリスト
設営が終わったら「通電テスト」を忘れずに
わたあめ機をセットして、テーブルも飾って、のぼりも立てて…よし!と安心してしまう気持ち、すごくわかります。
でも、設営が終わったその瞬間こそが、電源まわりのチェックをすべきタイミングなんですよね。
私がいつもやっているのは、まず延長コードをつなぎ、わたあめ機のスイッチを入れて、しばらく様子を見ること。
このときにコードが熱を持っていないか、機械が異音を立てていないかをじっくり確認します。
もし何かおかしいと感じたら、思い切って使用をやめて予備のコードに替える勇気も必要です。
準備段階で問題を見つけられれば、開店後の慌てふためきは避けられますよ。
延長コードが熱くなる原因とそのサイン
コードが熱を持つのは、容量オーバーか接触不良のサイン。
私も一度、開店してから30分ほど経った頃に「なんか焦げくさい…?」と違和感を覚えて、コードを触ってみたらアッツアツ。
ヒヤリとしながら電源を切ったことがあります。
そのときはコードの耐久性が足りなかったのが原因でした。
使うコードの太さ、対応ワット数、巻き取り式かどうか(熱がこもる)など、すべてが影響します。
表面がほんのり温かい程度なら許容範囲ですが、触って熱いと感じたら即交換。
それが事故を防ぐ一番の早道です。
予備のコード・機材を「使わなくても持っていく」
使う予定はなくても、私は必ず1本は予備の延長コードを持っていくようにしています。
というのも、何かあったときに買いに走る時間なんて、イベント中には絶対ありませんし、近くに電気屋さんがあるとも限りませんからね。
さらに、小型の電圧チェッカーやテスターもバッグに入れておくと、「電気が来てるか来てないか」の判断が一瞬でできます。
こういうちょっとした備えが、出店者としての自信にもつながるんですよ。
主催者との「連絡手段」は紙でも控えておく
出店中に何かトラブルが起きたとき、すぐに主催者さんに連絡が取れるかどうかって、実はものすごく重要なんです。
私は過去に、スマホの充電が切れて主催者の連絡先が確認できず、近くのスタッフさんをあちこち探して大変な思いをしたことがありました。
それ以来、スマホとは別に、連絡先を紙にメモしてポーチに入れておくようにしています。
地味だけど、すごく助かるんです。
心の余裕が「想定外」を味方に変えてくれる
イベント出店って、想定外の連続です。
人が多すぎて回線がつながらない、雨が急に降ってきた、隣の屋台の音楽が大きすぎて声が通らない…。
でも、準備が万全にできていれば、そういうトラブルにも冷静に対応できるんですよね。
「まあ、これも出店の醍醐味か~!」と笑えるくらいの心の余裕を持てるかどうかは、事前の準備で決まるんだなと毎回感じています。
まとめ:電源対策は「準備8割・安心2割」
わたあめ屋台の出店って、見た目のかわいさや味のバリエーションに目が行きがちだけど、実は裏側にある「電源と安全」の準備こそが成功のカギなんですよね。
私自身、初めて出店したときに延長コードの選び方を間違えて、ヒヤッとする経験をしたことで痛感しました。
わたあめ機は小さく見えても電力をしっかり使う機械。
だからこそ、適した延長コードを選ぶ、屋外でも安全に設営する、当日のトラブルに備えておく…こういった一つひとつの工程が、当日の安心とお客さんの笑顔につながっていくんだと思います。
特に屋外イベントでは天候や人の流れなど、不確定なことが多いからこそ、電源の準備を怠らないことが出店者としての信頼にもなります。
売上を上げたい、楽しく安全にお店を出したいと思うなら、地味だけどこの「電源まわり」にしっかり時間と気持ちをかけることを、私は強くおすすめしたいです。