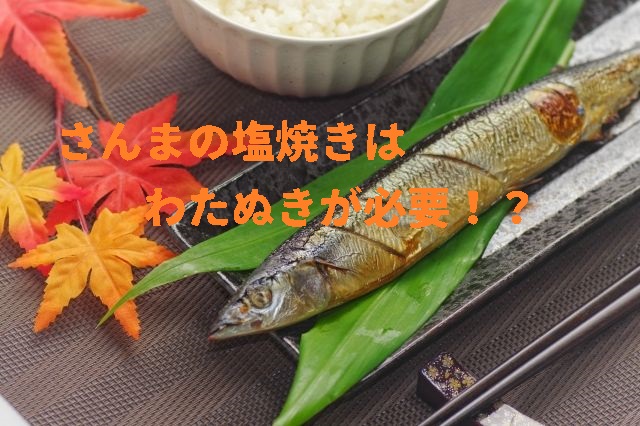
魚って、種類によって旬の時期がいろいろとありますよね!
どれも自宅で調理しても美味しく食べることができます。
我が家でも、定期的に魚の塩焼きや煮つけが食べたくなるので、作ります。
でも、その度に面倒だなと思うのが下処理です!
主婦になると、1秒でも時短したい!と思いがちですよね。
事前準備とか下処理って面倒!と思っている方は多いのではないでしょうか?
今回は、そんな魚の塩焼きの中でも、さんまについてお話をしていきます。
秋になるとなんとなく、さんまの塩焼きが食べたくなりますよね!
そんなさんまの塩焼きも美味しく食べるには、わたぬきをすることがおすすめです!
自宅で簡単にできるわたぬきの方法を、ご紹介していきますね。
秋はさんまの塩焼きをよく作る!という方は、是非最後までご覧になって下さい。
さんまの内臓の取り方で頭を残す方法を分かりやすく解説
さんまの内蔵は、食べられないわけではありません!
下処理が面倒だな…と思うと、そのまま焼いてしまうご家庭も多いですよね。
さんまの内蔵には、ビタミンDとかAが豊富に含まれています。
そのため、鮮度の高いものであればそのまま調理してしまっても良い場合もありますよ。
でもそのまま焼くと、やはり気になるのが内蔵の苦味です。
大人であれば、多少の苦味なら旨味に感じる!という方もいるかもしれません。
ただ、子供が食べるとなると話は別です!
苦味があると苦手意識を持ってしまうこともよくありますよね。
主婦だとなるべく時短したい!と思ってしまうものです。
でも家族みんなで美味しく食べるなら、やはり内蔵を取り除くのは必須かもしれません!
さんまの内蔵取りで頭を残す方法!
さんまの内蔵取りって、いろいろなやり方がありますよね。
よく調べているときに見かけるのが、頭を切り落としてしまう方法です。
簡単にできることもありますが、これだとさんま感がなくなりますよね!
どうしても、頭がついていた方が、美味しく感じるような気がしてしまいます。
そこで、頭を残す内蔵取りの方法をご紹介しますね。
さんまの頭を残す内臓取りの手順①洗って塩をふる
まずは、さんまを洗って両面に塩をふりましょう。
この状態で15分ほど放置します。
さんまの頭を残す内臓取りの手順②きれいに洗い流す
そのあと一旦きれいに洗い流します!
こうすることで、臭みも取れるので必須項目です。
さんまの頭を残す内臓取りの手順③エラに切り込みを入れる
その後、さんまのエラに切り込みを入れます。
骨を切り落とさないように、骨にあたるまで包丁を入れましょう!
この次に、さんまの頭からエラまでの距離と同じぐらいの長さ分、尾びれから測ってください。
その部分にも切り込みを入れます!
頭の方と尾びれの方で、合計2箇所切り込みを入れるということですね。
さんまの頭を残す内臓取りの手順④お尻からエラまで指圧で押す
さんまのお尻部分からエラの切れ込みまで、指圧で押していきましょう!
そうすると、内臓が動きやすくなっていきます。
さんまの頭を残す内臓取りの手順⑤尾びれの切り込みから水を入れる
そして、尾びれの方に入れた切れ込みから、優しく水を入れていきます。
このとき、蛇口からそのまま入れてOKなのですが、水圧には気を付けましょう!
内蔵が頭の方からでてきたら、菜箸などで取り除いてくださいね。
さんまの頭を残す内臓取りの手順⑥残っている内臓を菜箸で取る
最後に全体的に菜箸を入れて、残っている内蔵部分をしっかり取り除けばOKです!
文章での説明だと、ちょっと難しいかもしれません。
なんとなく雰囲気は伝わりましたでしょうか?
まとめると、切り込みを2箇所いれて、指圧をして、水で押し流す!という方法です。
我が家でもこの方法をよく使っていますが、慣れれば簡単ですよ!
是非試してみて下さいね。
さんまの塩焼きの下処理の仕方は?少しの手間で美味しさアップ
さんまの塩焼きは、先ほどご紹介をしたような下処理が大切です!
基本は、まず全体的に塩を振って15分前後で洗い流します。
そのあとでてきた臭みなどをキッチンペーパーで拭き取りましょう。
わたぬきをしない場合は、この状態で塩をふって焼いてしまえばOKです!
わたぬきをしたいときは、先ほどの手順を是非参考にしてみてくださいね。
そしてここでは焼く前に、更にひと手間加える方法をご紹介していきます!
この方法を使うと、さらに臭みが抜けて美味しく仕上がりますよ。
さんまの臭みを抜く手順①水気を拭いて料理酒をかける
さんまの下処理が終わったら水気を拭き取って料理酒をかけます。
トレイなどに置いた状態で、ポリ袋などに入れると良いですね!
その状態で、冷蔵庫に一晩保存をしてください。
さんまの臭みを抜く手順②キッチンペーパーに包んで冷蔵庫で寝かせる
翌日になると、水分がたくさん出ています!
これをキッチンペーパーなどで包んだら、更に冷蔵庫に入れて下さい。
最低でも30分は入れておくとよいですね。
さんまの臭みを抜く手順③塩をふって焼く
しっかりと冷蔵庫で寝かせたら、あとは塩をたくさんふって焼いてみて下さい!
一晩寝かさないといけなかったり、翌日も更に冷蔵庫で寝かせたり。
これだけ見ると、ちょっと手間には感じますよね。
でも、普通に下処理をするよりも、臭みを取り除くことができます!
料理酒って、それぐらい万能な調味料ですよね。
大人であれば、普通の下処理でOKかもしれません。
でも焼き魚が苦手な子供であれば、このひと手間がおすすめですよ。
さんまの塩焼きはわたぬきが必要?のまとめ

秋になると食べたくなる!という人が多いさんま。
でも魚は、自宅で調理するのは大変なイメージですよね。
大変なのに美味しくできなかったら、手間がかかるだけ損!と思う方もいるかもしれません。
さんまは、鮮度が高ければそのまま調理してもOKです。
でも、子供が食べるのであればわたぬきは必須とも言えますよ。
大人でも、苦味が嫌でさんまを自宅で作らない…という方もいますよね。
そのような方は是非、下処理の中でひと手間を加えてみてください。
食べたい日の前日から準備をするというデメリットはあります。
でもその分、臭みも取れて食べやすいさんまの塩焼きが完成しますよ!
時間がない日にはおすすめできません。
今日は時間に余裕がある!という日は、是非お試しくださいね。