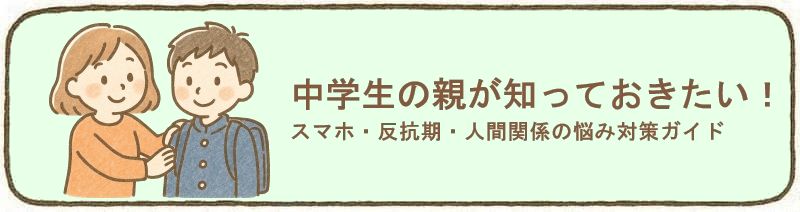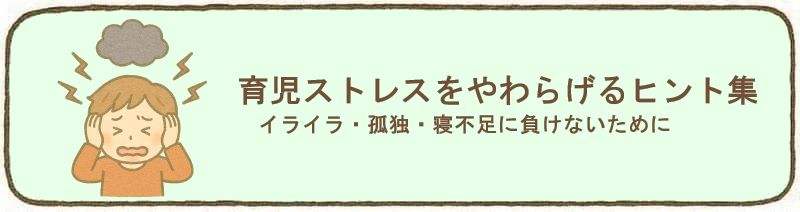思春期になると、子どもも親も
「最近よく怒るようになった」
「理由もなく泣いてしまう」
「体調が悪いと言うけど検査では異常なし」
と戸惑うことが本当に増えますよね。
私も親として何度も経験し、どうしたらいいか何日も悩みました。
思春期は心と体が急激に変わる時期で、そのストレスがいろんな形で現れるんです。
時には本人ですら気付かずに不安やイライラが募り、それが家族にも伝わってしまうこともありました。
だから親も子も、何も知らずにいるとさらに不安が増してしまうんです。
この記事では、そういった不安を少しでも和らげられるように、原因や症状、私の体験談や感じたこともたっぷり交えながら、親ができることをより詳しくお伝えしますね。
あなたが一人で悩まないためのヒントがきっと見つかるはずです。
はじめに
思春期は、子どもにとって人生の大きな節目であり、今までに感じたことのないような葛藤や不安を抱える時期です。
心も体も成長しながら、自分でも扱いきれない不安定さに悩むことが多くなり、それが周りの人にも伝わってしまうことがあります。
親としても、
- 私の育て方が悪かったのかな?
- もっとこうしてあげればよかったのかな?
でもそれは決して悪いことではなく、誰にでも訪れる成長の一環なんですね。
むしろ、そうして悩みながらも子ども自身が乗り越えようとしている証拠です。
私も最初は戸惑い、何度も迷いましたが、「この時期はこういうものなんだ」と知るだけで、気持ちがラクになり、少し肩の力が抜けたのを覚えています。
子どもの変化を恐れず、見守ってあげる勇気が親にも必要なんだと思いました。
思春期にストレスを感じる理由とは?
ホルモンバランスの変化による影響
思春期はホルモンが急激に変化するため、感情のコントロールが難しくなります。
自分で感情を持て余してしまうことも多く、イライラしたり落ち込んだりしてしまうのは自然な反応です。
私の息子も、理由もなく機嫌が悪くなったり怒ったりして、後で「自分でもわからない」と言っていました。
親としては理不尽に感じることもあるけれど、それも成長の証なんですね。
私自身も親として何度も悩みましたが、ホルモンの変化がどれだけ大きいかを知ることで、見守る覚悟ができました。
人間関係の悩みやプレッシャー
友達付き合いや部活、勉強…学校生活は思った以上にプレッシャーがかかります。
クラス替えや仲間外れ、部活での上下関係など、大人から見ると些細に思えることが本人にはとても重く感じられるんですね。
私の娘も一時期、「友達に嫌われたかも」と不安になり、学校に行くのが怖いと言っていた時期がありました。
子どもなりに必死でがんばっているんです。
その頑張りが裏目に出て疲れ切ってしまうこともありますし、親が無理に励ますとかえって追い詰めてしまう場合もあるので、そっと寄り添うことが大切だと思います。
自分自身のアイデンティティの揺らぎ
「自分はどんな人間なのか」「これからどうなるのか」と悩むのも思春期の特徴です。
社会や家族の中で自分の居場所を探し、自分自身が何者かを考えるのはとても苦しいことなんですね。
私自身も当時、なんとなく周りと比べて落ち込むことが多く、「早く大人になりたい」と思いながらも不安ばかり感じていましたし、なかなか答えが見つからずにもがいていたのを覚えています。
こうした悩みを繰り返しながら成長していくので、親は焦らずに見守る気持ちを持つといいですよ。
思春期ストレスの主な症状
心に出る症状(イライラ・不安・落ち込みなど)
気持ちが不安定になりやすく、ちょっとしたきっかけでイライラしたり泣いてしまったりします。
娘は何もない日に突然「もうイヤ!」と泣き出したことがあって、私も一緒に泣いてしまったこともありました。
何度も繰り返されるうちに、親としてもどうしたらいいかわからず、戸惑う場面が多かったです。
時には、笑っていたかと思えば急に落ち込み、「なんで生まれてきたんだろう」とつぶやく姿を見て胸が痛くなることもありました。
そんなふうに、感情の起伏が激しくなるのがこの時期の特徴なんですね。
体に出る症状(頭痛・腹痛・眠れないなど)
「お腹が痛い」「寝られない」と言うのも、実はストレスのサインなんです。
病院で診ても異常が見つからないことが多く、「気のせいじゃないの?」と言いたくなるけど、子どもにとっては本当にしんどいんですね。
うちの息子も、テスト前になると毎晩のようにお腹を抱えてうずくまり、「寝られない」と泣いていたことがありました。
こうした体の不調は、見過ごされがちですが、大切なSOSです。
学校生活や家庭で見えるサイン
遅刻や欠席が増えたり、何もしたくないと無気力になったり、逆に親に対して暴言を吐くこともあります。
私も息子から「うるさいな!」と言われたときはショックでしたが、今思えば心のSOSだったんですね。
家でずっとスマホばかり見ていたり、部屋に閉じこもって出てこない姿を見て、「何かがおかしい」と感じることもありました。
学校でも先生から「授業中にぼーっとしている」と言われたことがあり、こうした変化が見えたら、早めに気づいてあげることが大事だと痛感しました。
放っておくとどうなる?ストレスが引き起こすリスク
不登校や引きこもりにつながることも
強いストレスを抱え続けると、学校に行けなくなったり、家から出られなくなることもあります。
私の友人の子も一度そうなってしまい、完全に回復するまでにはとても時間がかかり、家族もたくさん悩みました。
一度不登校や引きこもりが長期化すると、周囲との関係を取り戻すのも難しくなり、子ども自身の自己肯定感がどんどん下がってしまうこともあります。
親もつい「なんで行かないの?」と言いたくなりますが、その気持ちをぐっとこらえて見守る覚悟が大切だと感じました。
心の病気の前兆かもしれない
心の不調は、うつ病や不安障害の前触れであることもあります。
ちょっとした変化に気づいてあげることが、早期のサポートにつながるんですね。
私の知人の子は、最初は「最近元気がないな」くらいでしたが、だんだん笑顔が減って無気力になり、病院で診てもらうと心の病気と診断されました。
でも早めにサポートができたことで、今では少しずつ元気を取り戻しています。
親の「おかしいな」という小さな違和感が、子どもを守るきっかけになると思います。
親や周囲にできるサポート方法
まずは「話を聞く姿勢」を大切に
「何があったの?」と詰めるより、「そばにいるからね」というスタンスが大事です。
私も最初はアドバイスばかりして失敗しましたが、黙って寄り添うだけで表情が和らぐことも多いです。
子どもは言葉にしなくても「味方がいる」と感じられると、少しずつ安心して自分の気持ちを話せるようになるんですね。
時には全く話してくれない日が続くかもしれませんが、それでもそばで見守り続けることが信頼につながると感じました。
無理に解決しようとしないこと
親はつい「こうしたらいい」と言いたくなりますが、それがプレッシャーになることもあります。
アドバイスは一見良かれと思っていても、本人が受け取れるタイミングでないと逆効果になることもあるんですね。
私も「学校に行ったら気がまぎれるよ」と軽く言ってしまい、余計に娘を泣かせてしまったことがありました。
それ以来、無理に答えを出そうとせず、子どもが自分で考えられる時間を大事にするようにしています。
焦らず見守るのも立派な支え方だと思います。
専門家への相談も視野に入れる
担任の先生やスクールカウンセラー、地域の相談窓口など、親子だけで抱え込まなくてもいいんです。
第三者が入ることで気持ちがラクになることもありますよ。
相談先によっては親が気づかなかった視点からアドバイスをくれることもあります。
そして、親自身の気持ちも軽くなるので、遠慮せずに頼ってみてくださいね。
私も一度カウンセラーの方と話して「それでいいんですよ」と言われたとき、心が救われるような気持ちになりました。
自分でできるストレス解消法
運動や趣味で気分転換する
体を動かすと気持ちもスッキリしますし、趣味に没頭する時間は心の栄養です。
息子はランニング、娘は絵を描くのがストレス発散になっていました。
運動といっても本格的なスポーツでなくても散歩やストレッチ、好きな音楽に合わせて体を動かすだけでも十分なんです。
趣味も、絵や音楽、料理、ゲームなど、自分が夢中になれるものなら何でもOK。
新しい趣味を見つける時間も、リフレッシュになりますよ。
友達や信頼できる人に相談する
親以外に話せる相手がいるのは心強いものです。
私も学生時代、親友に悩みを聞いてもらうだけで救われた経験がありますし、息子も「友達にだけは話せる」と打ち明けていました。
話すだけで心が軽くなることも多いですし、思わぬヒントや勇気をもらえることもあります。
友達以外にも、学校の先生や祖父母など、信頼できる相手が一人いるだけで安心感が違うんですね。
生活リズムを整える
夜更かしや偏った食生活は心の健康にもよくありません。
朝日を浴びて、決まった時間に寝る習慣をつけると、少しずつ調子が上向くことが多いです。
休日の寝だめや食事の抜きすぎなどはストレスをためやすいので、できるだけ規則正しいリズムを意識してみてください。
朝ごはんをしっかり食べる、寝る前にスマホを控えるだけでも違いますし、生活が整うと気持ちにも余裕が生まれやすいんです。
まとめ
思春期のストレスは、子どもにとっても親にとっても本当に大変でつらいものです。
でも「みんなが通る道」だと知るだけで、気持ちがかなりラクになることも多いんですよ。
無理に急いで変えようとせず、そばで見守りながらサポートしてあげることが何より大切です。
それだけで子どもにとっては大きな安心感となり、心強い支えになります。
あなたの子どもも、時間をかけて自分なりのペースで乗り越え方を見つけていけるはずです。
焦らず、一歩ずつ、寄り添いながら一緒に進んでみてくださいね。