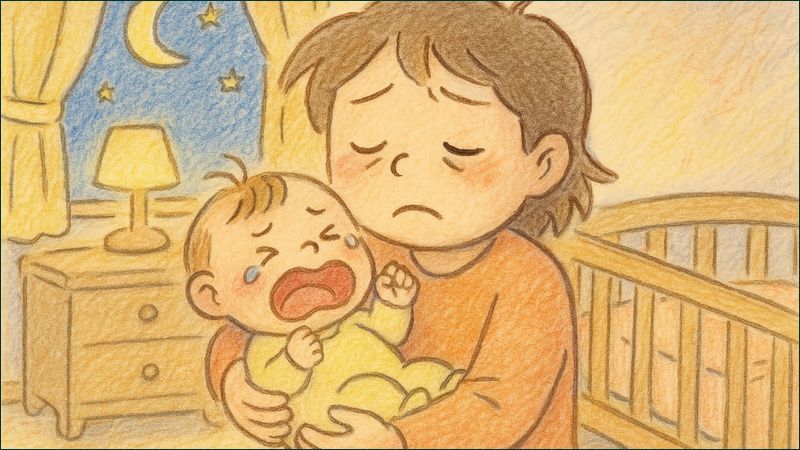
赤ちゃんの夜泣きが続くと、ママもパパも心身ともに疲れてしまいますよね。
毎晩何度も起きて、仕事や家事との両立でヘトヘトになり、心が折れそうになる気持ちもよくわかります。
私自身も娘の夜泣きが始まったときは、何をしても泣き止まず、つい「しばらく放っておこうか…」と悩んだことが何度もありました。
しばらく様子を見てもいいのか、それともすぐに抱っこすべきか、判断に迷って辛い夜を過ごしました。
でも、夜泣きを放置するのにはリスクがあるんですし、親子にとって大事な時期だからこそ知っておいてほしいことがたくさんあります。
この記事では、私が実際に試して感じたことも交えながら、夜泣きを放置したときに考えられる影響や、親の心も守りながらできる具体的な対策まで、丁寧にお伝えしていきますね。
少しでも気持ちが軽くなって、赤ちゃんとの時間を前向きに過ごせるお手伝いができたら嬉しいです。
夜泣きを放置してもいいのか迷うママ・パパへ
夜泣きが始まるのはいつ頃から?
多くの赤ちゃんは、生後6ヶ月ごろから夜泣きが始まることが多いです。
早い子では3ヶ月くらいから泣く子もいて、個人差がありますね。
私の娘もその頃から、夜中に何度も泣いて起きるようになり、こちらも眠れない日が何週間も続いていました。
これは、赤ちゃんの睡眠サイクルがまだ未発達で深い眠りが少なく、音や夢に敏感だからです。
寝てくれたかと思えばまた泣く…という繰り返しで、「いつまでこんな夜が続くんだろう…」と不安で涙が出た日もあります。
でも、成長とともに少しずつリズムが整って落ち着いてくる子がほとんどなので、焦らずに見守る気持ちが大事です。
放置する育児法もあるけど日本では賛否両論
欧米では「泣かせる育児」として短時間の放置が推奨される場合もありますが、これは赤ちゃんの自立を育むためだといわれています。
一定時間泣かせて様子を見る「セルフスージング法」という名前で広まっていて、実際に成功した家庭もあります。
でも、日本ではスキンシップや添い寝が文化に根付いているので、「泣いたら抱っこしてあげる」のが一般的です。
私も試しに10分ほど放置してみましたが、泣き声がどんどん大きくなり、こちらが胸が苦しくなってしまって結局抱き上げました。
その後は逆にしがみついて泣き続けたので、うちの子には合わなかったのだと思います。
こうした文化や赤ちゃんの性格によっても向き不向きがあるんだなと感じましたし、夫婦で相談しながら無理のない方法を選ぶことが大切ですね。
夜泣きを放置することで起こる悪影響
赤ちゃんのストレスや不安が増す可能性
泣いても誰も来てくれない…そんな不安が積み重なると、赤ちゃんのストレスが大きくなります。
私の娘も、泣き疲れて寝る姿がとても寂しそうで、こちらも涙が出てしまったことがあります。
泣き止んだからといって安心できないんですよね。
泣くことで気持ちを伝えるのが赤ちゃんにとっての大事な手段なので、そのたびに反応がないと「どうせわかってもらえない」という気持ちになりやすいといわれています。
長く続けると、夜泣きの頻度が増したり、不安定な気質になる子もいるそうです。
私も、何日か連続で泣き疲れて寝た娘を見て、胸が締めつけられるような気持ちになりました。
親子の信頼関係に悪影響が出るリスク
抱っこしてもらえないことで「泣いても意味がないんだ」と赤ちゃんが感じてしまい、親子の絆が弱くなることもあります。
私も、一時期甘えてこなくなった気がして、とても胸が痛みました。
泣いたときに必ず反応してもらえるという経験の積み重ねが、赤ちゃんにとっての安心感や信頼感につながるので、無視が続くと親子の距離感が広がりやすいんです。
そうなると、昼間の遊びや授乳の時間でも以前のように笑ってくれなくなったり、視線をそらすようになったりすることもあって、親としても不安が増します。
私もそのときはどうしたらいいのかわからず、後でたくさん抱きしめることで少しずつ戻っていったのを覚えています。
ママ・パパ自身の罪悪感やストレスが大きくなる
泣き声を無視するのは、親にとっても本当に辛いものです。
私も放置した夜は「もっと抱っこしてあげればよかった…」と後悔してしまい、気が張って眠れませんでしたし、翌朝も罪悪感が残ってしまいました。
頭では「少しぐらい放っておいてもいいのかな」と思っても、心がついていかず、胸が締めつけられる思いでした。
無理に我慢しようとすると、ますますストレスが積み重なってしまうので、無理せず赤ちゃんの気持ちに応えてあげるほうが親にとっても気持ちが楽になります。
無理に我慢するのはおすすめしません。
夜泣きを放置するメリットはある?
自力で眠る力を育むという考え方も
泣いても少しの間は様子を見ることで、赤ちゃんが自分で眠る力を育てるともいわれます。
こうした経験を積むことで、夜中に目が覚めても自分で寝直せるようになっていく子もいるそうです。
実際、私の知り合いの中にはこの方法で成功し、2歳になる前に夜泣きがなくなったというママもいます。
ただし、長時間放置は逆効果なので、短時間ならOKくらいの気持ちで。
赤ちゃんの様子をよく観察しながら、泣き方が変わったり苦しそうならすぐに対応する柔軟さも大事です。
「泣かせて寝かせる育児法(ねんねトレーニング)」とは
「フェードアウト法」という方法なら、赤ちゃんの不安を最小限にして自立心を育てられます。
これはいきなり放置するのではなく、短い間隔で様子を見に行くのを繰り返し、少しずつ間隔を伸ばしていく方法です。
私も少しずつ間隔を空けながら様子を見に行く方法を試しましたが、最初は10分ごとに見に行って、次第に15分、20分と延ばしていき、だんだんと夜中の授乳が減りました。
このやり方だと、赤ちゃんも安心しながら「一人で寝られるんだ」という感覚を持てるので、親も気持ちが楽になりますし、私も結果的に以前よりぐっすり眠れる日が増えました。
夜泣きを放置しないための対策とコツ
赤ちゃんが安心して眠れる環境作り
寝室の温度は22~24度くらいに保ち、湿度も50~60%に調整するといいですよ。
私も試しに加湿器を置いてみたり、エアコンの風向きを調節したりといろいろ試しました。
薄暗い照明や、ゆったりした音楽も効果的でしたし、お気に入りのぬいぐるみを近くに置いてあげると安心した表情になることもありました。
寝具も汗を吸いやすい素材に変えたら、ぐずりが減った気がしますし、枕元にほんのり良い香りのアロマを置いたときもぐっすり眠ってくれました。
さらに寝る前に部屋の空気を入れ替えて、静かで心地よい環境を整えると、泣かずに寝ついてくれる日が増えてきました。
こうして少しずつ試しながら、その子に合った環境を見つけていくのが大切だなと感じました。
お昼寝や生活リズムを整える
お昼寝のし過ぎや夜遅くまで遊ぶと、夜泣きが増えることがあります。
毎日同じ時間に寝るようにして、早寝早起きを意識したら、うちの子は夜泣きが減りました。
さらに、昼間にたくさん外で日光を浴びて遊ぶようにすると夜はぐっすり眠るようになったので、なるべく午前中に公園に出かける習慣をつけました。
お昼寝も遅い時間は避け、夕方には必ず起こすようにしたら、夜の寝つきがずいぶん楽になりました。
ママ・パパの心身を守る工夫も大切
夜泣き対応を一人で抱え込むのは危険です。
私も夫や実家にお願いしたり、日中に少しでも仮眠を取ったりして、気持ちを切り替えるようにしていました。
週末には夫と「どちらが夜中に起きるか」を交代制にして負担を軽くしたり、祖母に数時間見てもらって一人でカフェに行く時間を作ったりもしました。
自治体の育児相談や子育てサロンに参加して、同じ悩みを持つママさんと話すだけでも気持ちが軽くなります。
頑張りすぎず、周りに頼るのが本当に大事なんだなと実感しました。
まとめ:赤ちゃんの気持ちに寄り添った夜泣き対策を

夜泣きは赤ちゃんが「安心したいよ」というサインです。
無理して全部応えようとする必要はありませんが、完全に無視するのも良くないんですね。
私も、泣いている娘を見ながら「何ができるかな?」と一つずつ試してみて、抱っこしたり話しかけたり、時には少し様子を見たりと色々やってみました。
短時間の放置としっかり抱っこのバランスを取りながら、夫婦で支え合っていくと気持ちがぐっと楽になりますし、赤ちゃんも安心して眠れるようになりますよ。
疲れたときは周りを頼って、親も自分を労わりながら、赤ちゃんと一緒にゆっくり成長していきましょうね。
大変な時期ですが、そのぶん絆が深まる大事な時間でもあります。